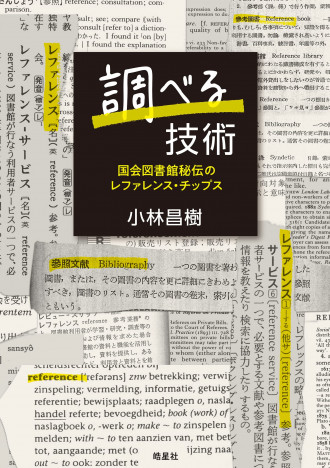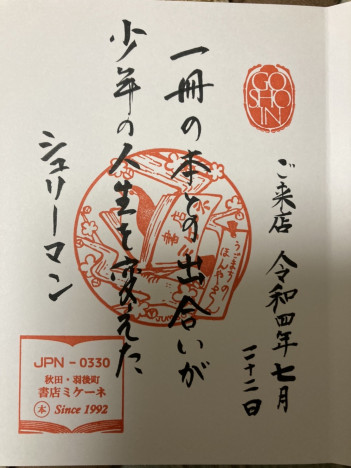本屋での“立ち読み”は日本独自の風習だった? 知られざる江戸時代のルーツとは

本屋ではお馴染みの光景として知られる「立ち読み」。あまりにも長く読んでいる立ち読み客のところへ店員が行き、迷惑そうにはたきがけをする……なんて光景が目に浮かぶ方も少なくないはずだ。
昨今では雑誌が減ってしまったことや書店そのものが少なくなったこと、本自体にカバーをかけるシュリンクなどによって、立ち読み客の姿を目にすることも減っているが、実はこの「立ち読み」は、他国ではあまり見られない日本独自の風習らしい。
なぜ日本では本を買わずに読むだけの「立ち読み」が容認されてきたのか。そして「立ち読み」文化はなにを育んできたのか。近代出版研究所の所長で、立ち読みの歴史を調べた小林昌樹氏に話を聞いた。
他の言語に「立ち読み」という言葉は、ほぼほぼ存在しません
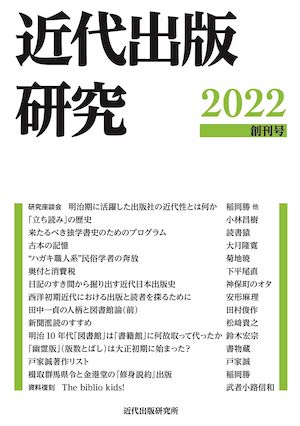
小林:考えるきっかけになったのは『公共図書館の冒険: 未来につながるヒストリー』という本で「図書館ではどんな本が読めて、そして読めなかったのか」という章の執筆を担当したことです。現在、ふつうの図書館ではアイドル写真集やアダルト雑誌も読めないのが当たり前です――特殊な図書館、たとえば国会図書館では読めますが。けれど、これが時代を遡ると、戦前は山手樹一郎の大衆小説やマンガなども読むことはできなかったんです。この論考では、「長い目で見ると、図書館で読むことができない書物の種類には変化がある」ということを書きました。
その後、より広い「読書の歴史」が気になって調べ始めました。すると古書は残っていても「誰がどうやって読んでいたか」は意外と調べにくい。一番研究が進んでいる新聞の話をすると、かつて明治時代の新聞は「新聞縦覧所」という場所で読むもので始まりました。新聞は後に本屋で買えるようになり、それが宅配に切り替わるのは明治の終わり頃でした。新聞縦覧所の発展なんかも面白い。
――靖国神社の新聞縦覧所の写真を見ると、何だかカフェみたいな感じですね。

小林:そうなんです。まさにカフェやマンガ喫茶みたいな感じで、明治半ばから新聞縦覧所は出会いの場に変貌していきました(笑)。本来の使い方を逸脱して、新聞縦覧所で不埒な行為をする人もいたらしい。2010年から東京都では「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」によって、ネットカフェの利用客の本人確認が必要になりましたが、これにも本来の漫画を読むためでなく、男女がよからぬ目的で利用するのを防ぐ面がありました。新聞縦覧所も同じパターンですね。
新聞縦覧所のように、違う用途に変質する例も含めて考えていたら、自分が本屋で本を買わずに「立ち読み」していたことに気が付いたんです。「○○はいつからあったのか?」という「事物起源」についての質問は、国会図書館でレファレンス司書をしていた頃によくあったのですが、よくよく考えると「立ち読み」の起源について調べたことはなかった。これは研究のしがいがあると思いました。
――具体的にどのように調べていったのでしょうか。
小林:明治23年(1890年)の丸善の銅版画を見ると、江戸時代と同じく本が座売りされていることがわかります。つまり130年前から今に至るどこかの時点で、本屋が閉架の座売りから現在の開架に切り替わり「立ち読み」が可能になった、と仮説が立てられますね。これをもとに文献を集めながら年代を絞っていきました。それから「立ち読み」という言葉がいつ生まれたかを調べるのも大切。その使用の先頭を特定できれば、その少し前に「立ち読み」が発生したことがわかる。
――「立ち読み」は西洋にないという話も書かれていて、なるほどと思いました。
小林:私は一度も海外旅行をしたことがないのですが、「立ち読み」の文献を集めると、昭和30年代の戦前くらいまでの海外渡航者が「外国にはない」と書き記しているんですよ。「本屋に入ると『何が必要?』と聞かれるが『特にない』と返すと怪訝な顔をされる」と。
さらに外国語の辞書も片っ端から調べましたが、他の言語に「立ち読み」という言葉は、ほぼほぼ存在しません。「立ち読み」という項目が書かれた日本語·外国語辞書もあるにはあるのですが、「立って読む」とか「立ちながら読む」といったすごく説明的な翻訳ばかりなんです。だから現象としては言葉にできても、習慣は存在しないのでは、と思い至ったんです。
――なるほど。
小林:ウィキペディアも活用しました。以前の図書館業界では「使うな」と言われていましたが、ウィキペディアは他の言語版と比較することに価値があるんです。「立ち読み」という言葉は日本語以外に、中国語、韓国語、台湾語にしかない。戦前に日本が統治していたエリアが含まれているので「これは日本の本屋の影響が大きそうだ」と、推測しました。日本で生まれ育つと、当たり前すぎて気付かないことってたくさんあるんですよね。「いただきます」の習慣だって大正時代に始まった意外と新しいものですし、「立ち読み」も同様に比較的新しい習慣なんです。