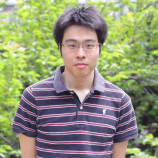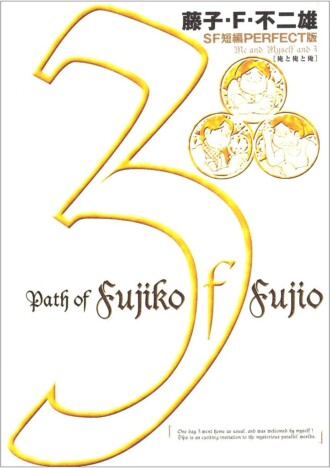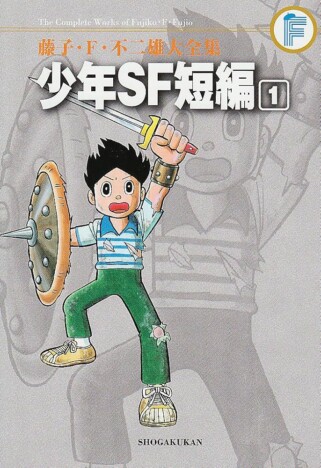藤子・F・不二雄 SF短編の最高傑作『みどりの守り神』とはどんな物語なのか?

さて、ここからギアをあげる。筆者はこれまで、本サイトにおける藤子・F・不二雄のSF短編の考察記事においては、極力「ネタバレ」をしない方向で執筆を進めてきた。が、『みどりの守り神』においては、「ネタバレ」をせずにその核心に迫ることが非常に難しい。そのため、以降は作品の終着点までを明かすことをご理解いただきたい。
冒頭で、タイトルの「みどり」の意味について疑問を提起した。表面的には主人公となる少女の名前という意味であったが、実はもうひとつの意味がある。植物を指す「みどり」である。そして、タイトルにも見られるこうした二重性こそが、本作の要となる。
作品のなかで、みどりは生物が消えたことへの違和感とともに、もう一つの違和感を覚える。それは植物のプレゼンスである。旅の過程で、植物はことあるごとにふたりの前に現れる。空腹を覚えたみどりの前には、豊潤な味わいの木の実が現れるし、みどりの痛めた足はわずかな間に完治し、喜びの声をあげる彼女のまわりには大量のコケが繁茂している。そして川を下るなかでいかだが壊れ、川に沈んだはずのふたりは、やがて地上で、植物のつるに絡まりながら、自分たちがまだ生きていることに気づくのである。
少女みどりにとっての「守り神」であり、みどり色をした「守り神」――。ここまでくると、植物が彼らを守っていることに否応なしに気づかされるが、では、その原因は何なのだろうか。植物の謎はなかなか明かされないが、いっぽうで、生きて動くものが何も見つからなくなったことの理由は、やがて読者に了解される。どこかの国が兵器として開発した細菌が、うっかり外部に漏れ、爆発的にあらゆる命を奪っていったことにあったというのだ。廃墟と化したビルのなかにあった新聞で、災厄の一部始終を知った坂口は発狂し、みどりのもとを去ってゆく。ひとり残され、孤独に耐えきれなくなったみどりは自ら死を選ぼうとし、かみそりに手をかける。しかし、やがて彼女は意識を取り戻し、そばに坂口ではない、見知らぬ男性がそばにいることに気づく。
白河貴志と名乗るその男性は、おそらくは自分たちが一度は死に、その体が何百年も保存されていたことを語ったうえで、なぜ自分たちが文明の失われた世界でよみがえったのか、考察を口にする。植物と動物は、空気の炭酸同化作用によってともに生きてきたが、動物がいなくなったことでバランスが崩れ、植物が必要とする炭酸ガスが不足してきた。動物のカムバックをもとめる植物は、短い期間で急速に進化を遂げていった。運動性を持った植物や、動物の細胞を再生させる能力を持った植物があらわれ、そうして自分たちも、この世界に再びよみがえったのだと。そして、「自分たちと同様に再生した人間もいるはず」という希望を持ったふたりは、新たな旅に出ることを決める。
このラストからわかることは何か。それは動物と植物の、ある種の対等性である。
ここまでの物語では、植物は飢え、けが、入水……と少なからぬ局面でピンチに対峙する人間たちを、身近でそっと支える「守り神」のような横顔を見せていた。さらには、無数の木や草が東京のビル群を覆う、ダイナミックな見開き2ページの存在もあいまって、彼らが地球の王者となったかのような印象も醸し出していた。
しかし植物は、神でも王者でもなかった。自分たちとは異なった生命のあり方を持つ、人間をふくめた動物とともに生きようとする、動物の「仲間」であったのだ。つまり、作品全体を通してみれば、植物は人間=動物の理解を上回る、動物を凌駕する存在から、終盤になるにつれて動物と融和し合う仲間へと、印象は変化していく。
同時に、こうした印象の変化は、人間どうしの関係においてもまた見られるだろう。前述のように、坂口とみどりの関係は、坂口がみどりを抑圧する、一方が優位であるかのような印象が目立ったものの、そうした関係はやがて終焉を迎える。あらたに目の前に現れた白河は、発言の節々からも温厚で知的な人物であることが了解され、おそらくはみどりとも良好な関係を築くことができるだろう。こうして、植物と人間=動物の関係に加え、人間どうしの関係も一方の優位から融和へと変わっていき、そこにこそ先ほど提示した「二重性」がある。
『みどりの守り神』は、藤子・F・不二雄のSF短編の中でも、最高傑作として推す声が多い。ディザスター作品としての面白さ、極限状態に直面した人間の弱さや醜さ、作中に描かれる植物のダイナミックさと多彩さ、絶望的な状況の中で提示される一筋の希望の鮮やかさ……。じっさいに本作の見どころは尽きないが、同時に、「人間と自然との共存」という大きなテーマを押しつけがましくなく、「二重性」の枠の中に組み込んだ構築力の巧みさも指摘できるのではないか。
藤子作品における「人間と自然との共存」というテーマは、たとえば後年の『ドラえもん のび太とアニマル惑星』『ドラえもん のび太と雲の王国』といった作品でも見られる。しかし、こうした作品では環境問題への警鐘や文明社会への批判が登場人物のセリフとして長々と語られるなど、メッセージがあまりにも直接的で、そこに対する違和感もまた拭えない(ライターの稲田豊史は著作『ドラがたり のび太系男子と藤子・F・不二雄の時代』で、短編「さらばキー坊」なども含めて、エコに主眼を置いた『ドラえもん』諸作品のそうした説教臭さを批判している)。『みどりの守り神』は物語としての面白さに主眼を置きつつも、同時に「二重性」という枠で、作中に鋭い文明批評を挟みこむことに成功している。そうした技術性の高さにこそ、本作が忘れがたい魅力を放つ理由の一端があるように感じられるのである。