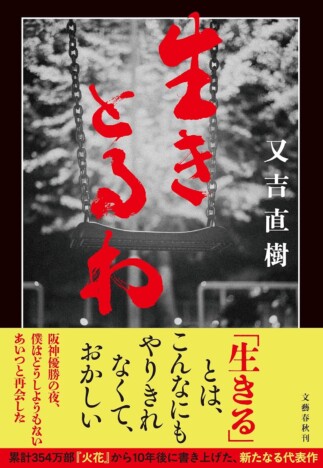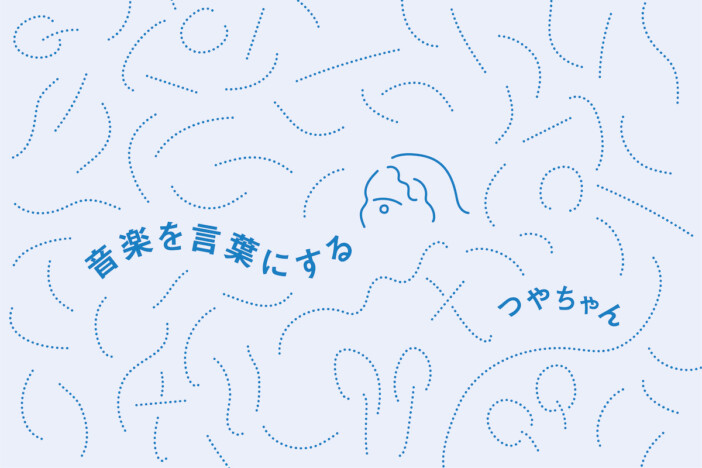【連載】福嶋亮大「メディアが人間である」 第8回:モデル対シミュレーション

3、現実対虚構からモデル対シミュレーションへ
繰り返せば、ピアノは、近代の機械論的な世界像の格好のモデルである。ピアノがさまざまな楽器のシミュレーションを実行する機械(メタ楽器)であるように、コンピュータはメディアそのもののシミュレーションを実行する機械(メタメディア)である(第4回参照)。同じく、ソーシャルメディアは社会そのもののシミュレーションを実行する機械であり、AIは知能そのもののシミュレーションを実行する機械であり、メタバースは現実そのもののシミュレーションを実行する機械である。これらの機械は、自分以外のものになりすます力をもつ。メディア史の展開とは、まさにこのシミュレーションの力の拡大と等しい。
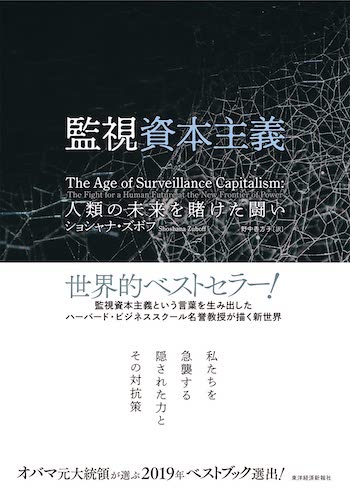
さらに、今日のデジタル資本主義は、シミュレーションや予測という認知能力を商品に変える水準にまで達した。ショシャナ・ズボフは近年、この新しいタイプの資本主義を「監視資本主義」と呼んで、その諸問題を指摘している。
ズボフによれば、現代の巨大IT企業は、人間の行動履歴を「原材料」としてそれを「予測製品」に変える。そこでは、インターネット上での個人のプライヴェートな経験はデータ化されたうえ、そのデータに基づいて、個人の未来の行動が予測され「修正」される。ズボフはこのビッグデータとアルゴリズムに基づく「行動先物市場」では、情報が自動化されるだけではなく、人間までもが自動化されてしまうと警告している(※5)。
この監視資本主義もまた、人間の一歩先の「影」を捕捉し、それを富に変えるシミュレーションのシステムである。もとより、監視資本主義は人間の思考をセメントでがちがちに固めてしまうものではない。ちょっとした自己訂正や気分の波長の移り変わりのようなものも「予測製品」の内部には含まれる。行動先物市場はその程度の変化のマージンは許容している。インターネットのユーザーが大きな違和感を抱くことのないまま、そのアルゴリズムに操作されるのは、そのためである。
これらの事例から言えるのは、≪現実対虚構≫という旧来の線分に基づく思考が、すでに限界を迎えつつあるということだ。21世紀の主要な紛争地帯は、むしろ≪モデル対シミュレーション≫にある。人間の知能や言語や文化を学習したAI、社会を学習したソーシャルメディア――それらは虚構だからではなく、シミュレーション(模倣)だからこそモデルとのあいだに軋轢や混乱を生み、やがてモデル(実在)そのものと溶け合ってゆく。ゆえに、モデル対シミュレーションと言っても、それは単純な優劣や対立の関係を意味しない。シミュレーションの増加はモデルの輪郭をにじませ、モデルとの区別をもあいまいにするからである。
この≪モデル対シミュレーション≫の構図を捉えるのに有効なのは、先述したピアノに加えて、写真である。写真を考えるのに、≪現実対虚構≫という枠組みはもともとさほど役に立たない。というのも、写真は世界からデータを取得し、それを瞬時にシミュレーションに変え、モデル(実在)になりすまそうとするのだから。カメラとは、現実のシミュレーションをほとんど自動的に制作する機械である。シミュレーションの思想家ボードリヤールが、写真に強い関心を示したのも決して偶然ではない。
※5 ショシャナ・ズボフ『監視資本主義』(野中香方子訳、東洋経済新報社、2021年)。
4、メディアの再人間化

このようなシミュレーションの時代の到来は、当然、メディア美学にも多大な影響を及ぼす。従来の社会批評的なメディア論は「人間拡張」(マクルーハン)のプログラムを読み替えるようにして、いわば「非人間的なもの」の発見に駆り立てられてきた。第4回で述べたように、20世紀のモダニズム芸術の関心は一種のエイリアン、日本的に言えば「妖怪」の探索にあった(※6)。映画のスクリーンにせよ、絵画の画布にせよ、それらはまさにエイリアン(妖怪)の住まう媒体である。
しかし、本連載で繰り返し述べているように、この「人間拡張」のプログラムはモダニズムにおいてピークに達し、21世紀にはむしろその反転(人間への旋回)が生じたように思える。それを≪メディアの非人間化からメディアの再人間化へ≫とまとめてもよいだろう。
現に、生成AIも人間からかけ離れたエイリアン的な知能ではなく、あくまでビッグデータとして蓄積された「みんなの意見」(集合知)を洗練させ、利用しやすくする装置である。それは人間の知能(推論や計算)を部分的にシミュレートし、強化し、顕在化させたうえで、得られた情報をチャットのインターフェースに落とし込む。それによって、あくまで人間的な忠実さや親切さ、つまりパートナーシップが擬態されるのである。
むろん、このような見立てには反論もあるだろう。実際、巷を見れば、AIが人間をはるかに超えた知性に進化するという議論は存在する。レイ・カーツワイルの主唱したシンギュラリティ論はその典型である。カーツワイルはいわばオカルト的に単純化されたマクルーハンのような著述家であり、テクノロジーの進化がいずれ「知能爆発」を起こし、人間拡張をも飛び越して、トランスヒューマンの次元に到達すると予想していた。カーツワイルの考えでは、この新しい知性と接触するとき、人間には永遠の命が与えられることになる。同様に、ユヴァル・ノア・ハラリの『ホモ・デウス』もまた、テクノロジーの進化を不死性のテーマと結びつけた。

しかし、池田純一が指摘するように、「死の克服」をめざすカーツワイルのシンギュラリティ論は今や通俗化し、ITの消費文化のなかに吸収されている。もともと、カーツワイルのシンギュラリティ論とは、今の人類の時代が終わり、新たな人類が誕生するというキリスト教の終末論と親和性の高い言説である。しかし、今の情報環境は、このような誇大妄想的な「大きな物語」ではなく、むしろ日々の健康管理をアプリで実行せよという、ありふれた勧告に向かっている。つまり、シンギュラリティ論は神学から「一つの技術」へと旋回しつつある(※7)。
こうして、人間拡張のプログラムは日常化する。しかしこのとき、再人間化したメディアは、確かに「スマート」な印象を与える一方、人間どうしの「鏡」の反射のゲームのなかにユーザーを閉じ込めてしまう。だからこそ、宇野常寛の近著『庭の話』のように、モダニズムの美学やシンギュラリティの神学に訴えることなく、人間外の事物との「交通空間」を回復せよというメッセージが説得力をもつのだ。宇野の掲げる≪庭≫とは人間から再び引き離されたメディア、私なりに言い換えれば、鏡のように反射しないメディア、あるいはシミュレーションを休止したメディアということになるだろう。このテーマは、もう少し後で改めて取り上げ直したい。
※6 筋金入りのモダニストとして知られる造形作家の岡崎乾二郎が、水木しげるの漫画の「妖怪」に批評的な関心を示すのも偶然ではない。『而今而後』(亜紀書房、2024年)参照。
※7 池田純一「シンギュラリティはより近く、世界はより複雑に」『WIRED』2025年1月9日公開の記事。