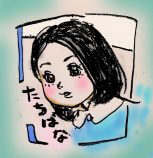立花もも新刊レビュー 井上荒野、23年ぶりとなる恋愛小説からSNSの承認欲求まで……今読むべき3選
発売されたばかりの新刊小説の中から、ライターの立花ももがおすすめの作品を紹介する連載企画。数多く出版されている新刊小説の中から厳選し、今読むべき注目作を紹介します。(編集部)
井上荒野『だめになった僕』(小学館)

音村綾はマンガ家で、ふだんは信州でペンションを経営しながら、実母と夫、そして息子と暮らしている。初のサイン会のため、久しぶりに上京した彼女の頭を占めているのは、かつて東京で出会った祥川涼という男のことだ。ネットで誹謗中傷をくりかえすのは彼ではないかと疑うから、だけでなく、綾はもうずっと、何年も彼のことが忘れられないでいる。涼もまた、アルコールに溺れながら綾を想い続けていることが、彼の視点でも語られる。そして酩酊した涼は、綾の夫と息子が見守るサイン会である事件を起こすのだけど……。
そこから物語は1年前、4年前、8年前……と二人が出会った16年前まで少しずつ遡っていく。二人はいったいどういう関係だったのか、というのも気になるけれど、「現在」では心から綾の仕事を応援しているらしい夫が、「1年前」になにかしらの〝反省〟をしているっぽいところが、まず、とても気になる。一方で、同じ時期、涼は〝僕が綾を愛しすぎているせいで、かかわった者は女も男もみんな死んでしまう〟なんて物騒なことを考えている。どういうことだろう? とページをめくるたびに、過去の事実が掘り起こされて、点と点が少しずつ線でつながり、現在の虚像が壊されていく。
愛ってなんだろう、と思う。ただ静かに、相手の幸せを願い続けていることができたら本物のような気がしてしまうけど、執着も独占欲もないその想いを、果たして愛と呼べるだろうか。だからといって、重なり合うことのない想いがぶつかりあって歪みを生み、罪を犯すことを、愛の結果と呼んでいいかもわからない。
描かれている人間模様を要約してしまえば、帯にも書かれているとおり、ありふれた恋愛だ。でも、世の中で起きる事件は、たいていありふれた関係性から生まれ、その裏には、はかりしれない感情が詰まっているのである。
中島京子『坂の中のまち』文藝春秋

まちには歴史があるということを、知ってはいても意識して生活することはない。なぜその坂には、路には、その名前がついているのか。紐解いていけばきっと、今の私たちにつながる誰かの足跡を見つけられるはずなのに、しようともしない。それがいかにもったいないことなのか、本作を読んで痛感する。
大学進学のために上京した真智は、祖母の親友である志桜里さんの家に居候することになる。坂だらけのまち、小日向に住む志桜里さんは、とりつかれたように坂の由来を語り、本棚には小日向の登場する小説(たとえば村上春樹の『1Q84』)をそろえて、細かくその意図をチェックしている。文豪の多く住んだ文京エリアゆえに、文学の知識も自然とインストールされていくのだが、それゆえか思わぬ「幽霊」に出くわしてしまう怪奇譚が、まずおもしろい。そのまま幽霊に遭遇する話が続いていくのかと思いきや、たまたま隣に座った見た目が好みの青年――亡き横光利一や小林秀雄に今なお指導を受けているかのように語るエイフクさんは現実に存在している。
過去と現在の狭間をたゆたいながらこの世を謳歌している彼はだいぶ浮世離れしているけれど、そんな彼に影響を受けながら、土地だけでなく自分の過去と現在をも見つめていく真智の、人生の散策模様が読んでいてとても心地いい。
エイフクさんは恋のアプローチも浮世離れしていて、真智が戸惑いながらも関係を育てていく家庭がとてもいとおしいのだけど、やがてコロナ禍で遠距離恋愛になった二人が、夏目漱石の小説に重ねて三角関係を展開していくのも、よかった。いろんな意味を持つ坂の中で生きる「まち」を思い浮かべながら、小日向を散策してみたくもなる。
本谷有希子『セルフィの死』新潮社

パンケーキと一緒に、映える写真を撮らなきゃ死ぬのである。「死んじゃうくらい撮影したいって言いたいんでしょ」と作中でウェイトレスが言うように、おおくの人は自撮りに必死になる若者たちを鼻で笑い、けしからんと腹を立てる。でも、本当に死ぬのだ。肉体がたとえ生きていたとしても、精神が切り刻まれて、立ち上がることができなくなるくらい、SNSにおける承認は、彼女たちの生死に直結している。
フォロワーが欲しくて欲しくてたまらない主人公・ミクルの弱点は、数字だけで評価される世界の圧倒的にシンプルさに、恋い焦がれながらも内面の複雑さを捨てられないことだ。フォロワーが増えない現実に絶望し、夜中に知人の写真を加工して投稿する衝動性はあるものの、開き直ることも心から反省することもできず、謝罪に呼び出されて向かう電車のなかで、ストレスに押しつぶされてまた死にそうになる。
〈社会的な振る舞いをすると、私の中の玉ねぎが小さくなってしまう〉〈私は私の大事な玉ねぎがむけすぎないように、鍋の中で溶けすぎないように常に火力を調整しながら生きている。〉と彼女は思う。だったらSNSなどやらなければいい、が、それができれば苦労しない。社会に適合することも逸脱することもできない彼女にとってSNSの承認だけが、生きていてもいいと思える証なのだから。
その切迫感を、笑うことなどできない。自意識と承認欲求にまみれ〈マウントを取ったり迷惑をかけることでしか他者の存在を確かめることができない〉彼女のいびつさは、私の中にもあるのだから。それでも他者と関わることをやめられない彼女が、最後に映し出すむきだしの自分――セルフィには、美しさすら感じてしまうのだ。