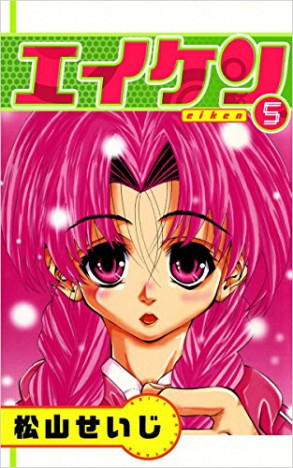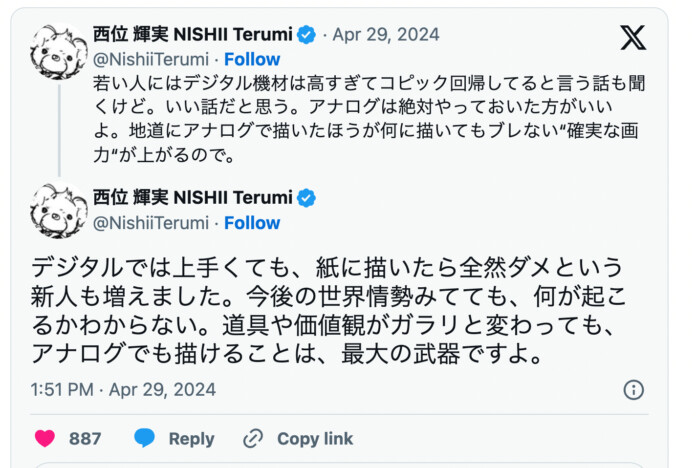名作ラブコメ漫画、生成AIでリメイク中の作業現場に初潜入 原作者・ 松山せいじに制作経緯を聞く
■あの『エイケン』を生成AIでリメイク

XなどSNS上では、連日のように生成AIについて活発な議論が展開されている。そんななか、4月25日、「まんが王国」でリリースされた一本の漫画が大きな反響を呼んだ。松山せいじ氏の名作ラブコメ漫画『エイケン』のリメイク版(正式名称は『エイケン リメイク版』)、しかもただのリメイクではなく、生成AIを使い、絵柄を含めて全面的にリメイクされた作品である。
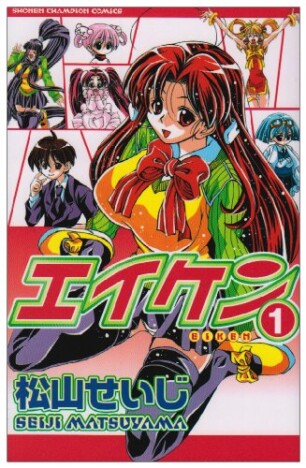
『エイケン』は2000年前後に少年漫画誌で流行が始まったラブコメ・ハーレム漫画の代表格であり、アニメ化もされた。松山せいじ氏の個性的な絵柄が、生成AIによる“現代的”な絵柄によって表現されたこともあって、ネット上では様々な議論が巻き起こった。
今回、原作者の松山せいじ氏をはじめ、ビーグリーの広報の三吉達治氏と、実際に漫画の制作を担った大森勇作氏にインタビュー。なぜ生成AIで過去の名作のリメイクを試みたのか。そして、リリース後の賛否両論など様々な反響はいかほどのものだったのか。独占インタビューで明らかにした。
■名作漫画を読んでもらいたい
――『エイケン』を生成AIの力を借りてリメイクするアイディアは、どなたが考えたのでしょうか。
松山:ビーグリーさんの発案ですね。
大森:プロジェクトが立ちあがったのは2023年の夏ごろですから、まだ1年経っていませんね。話題性のある、面白くて、新しいことをやりたいと話していたところ、生成AIを使って過去の名作をリメイクできないかという上司の提案に、私が手を挙げたのがきっかけです。
三吉:当社はクリエイターとファンを繋ぐことをミッションにしておりまして、松山先生の『エイケン』をはじめ、新旧の漫画を電子書籍化して「まんが王国」で販売しております。近年、電子書籍の普及によって、より手軽に多くの作品に触れることができるようになり、WEBTOONの登場でフルカラー作品も増えてきています。様々なジャンルの作品が増えた一方で、過去の作品が読まれにくくなってきた面もあります。また、読者からは、名作をWEBTOONのようにフルカラーで読みたいというニーズが寄せられていました。
――漫画のみならず、小説や映画も過去の名作を読んでもらうことは難しいですし、作品を知る機会も少なかったりしますよね。
三吉:そうですね。そこで、当社で何かできることはないかと考えたところ、著作権者の先生の許諾をいただき、現代に合ったリメイク版を制作して、過去の名作を掘り起こすアイディアが出ました。漫画家さんに丁寧に理念や取り組みの意図を説明し、場合によっては事前にサンプルとして制作した原稿を見ていただき、了承いただいたうえで「名作リメイクプロジェクト」を始めました。長く愛されている名作をカラー化し、さらに現代風に再構築することを目指しています。
――その一環として、生成AIを使ってリメイクされたのが『エイケン リメイク版』というわけですね。『エイケン』のほかにも、同様の作品は制作されているのでしょうか。
三吉:現在は『オレの子ですか? リメイク版』や『児童福祉司 一貫田逸子 リメイク版』など、4作品を並行して制作しています。いずれも生成AIを使用し、リメイクしています。『エイケン リメイク版』は名作リメイクプロジェクトの3作目に当たり、松山先生とは長い付き合いということもあって、相談させていただきました。
■声をかけてもらい嬉しかった

――先ほど、生成AIを使って漫画を制作している現場を見せていただきました。おそらく、多くの読者は生成AIで出力した絵を、そのままコマに当てはめていると考えているはずです。実際は相当な手直しをされていますね。しかし、これならゼロから人が描いたほうが早いのではないか、と思ってしまったのですが。
松山:僕も今日、初めて現場を見たのですが、率直に手間がかかっていると感じました。僕が週刊連載をやっていた頃と、あまり変わらない体制で作業していますね。
三吉:描いた方が早いというのはおっしゃる通りかもしれませんが、AIのメリットとして、誰が担当しても絵の水準が一定になり、統一感を出せる点が挙げられます。ただし、全体をディレクションする人は必要ですので、大森がその役割を担っています。
――大森さんは漫画の編集経験などはお持ちだったのでしょうか。
大森:電子コミックの編集には10年以上携わってきましたが、生成AIを活用した漫画の制作は初めての経験だったので、手探りで始めました。他社でも同様のリメイクをしている例はほとんどないので、ノウハウは実際に作業を進めながら構築していきました。
――生成AIを活用した漫画制作を行っているのは、ビーグリーさんだけでしょうか。
三吉:生成AIで漫画を作る取り組みは、WEBTOONなどの一部で始まっています。ただ、リメイクという立ち位置で取り組んだ例は少ないと思います。
――実際に完成した漫画を見て、どんな感想を抱きましたか。
松山:素直に嬉しかったですね。実は、生成AIで出力された自分のキャラを見てみたくて、Xでも、誰か出してくれないかなとずっと言っていたんですよ。だから、お話をいただいたときは、契約書を見てすぐにOKを出しました。オフィシャルでやってくれたビーグリーさんには感謝ですね。
大森:1キャラずつ生成していくため、『エイケン』は登場人物が多くて大変な面もありました。アクセサリーなどを身に着けたキャラの生成も難しかったです。なかなかアクセサリーとキャラは同時に出ないので、別々に生成し、合成する必要があったりと、試行錯誤を重ねました。生成AIは特定の構図を狙って出したり、キャラクターデザインに一貫性を持たせることが難しいので、かなり挑戦的な作業といえます。
――制作にあたって、松山先生から具体的な要望は出されたのでしょうか。
松山:敢えて口を出さずにいこうと思いました。というのも、『エイケン』がOVAでアニメ化されたときに口出ししたことがあったのですが、かえって現場をかき乱してしまったんですよ。今回はビーグリーさんを信頼して、お任せしたんです。リメイク版は原作者にとってのアニメのようなもので、あくまでも原作とは別物と捉えています。そのかわり、自分がペンを入れて描く漫画は、とことんこだわろうと思いました。