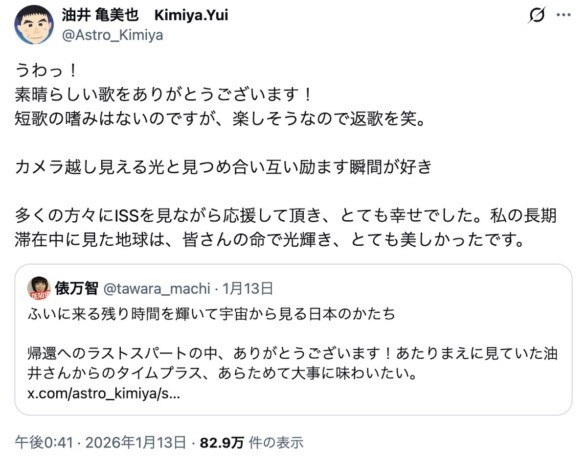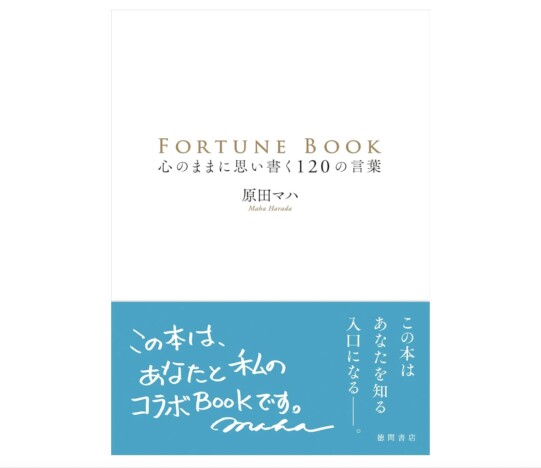木澤佐登志『闇の精神史』から考える、「持続可能」以外の未来像

未来は明るいもの。そう思えなくなったのはいつからだろうか。今や社会をいかに持続させるかが議論されるようになり、人類に劇的な進歩を期待することは難しい。それでもなお、私たちは現実と違う空間――未知の未来像やユートピアを思い描けるのだろうか? そんな問題提起を出発点に、著者で文筆家の木澤佐登志が〈堆積した歴史と記憶と夢の残骸の中から朽ちた〈未来〉の破片をサルベージし、それに一条の光を当てる作業〉を通じて、未知の世界を見つけるヒントを読者に提供する一冊。それが本書『闇の精神史』(木澤佐登志/ハヤカワ新書)である。
とはいえ「未来を絶対見つけ出す」なんて、前のめりになって読まなくても大丈夫。まずは本書で紹介される未来にまつわるイメージや思想の数々を盲信するのではなく、分析したり、比較したり、ツッコんでみたり。どんな形であれ、関心を持って読んでみるのが吉というもの。たとえば宇宙の捉え方も人それぞれで、思考のディテールに個性の現れるのが面白い。
X(旧Twitter)のオーナーでもある実業家のイーロン・マスクにとって、宇宙とは居住区である。マスクは人類がいずれ存亡の危機に瀕するとして、2050年までに100万人を火星に移住させることを目標に掲げる。「モスクワのソクラテス」の異名を持つニコライ・フョードロフもまた、宇宙への移住を考える。彼が19世紀に構想した「ロシア宇宙主義」において、人類は人口が増大し資源の枯渇した地球を離れ、宇宙を開拓することが運命づけられている。
宇宙へ向かう目的はよく似た両者だが、大きく違うのが理想とする世界だ。マスクのヴィジョンの根底には、「長期主義」と呼ばれる倫理観があると指摘されている。彼をはじめとする長期主義者は、自分たちがリーダーとなり「人類絶滅のリスク軽減」を名目に遠い未来の都合を最優先し、今いる人々の人権を制限した監視社会を志向する恐れがあるという。一方、ロシア宇宙主義において、人類は進化の途上にあると信じられている。飛行能力や遠視能力、さらには死者を復活させる技術を身に付けた人類はやがて、神の意志のもと先祖まで全ての人間を蘇らせて不死の世界が完成する。
宇宙に対し移住とはまた異なるアプローチをするのが、アメリカのジャズ作曲家でありバンド・リーダーであり、ピアノ・シンセサイザープレイヤーでもあるサン・ラーだ。彼は自らを土星人であると主張した。リーダーをつとめる「アーケストラ」(エジプトの神ラーの方舟を暗示している)と呼ばれるバンドは演奏中、抑圧と絶望に満ちた地球から脱出し、宇宙という無限の空間へ飛び出して行くと高らかに唱える。アフリカ大陸から奴隷として連れてこられてきた祖先を持ち、自分たちのルーツや故郷を知ることもできない。そんなアフリカ系アメリカ人の現実を寓話として描き、彼らにとっての真の故郷が宇宙であるとサン・ラーは定義する。
個性の異なる3人の宇宙観において、地球にはいられない/いられなくなるとする点で共通しているのが興味深い。イーロン・マスクの思い描くユートピアは真っ平御免だが、1993年に亡くなったサン・ラーがもし今も生きていたら、ネオリベ的な未来の実現にどう抗っただろうかと考えてみたくなる。
本書のタイトルにある「精神史」に目を向けてみると、過去に生まれた未来的なモチーフや思想は紆余曲折を経て再評価されることもあれば、形を変えて現代まで生き続けることもある。その過程にある意外性とドラマ性も読みどころの一つであり、未来について考える際のヒントにもなる。そしてここで主役となるのが、「テクノロジー」だ。