千葉雅也 × 速水健朗が語る、テクノロジーと創作の共進化 「マルチウィンドウは再評価すべき」

千葉雅也の三冊目となる小説『エレクトリック』(新潮社)は、1995年の栃木県宇都宮市を舞台に、高校二年生の主人公・達也が東京へ憧れながら、広告業を営む父と過ごした日々を描いた青春小説だ。黎明期のインターネットをはじめとした当時のメディア環境を細かに描き出しているのも特徴で、2023年7月に『1973年に生まれて 団塊ジュニア世代の半世紀』(東京書籍)を著したライターの速水健朗も大きな感銘を受けたという。
1995年はどのような時代で、地方都市で暮らしていた少年たちは何を夢みていたのか。そして、メディアやテクノロジーの発展は創作にどんな変化をもたらすのか。千葉雅也と速水健朗の対談をお届けする。(編集部)
メディアの変化と新しい時代への期待があった1995年
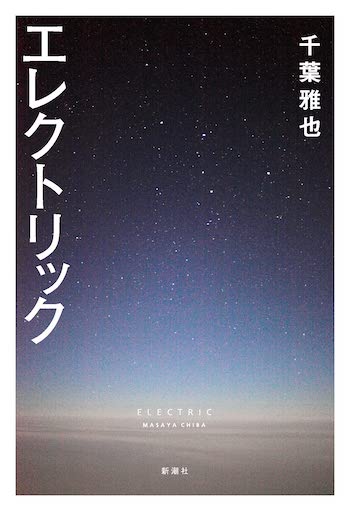
速水:『エレクトリック』は1995年の栃木県宇都宮市を舞台にした小説です。真空管オーディオとCD、ファックスと電子メールといった具合に、メディアの変化の様子をちりばめてますよね。家族の生活の中でも、さまざまな装置のことをつぶさに描写している。特に印象に残るのは、主人公の妹が使っているポラロイドカメラと主人公が使っているPhotoshopですよね。バージョンで言えば、2.0~3.0くらいの頃かなと。高校生の主人公の青春期や家族との関係が、メディアの変遷となぞらえて語られる構造がまず小説としておもしろかった。僕も『1995年』(ちくま新書)という題名の本を書いたことがあって、ワープロからパソコン、パソコン通信からインターネットみたいな変化そのものは少しずつではあるけど、決定的な変化の兆候の年として記憶しています。
千葉:ありがとうございます、速水さんにそう言ってもらえるのはすごく嬉しいです。ご指摘くださったように、僕は時代の刻み目となる細かな変化が気になっていて、例えば「シャウエッセン」はいつ頃発売されたのかとか、バルサミコ酢やモッツァレラチーズが一般化したのは90年代だったな、といった感覚を大事にしています。そういう感覚こそが時代の流動であり、各々の主体性やカルチャーの変化とも繋がっているからです。
1995年をどう経験したかについては、僕と速水さんでは世代差があるわけです。僕はこの小説の主人公と同じく、1995年は高校二年生で17歳でした。僕は『デッドライン』『オーバーヒート』『エレクトリック』を「私小説の脱構築三部作」と呼んでいるのですが、今回の『エレクトリック』は主人公の変化と時代の変化が、もっとも一致している時期を描いた作品になりました。三部作はどれも「その一線を越えるか越えないかのギリギリ」を描いていて、今回は「時間」や「時代」を軸に「その一線」を描いたという感じです。オーディオを象徴的に描いたのは、それが過去の音を再生するという意味でのタイムマシーンでもあるからで、そう考えるとタイムトラベル小説のような側面もあるかもしれません。
速水:「私小説の脱構築」というのはどういう意味でしょうか。

千葉:デビュー作となった『デッドライン』は、まず修士課程の時期のことを書こうという大枠があって書き始めたものでした。過去の経験を素材にしていますが、記憶の断片と虚構の関係それ自体がテーマになっています。どんな小説でも私小説的側面はあるし、物語がどう展開するか、どういう意味を持つかだけでなく、小説はつねに、フィクションとは何かと問いかけている。僕が「私小説の脱構築」と呼んでいるのは、そういう問題意識のことです。
速水:『エレクトリック』を読んでいると、ディティールが細かいから、おそらく実体験やエッセイ的な要素が混ざっているのだろうと思っていると、突然、同じ出来事が、別の意味を持って繰り返されたり、伏線だったことに気がつかされて、物語に引き戻されます。そういう部分は、『エレクトリック』から『オーバーヒート』に引き戻されたり、『デッドライン』で繰り返されたり、複雑に絡み合ってますよね。脱構築はそういう部分を指しているのかなと思いました。
千葉:結果的に、三作にまたがって、いろんな要素が関係のネットワークになっていると思います。『デッドライン』は初めて長い小説を書くチャレンジだったし、それから試行錯誤してきましたが、構造を考えて書いているところと、即興で書き流しているところがハイブリッドになっています。どんどん進行していくシーンを作りたい時は音声入力を下敷きにすることもあり、それを箱書き的な構成に落とし込んだりしています。『デッドライン』の時からそうですが、書くこととツールの関係もいろいろ考えてきました。『デッドライン』は、東京に住んでいた頃にあった井の頭通り添いの「ドンキホーテ杉並店」が「紳士服の青山」になっていたのをGoogleマップのストリートビューで確認して、2000年代初めの記憶が蘇ってきて、アイデアの断片をアウトライン・プロセッサに書き出すところから始めました。それらをスクリブナーというソフトに持っていって構成を試す。スクリブナーは文章をパーツに分けて執筆し、再構成ができる特殊なワープロで、映像編集ソフトや音楽のDAWに似ています。最近は別の方法を試しているところなんですが。
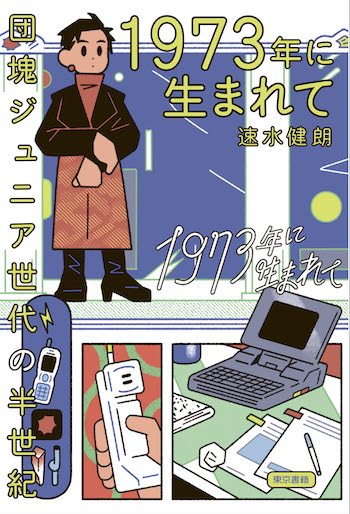
速水:街の描き方も、同じ場所が何度も繰り返し登場し、少し変化を遂げているみたいなところも感じました。小説って物語をたどるんですけど、その物語って、主人公の冒険とかではなく、小さな細部の描写が繰り返され、少しずつ変化していくみたいなものなんだということに気がつきます。それがわかってくると、『エレクトリック』のおもしろさがすんなりと入ってきたように思います。僕の友だちで小説家でもある古市憲寿くんと最近しゃべったんですけど、僕の『1973年に生まれて 団塊ジュニア世代の半世紀』を読んだ感想で、「細かな生活の中のテクノロジーの変化を描きたいのであれば、むしろ小説が向いている」って言ってたんですよ。確かに、ノンフィクションは、社会の大きな変化を書くのに向く。小説は、細部までそれを書くことに向くメディアだなと思いました。
千葉:僕には、小さなものと結びついた身体感覚が、大きな悩みや世界の動きと連動していくという世界観があるんだと思います。ミクロとマクロの呼応というか、微細なところに世界のすべての兆候が凝縮されているようなイメージ。例えばタバコで言うと、マルボロライトメンソールについて語ると、2000年前後の若者文化が立ち上がってくる。
速水:タバコの銘柄はそれだけで文学が立ち上がってきますね。学生運動の時代の小説には必ず両切のピースの話が出てくるなって思ってました。僕が知っている時代ではハイライトっておじさんタバコの印象だったんだけど、1960年代は若者が吸うブランドだったとか、小説を読んでいると、自分の生まれる前のことが入ってくる。ただ、タバコと小説の距離もできてしまったのか、今どきのブランドだと、どういう位置づけの銘柄なのかわからなくなってます。例えば、アメリカンスピリッツはよく見るけど、あれはワイルドなのか、自然派なのかどっちかよくわかってない。
千葉:アメスピはちょっとおしゃれな人が吸いますよね。燃焼剤が入っていなくてオーガニック系。だから燃えるのが遅くて、なんとなく持続可能性を感じるというか。ネイティブアメリカンのイメージも相まって、反植民地主義的な抵抗としての不良感を演出できるんじゃないでしょうか。



















