千葉雅也 × 速水健朗が語る、テクノロジーと創作の共進化 「マルチウィンドウは再評価すべき」

東京と地方都市の距離感
速水:小説の舞台となっている宇都宮は首都圏にも近いし、東京に行こうと思えば行ける距離です。僕は中高生の頃を新潟で過ごしたんですけど、僕が新潟に越してくる少し前にまでは新幹線が上野駅に延伸されて、時間も短縮されて1時間39分になった。首都との距離みたいなことは、かつては分単位で意識されていたというか、多分僕は意識してた高校生だったんですね。
千葉:宇都宮は新幹線で50分くらいで東京に行けるので、まあまあ近いですね。北関東の都市は東京の流行を真似るようなところがあって、宇都宮も80年代は丸井や西武があって、渋谷セゾン的な雰囲気がちょっとありました。うちの両親は学生時代を東京で過ごしていて、地元に戻ってからも、おしゃれな雑貨や家具はわざわざ表参道とかに買いに行ったそうです。僕が生まれたときの揺りかごも東京まで買いに行ったと聞きました。
中高生の頃、オリオン通りというアーケードにある新星堂でCDを買っていたんですが、そこでECMの現代音楽シリーズに出会ったりと、それなりにマニアックなジャンルも置いてありました。かつてはオリオン通りにはアムスという西武系のデパートがあって、その後、アムスは宇都宮109というファッションビルになり、今では建物がなくなってオリオンスクエアというイベントスペースになっています。そのアムスの地下にあったリブロでは、ジョルジュ・バタイユの翻訳とかティモシー・リアリーの『大気圏外進化論』なんかに出会いました。宇都宮はそういう距離感でした。
速水:なるほど。僕もたまに東京に行ってたんですけど、深夜の高速バスが西武のバスで、4、5時間かかった、朝の4時に池袋のサンシャインに到着するんです。ちょうど高校時代がバブルの頃と重なっているので、80年代のセゾンカルチャーはかすっている。池袋のリブロに最初に行ったのは、大学受験のときです。突然、棚の並びに驚いて連日通ってしまったんです。これ親にも秘密なんですけど、実は池袋の会場で受けるはずの受験をさぼって本屋に入り浸ってました。
千葉:僕の場合、東京から色々と届きはするものの、簡単には行けないところで、高校を卒業したら東京で一人暮らしをするんだという希望を抱いていました。両親も高校卒業後に東京へ行ったわけで、それが我が家の通過儀礼だった。『エレクトリック』では、メディア環境が大きく変化しつつある時期に、性的な自覚も芽生えて、いよいよ冒険が始まるんだという前夜を描いています。それはちょっと『魔女の宅急便』みたいなイメージですね。
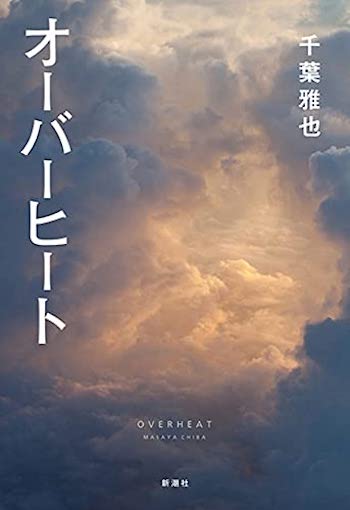
速水:時系列的には、『エレクトリック』で宇都宮での青春時代を描いて、その後に『デッドライン』で東京に行き、『オーバーヒート』で大阪に行っている。千葉さんの小説は都市論でもある。どうやって住む場所を決めるか、住む用の街と住むようではない街の手触りみたいな話とか、行きつけのバーをきっかけに街になじむ話なんかは都市論としておもしろい。あと小説の中にラーメン店の話が多いのもいいです。ちなみに、僕がラーメンについて書いたTwitterに千葉さんからのいいねが付く気がする(笑)。僕は『ラーメンと愛国』(現代新書)という本を書いたことがありますけど。
千葉:小説の中で細かに描いていることって、時代の風俗を描くためのうんちく程度に思っている人が多いけれど、実はもっと深く人のあり方に関わっているんですよね。実際、速水さんはラーメンというものから時代精神や日本人のトラウマを炙り出しているわけで。
速水:『エレクトリック』では、オートマ限定の免許とマニュアル車を運転することの意味の話も出てくる。ギアをセカンドからサードに入れる方法を細かに説明することで、人間が主体的に機械を制御することの意味を語っている。僕と同世代からオートマ限定の免許制度がスタートしていて、マニュアル車に乗るのは、マニアだけっていう時代ですけど僕はマニュアル派です。
千葉:すべてが自動制御になり、最終的に映画『マトリックス』のように人間がただただ快感のスープに浸かっているような時代になることに対する抵抗が、僕にはすごくあります。昔のマッキントッシュはすぐに調子が悪くなったりもしたけれど、そこで何度も再起動したりとか、面倒な関わりをすることの中に人間的な自由もあると思うんです。これまでもずっとそういうことを描いてきたし、これから先もずっと描いていくと思います。





















