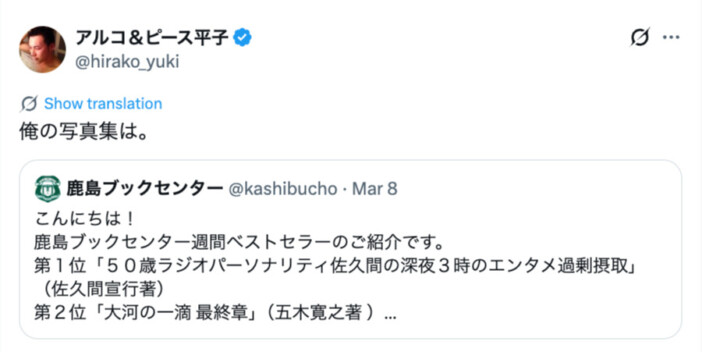「国書刊行会」50周年記念小冊子は一般的な社史にあらず 読書好き必見の面白すぎる内容

ちょっと目が肥えた本好きなら誰しも、「国書刊行会」という出版社にある種の尊敬の念を抱いていることだろう。
創業は、1971年。初期の頃は仏教、神道、郷土史などの本をおもに刊行していたようだが、紀田順一郎と荒俣宏の持ち込み企画として始まった『世界幻想文学大系』(1975〜1986年/全45巻)を皮切りに、内外の幻想文学の版元として広く知られるようになった(その他にも、いまでは、SF、ミステリ、ホラー、オカルト、歴史、宗教、映画、美術、コミックなど、幅広いジャンルの本を手掛けている)。
具体的なタイトル(シリーズ名)を挙げれば、『ラテンアメリカ文学叢書』(全15巻)、『ゴシック叢書』(全34巻)、『セリーヌの作品』(全15巻)、『定本 ラヴクラフト全集』(全10巻)、『バベルの図書館』(全30巻)、『日本幻想文学集成』(全33巻)、『山尾悠子作品集成』など、その多くは函入り・箔押しによる凝った造本であり、いずれも書店の一角で妖しげな光を放っている。
その国書刊行会が創業50周年を迎え、昨年の11月と今年の3月に記念の小冊子が作られたのだが、これがなんというか、いずれも無料の販促物とはとても思えない、装幀・内容ともに非常に手が込んだ見事な“書物”である(厳密にいえば、同社の創業50 周年は2021年なのだが、コロナ禍の影響で記念フェアを行うのが少しずれたようだ)。
特殊な版元の成り立ちを描いたドキュメンタリー
今回、「国書刊行会創業50周年記念小冊子」として作られたのは、『私が選ぶ国書刊行会の3冊』と、『国書刊行会50年の歩み』の2冊(前者については、創業40周年の際にも、同様のテーマの小冊子が作られている)。
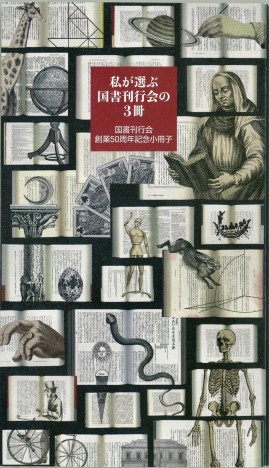
いずれも2023年4月現在、同社の「創業50周年記念フェア」に協力している書店を中心に無料頒布されているものだが(協力店については公式サイトなどで確認されたい)、本稿では後者――『国書刊行会50年の歩み』を紹介したいと思う。
『国書刊行会50年の歩み』は、書名からもわかるように、いわゆる「社史」である。通常、社史というものは部外者が読んでもさほど面白いものではないはずだが、これがある種のドキュメンタリーとして(あるいはちょっと風変わりなサクセスストーリーとして)、すこぶる面白いのだ。
メインコンテンツは、元編集長・礒崎純一(澁澤龍彥、山尾悠子などの書籍を担当)へのインタビュー、同社のミステリ路線を開拓した藤原義也(藤原編集室)によるコラム、特殊翻訳家・柳下毅一郎と特殊編集者・樽本周馬の対談、50 年の間に起きたさまざまな“こぼれ話”を断片的に描いた「国書刊行会社史余滴」(竹中朗)、そして、社員9名による座談会であり、いずれも濃い内容だが、個人的には「国書刊行会社史余滴」をたいへん興味深く読んだ。
本文の一部が赤い紙で「封印」されている魔術書をめぐる騒動(?)「『法の書』事件」や、営業部長が「上田アキナリ先生」の連絡先の問い合わせに対応しようとした「秋成事件」(念のため書いておくが、上田秋成は江戸時代の人物である)、「八重洲ブックセンター事件」、「荒廃する営業部員」、「ゲタ事件」など、各「事件」の当事者たちはともかく、本好きなら思わず吹き出してしまうような笑えるエピソードが満載だ(さらには実話怪談めいたちょっとコワい話まで収録されているのだが……詳しくはまあ、同冊子を読まれたい)。
「国書刊行会らしさ」とは何か
それにしても、この小冊子を通読して印象に残るのは、複数の関係者たちが語っている「国書刊行会らしさ」についてではないだろうか。
たしかに、多くの読書家が思い描いている「国書刊行会らしさ」というものはある。だが、それはぼんやりとしたイメージに過ぎず、はっきりとした言葉で表わすのは難しい、ともいえる。むろん、同社が「内外の幻想文学に強い版元」であることに間違いはないだろう。しかし、先にも述べたように、仏教関係の本からオカルト書まで、あるいは、芸術書からコミックまで、国書刊行会からはいまも昔も幅広いジャンルの本が刊行されているわけであり、そうした1冊1冊が「国書刊行会らしさ」を形づくっているのだ。
逆にいえば、それは、1人1人の編集者の「個性」が集まってできた「らしさ」だともいえるだろう(だから、実際は、編集者が入れ替わるたびに少しずつ刊行物のジャンルやカラーも変わっているはずなのだ)。
では、明確な「国書刊行会らしさ」というものはないのかといえば、もちろんそんなことはなく、たとえば、今回作られたもう一方の小冊子、『私が選ぶ国書刊行会の3冊』の中で、書評家の朝宮運河がこんなことを書いている。
もちろん国書はジャンルの中心にある重要作も刊行している。しかしそれと同じくらい、どこかはみ出した作品、名付けようのない作品も出している。
朝宮のこの文章は、おもに小説について述べたものだが、国書刊行会が刊行している全てのジャンルの本についてもいえることではないだろうか。そう、この、「どこかはみ出した作品、名付けようのない作品」――それこそが、いかなるジャンルの本であったとしても、「国書刊行会らしさ」を持った書物なのだと私は思う。
もともと「畸人(奇人)」の「畸」という字は、地勢の関係で正方になれない田の余った部分を指していたそうだが、そうした「はみ出した」ものや「名付けようのない」もの――すなわち、“逸脱したもの”こそが、退屈な日常に刺激を与えてくれるのは間違いない。嘘だと思うなら、試しに想像してみるといい。国書刊行会のない日本の出版界ほど、つまらないものはないだろうから。