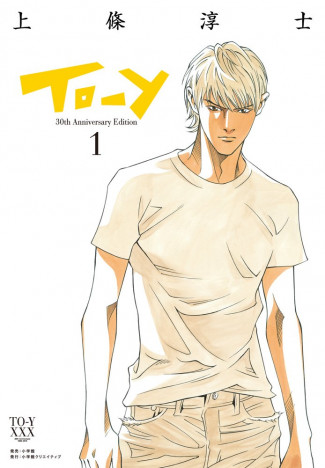元祖ロック漫画『ファイヤー!』著者・水野英子インタビュー「時代が変わろうとしているのを実感した」

水野英子の『ファイヤー!』は、「日本初の本格的なロック漫画」といわれている作品だ(「週刊セブンティーン」1969年1号〜1971年28号連載作)。
【写真】 “元祖・ロック漫画”と言われる『ファイヤー!』の中面を見る
主人公は、純粋な心を持っているがゆえに破滅に向かうしかなかったボーカリストのアロン。そんな彼の熱い歌声と、自由を掴みとるための壮絶な闘いを描いた同作は、技法的にも、内容的にも、のちのロック漫画の“型”の1つを作ったといっていいだろう(じっさい、『DESPERAD』、『BECK』から『ウッドストック』、『ぼっち・ざ・ろっく!』にいたるまで、『ファイヤー!』の後続作品の多くが、ナイーブな少年ないし少女がロックと出合って自分を解き放つ、というものである)。
さて、その伝説的な作品が、先ごろ全2巻の単行本として、文藝春秋より復刻された。そこで今回のインタビューでは、作者である水野氏に、執筆当時の思い出や、漫画で“音”を表現するテクニック、そして、作品の根底にあるラブ&ピースの精神についてうかがった。(島田一志)
漫画でラブ&ピースを表現する


――まずは、『ファイヤー!』が、「日本初のロック漫画」といわれていることについてですが、たとえば同作以前にも、宮谷一彦先生が「セブンティーン」(1968年)という作品の中で、エレキギターを大音量でかき鳴らす少年の姿を描いていたりはします。調べれば他にもあるかもしれません。ただし、“ロックの音と精神を真正面から描いた大作”という意味では、やはり『ファイヤー!』が「元祖」といっていいかと思います。
水野 そうですね。私も厳密に調べたわけではありませんが、当時、ロックそのものをテーマにした長編漫画は他になかったように記憶しています。だからこそ描かなければと思いました。
――水野先生のロックとの出会いを教えてください。
水野 もともとはクラシックが好きだったんですよ。小学生の頃は、ラジオでよく「音楽の泉」という番組を聴いていました。堀内敬三さんの解説もよかったですね。やがてFM放送が始まってからは、長い音楽も聴けるようになり、それまでは断片的にしか知らなかったオペラの凄さを知りました。オペラは漫画を描くうえでもかなり影響を受けています。
自分でレコードを買うようになったのは、上京後のことでした。トキワ荘(注・水野氏は「トキワ荘の紅一点」としても知られている)にいた石ノ森章太郎さんがレコードをたくさん持っていて、刺激されました。同じ頃、映画もたくさん観るようになり、映画音楽も聴くようになりました。とにかく若い頃はいい音楽ならなんだって貪欲に吸収していましたし、音楽なしの生活は考えられませんでした。
ロックについては、最初にビートルズが出てきた時、リズムは強烈でおもしろいと感じましたが、クラシックを聴き慣れていた人間としては少々物足りなくもありました。全体的に曲が単純な気がしたんですね。でもいま思えば、彼らの歌には強いメッセージがありました。
私が惹かれたのは、どちらかといえば、ビートルズ以降のプログレやハードロック系のバンドで。当時はそれらの音楽と連動する形で、若者たちの反体制の活動も盛り上がっていました。ベトナム戦争の泥沼化に多くの人たちが憤っていましたし、黒人をはじめとした有色人種の主張も重なり、もの凄いパワーを生み出していた。そうしたアメリカの動向がずっと気になっていて、目が離せなかったんですよ。暴力的な革命を目指すのではなく、ラブ&ピースの力で世の中を変えようという動きですね。日本にいながら、これは私の考えていることと同じだと強く感じたのを覚えています。
――漫画で“音”を描くことや、いまおっしゃられたようなさまざまな社会問題をエンターテインメント作品に落とし込むことの難しさは感じませんでしたか?

水野 それはまったく感じませんでした。むしろ伝えたいメッセージが次々と自分の中で溢れ出してきていたのです。もちろん紙の上でじっさいに音を出すことはできません。ある意味ではそこが一番苦労したところだったともいえますが、逆に助かった部分でもありました。というのは、「凄い曲」をじっさいに作って演奏するのは至難の業ですが、漫画で読者に想像してもらうぶんには自由ですからね(笑)。
取材旅行で目にした海外の光景と主人公・アロンのモデル
――それまで前例のなかった「ロックをテーマにした漫画」について、当初、掲載誌である「週刊セブンティーン」の編集部はすんなりと受け入れてくれましたか?
水野 ピンク・フロイドやレッド・ツェッペリンみたいなバンドの話を描きたい、といっても企画が通らないのはわかっていましたから、当時日本で流行っていた「GS(グループ・サウンズ)の漫画を描きたい」と編集さんにいってみたんですよ。そうしたら、「ああ、それはいいですね!」とほとんど即答で連載が決まりました(笑)。
――「グループがサウンドを奏でる物語」だから、大きな意味では間違ってはいない(笑)。
水野 そうですね(笑)。でも、アロンが感化院を出るあたりまでは、編集部も読者も、この物語がどこに向かっていくのか、ほとんど理解できていなかったと思います。
――ちなみに、連載前に海外へ長期の取材旅行に行かれたそうですね。
水野 はい。当時、FEN放送をかけっぱなしで仕事をしていたのですが、やはり向こうのバンドの音は日本のそれとは全然違うわけですよ。これは本場に行かないことには何も始まらないなと思いました。
訪れたのはアメリカとヨーロッパのいくつかの都市でしたが、ライブハウスの空気を肌で感じられたのは貴重な経験でした。中には女性シンガーも何人かいて、彼女たちは本当にかっこよかったですよ。他にも日本にいたら絶対に見られないようなものをたくさん見てきました。当時のロンドンのカーナビー・ストリートやキングス・ロードの風景は、いまでも目に焼き付いています。アメリカでも広場に花を持ったヒッピーたちがたむろしていたりして、時代が変わろうとしているのを実感しました。
――連載が始まってからの読者の反応はどうでしたか?
水野 それはもう凄いものがありました。自分でも驚くくらいに。ただ、それまで私が描いていたロマンチック路線の漫画とは作風ががらっと変わってしまったものですから、昔からのファンの方たちはちょっと戸惑ったみたいですね。女性向けの漫画で男性が主人公、というのも受け入れ難かったみたいで。
――主人公のアロンには、ウォーカー・ブラザーズのスコット・ウォーカーのイメージが投影されているそうですね。ウォーカー・ブラザーズというのは、水野先生がお好きなプログレやハードロックというよりは、どちらかといえばメロディー重視のおとなしめなバンドの印象があるのですが。
水野 それが逆に新鮮だったんですよ。ジミヘンのような爆音のロックが全盛の時代に、あえてビートよりも美しい旋律を重視したバンド、というのが面白いと思いました。
ウォーカー・ブラザーズは、曲がいいのはもちろんですが、ボーカルのスコット・ウォーカーという人物の内面にも惹かれました。甘いマスクで、甘い歌を歌っていた人ですけど、彼自身は女の子にキャーキャーいわれるのが嫌だったみたいですね。純粋に、ただ歌を歌いたかっただけの人なんです。どんなに曲がヒットしても、お金を得ても、それがシンガーとしての到達点ではないのだという。汚れたくても汚れない人間、とでもいうのでしょうか。そんな彼の悩みがなぜか手にとるようにわかってきて、そのうちに私の中でアロンというキャラクターが形づくられていきました。