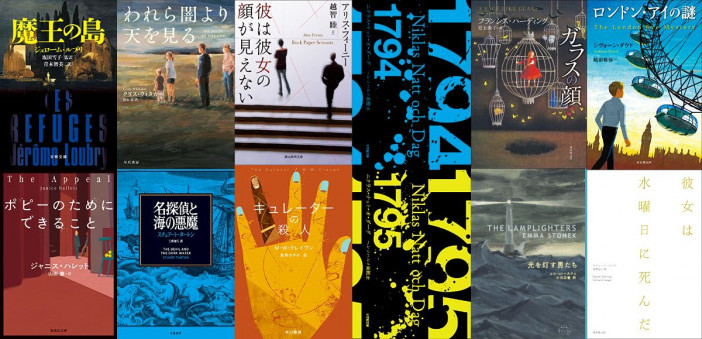高知東生のデビュー作『土竜』は芸能人の余芸にあらず “小説家の小説”たらしめた創意工夫
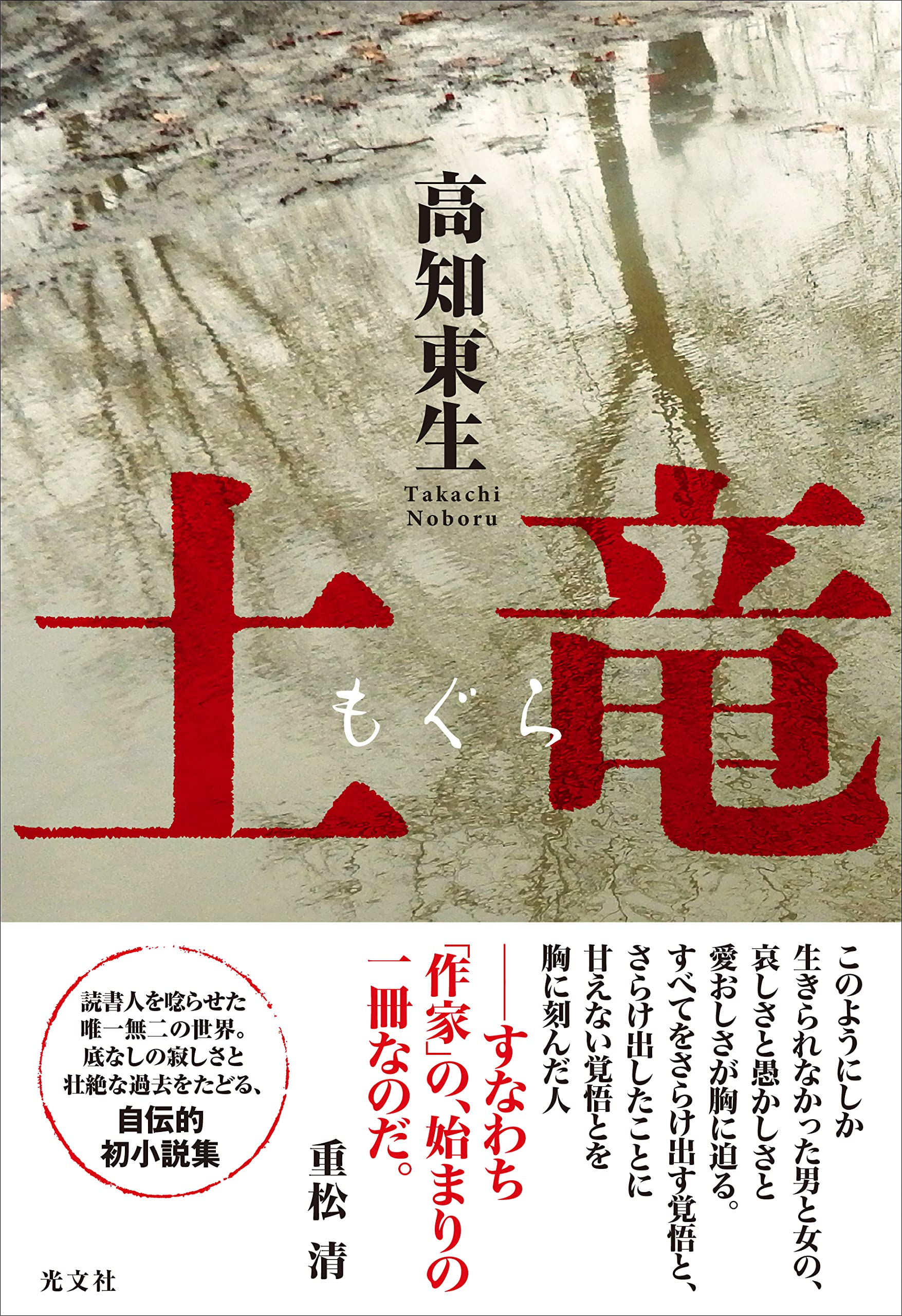
高知東生の小説家デビュー作『土竜(もぐら)』(光文社)がべらぼうにおもしろい。
そのことを一人でも多くの読者に知ってもらいたい。いいのである。きちんと小説家の文章で書かれた作品だ。
六篇が収められた連作短篇集で、中心にいるのは大崎竜二という男だ。高知県生まれで、しばらく腰の据わらない暮らしをしていたが、一旗揚げるために上京し、俳優となって坂本竜生を名乗る。坂本は土佐の英雄・坂本竜馬から採った芸名だろう。坂本竜生と高知東生、見比べてみればこれが作者自身のことであるのは明白だ。つまり半自伝的な小説で、巻頭の「アロエの葉」は竜生の上の世代の物語である。祖母のあてと、竜生の母である妙子が主役を務める。
その他の収録作については後で触れる。とりあえず言いたいのは、四番目に収録されている「昼咲月見草」がいいということなのだ。本書の収録作はすべて草花の名が題に使われている。昼に咲く月見草とは誰だ、ということはちょっと措いておく。
本篇の主人公は三十歳の高橋という男である。他の短篇にも出てくる人物で、竜二の同級生にあたる。高橋の家は教師の家系で、特に祖父は厳格な人物だった。きょうだいは家の雰囲気を嫌ってみんな東京に出てしまった。逃げ遅れた高橋は空気を読んで教師になる。しかし適性はまったくなく、厭な仕事を続けていくストレスから高橋はパチンコ依存症になり、百万円もの借金をこしらえてしまうのだ。
そんなある日、高橋の前に地元では有名な不良の先輩である東野が現れる。パチンコ屋ですっからかんにされた高橋に彼がかけた、こんな言葉から「昼咲月見草」は始まるのだ。
「おう、高橋。ええとこで会うたでよぉ。おまえのチン毛くれや」
なんという完璧な掴みの台詞であろうか。
あまりのことに高橋は固まる。当たり前で、そんなことを往来でいきなり言われたら私だって固まる。
東野がそんなものを欲しがるのには理由があった。彼は仲間と一緒に通信販売のブルセラショップを始めていたのである。今となっては説明が必要かもしれないが、これは一世を風靡した風俗産業で、未成年女性が身に付けたものなどを、そういうものに興奮する男性に売りつける商売である。ブルマーとセーラー服でブルセラだ。警察もそんな商売が出現するとは思っていなかったらしく対応に苦慮し、結局は古物商の鑑札なしに中古品の買取を行った、という理由で取り締まりを行った。そのブルセラだ。
高橋の毛が必要なのは、未成年女子のものと偽って販売するためなのであった。東野先輩は周囲の者からそれを刈り集めていたが、さすがにみんな禿山になってしまったので、新しい林を必要としていた。そのお眼鏡に叶ったわけである。
馬鹿馬鹿しいと思いつつもパチンコの借金がある高橋は断れない。しぶしぶ仲間に入って東野先輩の手伝いをするうちに、彼は意外な才能を発揮するようになる。新しい商売の種を考えるのが上手かったのだ。たとえば、顧客の中には若い女性が耳かきをする場面に興奮する者がいた。高橋は自分の同級生を連れてきてビデオを録る。三十歳だが顔は映さなければいいのである。こうして東野先輩の商売は右肩上がりになっていく。
傍目で見ればろくでもないことをしているのだが、お祭り感がある。この盛り上がりが楽しくなってしまうような筆致で書かれている。そのさなか、高橋はどん底に沈んでいく。パチンコの借金でいよいよ首が回らなくなり、自己嫌悪が極限に達したのだ。やっていることはろくでもないブルセラ稼業だ。お祭りのてっぺんを描いた直後にこの高橋の失意が描かれるのが上手い。やけになった高橋は自ら破滅への扉を開こうとする。
卑小な犯罪を描いた実にいい短篇である。これが本書の白眉だと思う。「昼咲月見草」の前に置かれているのは、最初に上げた「アロエの葉」と、竜二の高知時代を描いた「シクラメン」「喧嘩草」の二篇だ。「シクラメン」は竜二の同級生だった夕子という少女の物語である。夕子の母親はいわゆる風俗産業で働いていて、そのために周囲からひどい差別を受けていた。現在ではなく昭和の話だから、人権意識などもより希薄だったのである。その夕子と竜二の間に産まれた交流が描かれる。「喧嘩草」のほうは竜二とコンビを組んで喧嘩やナンパに精を出すことになる半沢が視点人物で、いわゆるヤンキーものだ。乗り回す車がセリカにソアラ、ナンパの舞台が大箱のディスコというのが昭和末期の世情をよく表している。
本書の収録作はすべて『小説宝石』が初出なのだが、最初に掲載されたのが「シクラメン」」だった。以降の掲載作もおもしろく読んだのだが、無数に読んできたいわゆる不良小説の域を出ないというのが最初の印象で、いい書き手ではあるけど、と思いつつ感想をメモしておくだけで特に気には留めなかった。こうして単行本化されてから改めて読むと、きちんと人情噺のツボを押さえた書きぶりであり、物語を小説として綴ろうという作者の創意工夫が随所にあることに気づかされる。「シクラメン」の、題名の意味が最後にわかる幕切れなどは、よくある手ではあるがそれでも感心した。
ここまでの四篇が過去篇で、残る「リラ」「梔子(くちなし)」の二篇は現在篇になる。「リラ」は現在の竜二、つまり坂本竜生が中田という女性のプロデューサーにインタビューされる場面で始まる。インタビューされている竜二は不機嫌だ。隠遁生活中なのである。「人気女優を妻に持ち、格下婚と世間で言われながらも、バイプレイヤーとしてそこそこ売れていた俺は、愛人と一緒にシャブを使っていたところを踏み込まれ逮捕された」からであり、他人の視線が気になって街にも出られないありさまなのだ。その竜二が自分の故郷である高知に帰り、自分の知らなかった母・妙子像に触れることで新たな心境を開いていく。