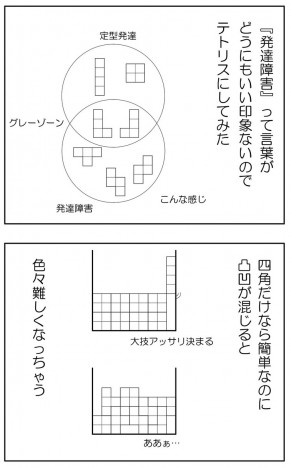ニットデザイナー三國万里子が語る、編むことと書くこと「人間はきっと、自分の思いを外に放つべく作られた動物」

人気ニットデザイナーの三國万里子氏が、初のエッセイ集『編めば編むほどわたしはわたしになっていった』(新潮社)を出版した。人とのコミュニケーションが苦手だった10代の頃、父や母、息子といった家族との記憶、腕時計やぬいぐるみなど人の手が生み出したもののこと、編みもの作家として世界に居場所を見つけるまで……そんなさまざまなできごとが大切に、丁寧に綴られている。エッセイ集を書いたきっかけや、書くことと編むことの関係性、さらに「読むこと」についてもうかがった。(小沼理)
編むことも書くことも旅のよう

三國:編むことをずっと続けてきた私が書く時、その編む仕事の影響を受けないわけにはいかないんだなと思いました。編み物って、すべての編み目を方眼で表せるんですよ。最後まできっちりと編み図を書いてから編む方もいらっしゃるんだけど、私は自分の手の中でできあがっていくのを見ながら、こんな感じかな? とじわじわ作っていって、最後に編み図に起こすやり方です。
毛糸が行ったり来たりしながら上に伸びていくのは、山登りみたいでもあります。だから編んでいると、朝から同じ場所に座っていても、一日書いているうちに旅をしたような感慨を持つことがあって。書くことも同じように、夕方になると自分が違う場所に連れてこられた感覚になるのが似ているなと思います。
編み物の経験からなのか、一編一編が工芸的なパッケージに納まる感覚もあります。ものとして触っているうちに形ができていくと言うのかな。書きながら「自分はこう思ってたんだ」とわかっていくんです。
――エッセイでは書くことを"「解放」のようなことでした"と表現していました。
三國:人間ってきっと、自分の思いを外に放つべく作られた動物だと思っているんです。編み物の仕事ってムッと口を結んだまま一か所に座って、お昼ご飯の時以外は口を開けないんですね。編み物にも思いを消化する力はあるんだけど、それだけでは足りない。書くことは、そんな編むだけでは消化できない何かを言葉にして取り出すことでした。

よく言っているのですが、編み物はどんな作品を作っても人を傷つけることはまずありません。それはいいことなのかもしれないけど、自分が表現をする上で、それだけでは苦しく感じることがありました。文章を書きはじめて、その自由度にすごく驚きました。言葉を連ねるだけで、こういうものが表現できるんだ、という。そして、今どきの言葉で「刺さる」っていうんですか、それがちゃんと手ごたえとして分かる。傷つける可能性すらあって、便利で鋭い。だからこそ、大事に、丁寧につくらないといけないものとして言葉を扱おうと思いました。
手に取る人を想像しながら
――このエッセイは友人とのメールのやりとりから生まれたとうかがいました。
三國:「ほぼ日」というウェブ媒体で文章の責任者を務めている永田泰大さんという方がいて、たまにご飯に行く友達なんです。もともと「ほぼ日」で私がちょこちょこ書いていたのを読んでくれていたみたいで、ある時、「なんか書いてみない?」と言ってくれて。永田さんが言うなら、と気軽に引き受けました。褒め上手の永田さんに面白がってもらいたい、次はもっと褒められたいと思いながら書いたので(笑)、ちょっと手紙のようでもありますね。
――読む人のことを想像した文章になっていたんですね。
三國:永田さんともう一人、(「ほぼ日」の)山川路子さんという方にもCCで送っていました。彼女も私の仕事仲間なんですけど、潜在的な読者として一番ぴったりの人だったかもしれない。本を買ってくれる人がいるとしたら、きっと子育て世代で、恋バナが好きな彼女みたいな人なんだろうと思っていました。
――編み物の作品を作るときも、手に取る人のことを想像していますか?
三國:すごく意識しています。自己表現として作る方もいますけど、私は実用的なものを、役に立ってほしいという気持ちで作る方がやりやすい。人と関わることがずっと得意ではなかったぶん、人の役に立てることがすごくうれしいんですよね。
――10代の頃にコミュニケーションが苦手だったことは、エッセイでも繰り返し書いていましたね。
三國:多くの人がナチュラルにできることができなくて。一対一で話すのは大丈夫なんですけど、人の輪の中で会話をまわしていくようなことがとても苦手なんです。学校の休み時間、誰かの輪の中に入って何気なくいる時間がすごく苦痛でした。大人になっても変わらなくて、人と関わるなら私なりのやり方を見つけないと難しいと感じていましたね。
それがようやくできたのが、編み物を売るという経済活動を介してでした。「わあ、いいですね、買えてよかったです」。そう言ってもらえることが、天にものぼるくらいうれしかったです。
――「編みもの作家」というエッセイで、作品をはじめて売った時のことが鮮やかに綴られていました。
三國:妹が働いていた代々木上原の自然食レストランで、レジ前に置かせてもらったのが最初でした。誰かが手に取るところを私は見ていないんです。エッセイには「都合がつかなかった」って書いた気がするんですけど、本当は怖かったの。ドキドキして、買っていく人の姿を見れないと思ったんです。なので妹が、電話で「こういう人が買ってくれたよ」と報告してくれたのがとてもうれしかったですね。私にとって、世界とつながる手助けをしてくれた最初のひとりが妹です。