「銀英伝」にも通ずる大国滅亡の物語 田中芳樹が描く中国史小説の魅力
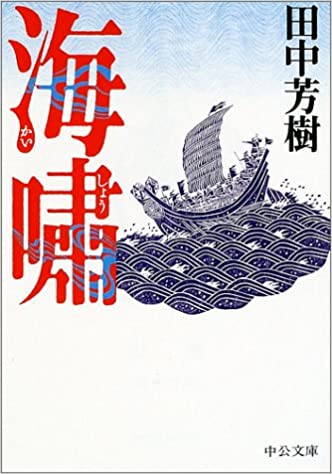
国家存亡の危機の南宋で強烈な光を放つ傑物たち
後世から見て最も有名なのは、文天祥(ぶんてんしょう)だろう。とにかく、清廉潔白。秀才にして、曲がったことは大嫌い。潔癖なほどのまっすぐさが、物語を引っぱる。
次に挙げたいのは、やっぱり張世傑(ちょうせいけつ)。たたき上げの軍人で、ひとことでいえば不撓不屈の闘将だ。
そして、陸秀夫(りくしゅうふ)。秀才の文官であるが気骨があり、何がなんでも宋という国を保とうとした。
この3名を歴史上は「亡宋の三傑」という。国が亡ぶときに、強烈な光を放った3名として称賛されているのだ。
そして、もうひとりの主要キャストがいる。ギリギリ健在だったころの南宋の宰相だった陳宜中(ちんぎちゅう)だ。ただし、彼は前記の三傑ほどの潔さはない。くよくよ悩み、逃亡もする。
さて、中国史には「士大夫」という概念がたびたび登場する。要するにある種の特権階級を指すのだが、宋の時代にはこの概念がかなり顕著だ。
まず、彼らは学識豊かでなければならない。それで、科挙という超難関試験を突破し、官僚となるのだ。詩文など文化にも通じ、正しく、立派に生きることを旨としている。なんとなく、西洋でいう、「ノブレス・オブリージュ」に近い感じだ。高貴に生きるのだから、義務がある、という特権階級の自己弁護ともとれる。
でも、だからこそ、国難に当たって、士大夫は死なねばならない。どまっすぐに実行したのは、士大夫の権化のような文天祥だ。
彼はまっさきに元軍にとっ捕まる。バヤンは立派な彼に元へ降伏しろと諭す。すると、文天祥の強烈な舌鋒。
「三つの条件が整ったら降伏してやる。ひとつ、水中で火が燃えること。ふたつ、長江の水が東から西へ流れること。みっつ、太陽が西から昇って東にしずむこと」
そんなもん、整うはずがない。でも、バヤンは怒るよりも感銘してしまう。ここまで、南宋の人は、どいつもこいつも元軍を前に逃げたり、裏切ったりばかり。なのに、文天祥はこれなのだ。バヤンの話を聞いて、フビライも文天祥が好きになる。
「殺すな!」
フビライは命じる。文天祥は死にたいのに死ねない。
文天祥だけでなく、南宋の人たちはあちこちでがんばっていた。でも、この朝廷は元への降伏を決める。首都の杭州臨安府は開城したのだ。
だが、王朝の幼い血統は逃げていた。張世傑がこれを擁護して、元の追撃を振り切る。陸秀夫は、何がなんでも王朝の形をつくる。大冒険して元の捕縛から逃げてきた文天祥もやってくる。元軍を前にヘタレて逃げていた陳宜中もひっそりと帰ってくる。
なんというか、人材がそろってきた。なんとかなるような気がしてくる。
でも、そうならない。立派な人は複数いるのに、逆転の一歩を踏み出せない。それが、現実なのだ。歴史を扱っている以上、そのまま、話は進む。
こういう部分が、田中芳樹の描く長編にも生かされていると感じる。「銀英伝」のヤン・ウェンリー提督は、あれほどの戦上手であるのに、自由惑星同盟はまとまらない。だから、ヤン提督は苦労する。それが物語のおもしろさとやるせなさを生んでいく。
『海嘯』という物語の帰趨とは関係なく、結論として宋は滅亡する。ネタバレでもなんでもない。歴史の年表を見れば、宋の後は、元なのだ。そういうことになる。
ただの敗者の物語にも見える。でも、それだけではない読後感がある。そのヒントが、史上に文天祥が残した「正気(せいき)の歌」という詩に見え隠れする。せっかくだから、少しだけ触れておこう。
ざっくりいえば、「この世の中には正気という正しい精神があるんだよ」「それはいろんな形でこの世の中に現出してるんだよ」という論法でこの詩は進む。
そしてそれは、あるときは漢の三傑である張良が始皇帝を暗殺しようとした行動になったり、諸葛孔明の書いた「出師の表」という名文になったりしている。そんな調子で文天祥は歴史の中で、まっすぐで正しいことを列挙する。
「私は上手にできなかったけど、ちゃんと歴史は評価してくれるよ」
そんな彼の心情を感じる。そして、文天祥の生き方とこの詩は多くの人に感銘を与え、時間と海を越え、日本の幕末の志士らにも愛されたという。
登場人物たちは時代の大波に抗うことはできなかったが、滅びる国の敗者というレッテルだけに収まらなかった。現実を逆転するカタルシスはそこにないが、何かは確実に逆転したのだ。
それが「銀英伝」などにも通じる、時空を越えて人物を描く、歴史ものならではのおもしろさなのだろう。























