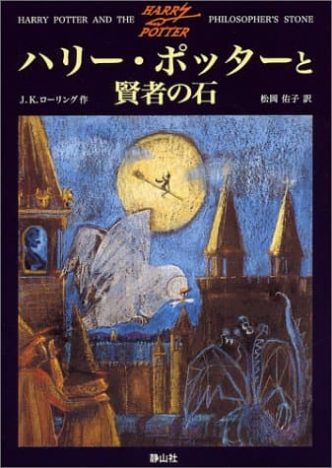『騙し絵の牙』が描く出版業界はリアルなのか? 業界人が小説版と映画版を検証

映画版…出版社や作家のマスメディア上での扱いが現実以上に過大に
映画版は原作小説とはストーリーがほぼまったく別物になっており、宣伝でも「騙し合い」がウリになっている。原作は「自分は何のために生きるのか」と問う編集者の姿がテーマだったので、作品の力点も異なる。
映画としてのわかりやすさ、ケレンの強さ優先になっていて、それゆえのおもしろさはある半面「ありえない」度合いは原作よりも増している。
出版業界人的に気になるところはたとえば以下だ。
・小説雑誌「小説薫風」の関係者が口を開けば「文学」「文学」と言っている。一般的に出版業界で「小説〇〇」と冠された雑誌は大衆文学、中間小説、エンタメ小説の雑誌であって純文学の雑誌ではない。だからそこに載る小説が直木賞を獲ることはあっても芥川賞は獲れない。だが作中では編集者が新人作家に「芥川賞を獲らせてやる」と発言したというシーンがある。
・「文学」「文学」と言ってる作家の代表作のひとつが忍者アクションもの。村上龍や吉田修一のように芥川賞獲ったあとでアクション小説書いている作家もいるから「絶対ありえない」とは言えないが……。
・ド新人の作家が雑誌に小説連載が決まっただけで記者会見が開かれる。ないと思う。
・音楽雑誌の編集長が、広告が入っていた大物アーティストの新譜をけなしてクビになったことが武勇伝的に語られる。そういう人間はそもそも編集長になれないと思う。
・文芸評論家が全国区のテレビのニュース番組にスタジオ出演して出版社経営陣の後継争いのゴシップを紹介。いや、『5時に夢中!』みたいなバラエティに出演とかならまだわかるんですがね……。
・文芸評論家が未発表の小説を新聞の文芸時評でとりあげる。
・出版社がAmazonと提携して作品の独占販売契約を結ぶ。ただこれに関しては中国のECプラットフォームと出版社とでは当たり前にやっていることなので「ありえない」とは言い切れないものの。
全体的に出版社や作家が、現実でそうである以上に、社会的に影響力が大きいように描かれている。ありがたいと言えばありがたいのだが……。
『騙し絵の牙』を「出版業界もの」だから読むという人はおそらく少なく、タイトル通りどんでん返しを期待して読む人が大半だと思うが、業界人目線で述べれば以上になる。
個人的に一番ツボったのは、映画では小説版にはない「横浜にある広大な敷地を使って出版の新しい生産・物流拠点を作る」という構想が語られ、その計画が頓挫する点である。これはどう考えてもKADOKAWAがやっている「ところざわサクラタウン」がモデルだろう。自前で企画から印刷・製本・物流まで担うことで経営効率を上げて少部数出版・重版も可能にする、というやつだ。それをくさすなんて、原作、角川文庫から出てるのに攻めすぎでは???
観ながらKADOKAWAの人たちがどう思うのか、その感想が気になってしまった。
■飯田一史
取材・調査・執筆業。出版社にてカルチャー誌、小説の編集者を経て独立。コンテンツビジネスや出版産業、ネット文化、最近は児童書市場や読書推進施策に関心がある。著作に『マンガ雑誌は死んだ。で、どうなるの? マンガアプリ以降のマンガビジネス大転換時代』『ウェブ小説の衝撃』など。出版業界紙「新文化」にて「子どもの本が売れる理由 知られざるFACT」(https://www.shinbunka.co.jp/rensai/kodomonohonlog.htm)、小説誌「小説すばる」にウェブ小説時評「書を捨てよ、ウェブへ出よう」連載中。グロービスMBA。