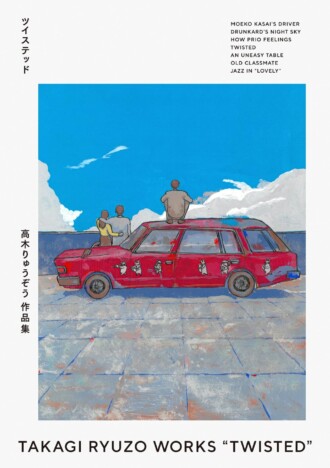理解し合えない寂しさを描き出す『違国日記』 ヤマシタトモコの繊細な詩的感覚

35歳の女性小説家・高代槙生と、15歳の姪・田汲朝が送る共同生活を描いた漫画『違国日記』(ヤマシタトモコ)。祥伝社『FEEL YOUNG』で連載されている本作の6巻が8月6日に発売された。まずは、1巻〜5巻までの物語を振り返っていきたい。
※以下、ネタバレあり

一方、両親を亡くしたという事実にまだ向き合えていない朝も、槙生が“欲しい言葉”をくれないことに孤独を感じるのだった。そんな2人を取り巻くのが、槙生の友人・醍醐奈々や元恋人の笠町信吾、後見監督人を担当する弁護士の塔野和成、朝の親友・楢えみり。それぞれに痛みや孤独を抱える彼らのサポートもあり、槙生と朝は少しずつ歩み寄っていく。そんな矢先、実里が遺していた日記が見つかった。6巻では、ようやく両親の死を実感し、襲い来る孤独と対峙する朝の姿が描かれる。
人の死というものは、実感して終わりではない。むしろ受け入れた後の方が苦しさは増すものだ。特に亡くした相手が身近な存在であればあるほど、前を向くには時間がかかる。朝にとって、実里は代わりのきかない唯一無二の母親であることはもちろん、進むべき道を照らしてくれる存在だった。
“普通”であることに固執し、密かに朝の人生をコントロールしていた実里。単純に考えれば、実里から高圧的な態度を取られていた槙生がそうだったように、息苦しさを感じるはずだ。けれど、例えば進路を迫られた学生時代を思い出してほしい。それまで同級生と同じ教室で共通の教育を受けていたのに、いきなり自分で人生を選択しろと言われ、突き放された気分になったことはないだろうか。明確な夢があれば別だが、多くの人は面倒だと感じたこともあるだろう。誰かに支配されることは煩わしい一方で、責任が生じないため楽なのだ。「何か好きな仕事がしたい」と言いながら、誰かに決めてほしいと願う朝も、実里の支配を甘んじて受け入れていたことがわかる。
6巻を読み進めていくと、朝の言葉では表現できない苛立ちやモヤモヤがリアルに伝わってくる。孤独を手軽に埋めてはくれない槙生、会話の主導権を委ねてくる学校のカウンセラー、「うざいから」と自分との恋話を拒むえみり。理解し合えない寂しさを、「誰でもがまるで違う国の言葉で話している」と表現するヤマシタトモコの繊細な詩的感覚に思わずため息が出た。