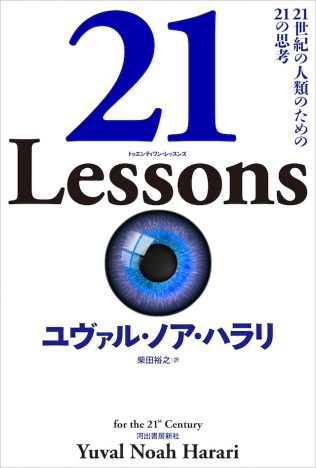独哲学者マルクス・ガブリエルの思想は過大評価か? 福嶋亮大が『新実存主義』を読む

*
ただ、自然主義を批判しつつ精神の固有性を強調するとき、新実存主義は「新しい実在論」というガブリエルの表看板を果たして必要とするのだろうか? ガブリエルは構築主義(=現実は解釈に還元できる)に対しては実在論(=解釈を超えた「意味の場」がある)を掲げ、自然主義(=心は脳に還元できる)に対しては観念論(=脳を超えた心がある)を掲げているように見える――というのは私なりにだいぶデフォルメした形容だけれども、そのように読めないこともないだろう(ちなみに、ガブリエルの知的出発点はドイツ観念論[とりわけフィヒテの観念論を内在的に批判したシェリングの哲学]にある)。だとしたら、彼の哲学はヌエ的であり、あまり褒められたものではない。
念のために言えば、本書の自然主義批判そのものは決しておかしな議論ではない。現に、心や意識に関わるすべてを科学的に記述しつくすことはできそうにないし、今のニューロン中心主義は悪しきイデオロギーに転化する危険性もあるからだ。ガブリエルの論文はさまざまな論点が整理されており、一読する価値はある。ただ、哲学に対しては遠くから見物人として接しているだけの私からしても、本書の議論は(正しいかどうか以前に)全体的に平板に思えてならない。その理由を三点、簡単に記しておく。
<1>パンデミックを含めたあれこれの問題に簡単に当てはまるということは、理論としてはたいしたものではないということである。本書も含めて、ガブリエルの著作はひとをぎょっとさせるヤバイものではなく、比較的穏健で常識的である(この点は十年前にブームになったマイケル・サンデルの共同体主義と似ている)。少なくともガブリエルは、かつて共著(『神話・狂気・哄笑』)を出したスラヴォイ・ジジェクのような悪魔的な才気を売りにするタイプではない。哲学のスターを待望する空気のなかで、ガブリエルの思想が過大評価されている面も否定できないだろう。それこそ一部の出版人やメディア人の「心」のなかでガブリエルという名が膨張しているだけではないか。
<2>自然主義が人間をニューロン(神経)に還元するとしたら、新実存主義は人間の人間たるゆえんをプシュケ(心的なもの)に還元する。だが、この肝心の心(精神)の働きについて、ガブリエルは多くを語らない。せいぜい「虚構の物語をつむぎだす多様な能力」(61頁)を挙げるくらいで、はっきり言って凡庸である。自然主義を批判するのはいいとしても、つまらない人間主義に居直るのでは、理論的には後退だろう。それに「精神」の有無をもって、人間を規定するやり方にも問題がある。例えば、身体として姿を現さず、心があるかどうかもわからない胎児はどういう扱いになるのか? 胎児は人間ではないのか? あるいは逆に動物には心はないのか? 疑問は尽きない。本書はところどころ「人間以外」とされたものを不当に軽視しているようにも思える。
<3>ハイデッガーという巨星を生みながらナチズムに到ったドイツに代わって、戦後は長らくフランスが哲学の拠点となってきた。戦後ドイツの思想は、主にフランクフルト学派の衣鉢を継ぐ社会学や政治思想によって名声を得てきた。そのなかで、ガブリエルはドイツから久しぶりに出た哲学の新鋭であるには違いないし、「新実存主義」という命名にも野心が感じられる。にもかかわらず、ガブリエルは新実存主義がかつてのサルトルらの実存主義と何が同じで何が違うのか、ほとんど触れようとしない(冒頭でマクリュールが多少触れている程度)。思うに「人間」の捉え方について、新実存主義が実存主義よりも前進したとは言い難い。例えば、ベルナール=アンリ・レヴィの大著『サルトルの世紀』は「実存主義はヒューマニズムである」と言ったサルトルのなかに、あえて「実存主義は反ヒューマニズムである」という別のラディカルな一面を読み込もうとする。あるいはメルロ=ポンティにしても、幼児の世界について優れた洞察を残している。こういう奥行きは、すなおに人間主義に基づく新実存主義には見られない。
ともあれ、昨今の唯物論や実在論、あるいは認知科学や遺伝子工学は哲学に大きなショックを与えるものである。それらによって、用済みとなりかねない「人間」について、ガブリエルは自然主義を敵としながら、もう一度新たな位置づけをおこなおうとする。この新実存主義の試みそのものは私は面白いと思うが、その闘い方については不可解なところが多く残る。結局のところ、今は過渡期なのだろう。
(※)この点は『現代思想』2018年10月臨時増刊号に載ったマウリツィオ・フェラーリスの論説「新しい実在論」が詳しい。なお、この号の座談会で宮崎裕助が指摘するように、ガブリエルがポストモダン思想を「構築主義」の名のもとにひとくくりにするのはおかしい。というのも、フランスのポスト構造主義者は、むしろそのような現実の構築作業が矛盾をはらみ、いわば内在的なエラーに直面するところに、唯物論的な契機を見出したからである。
このことは日本のポストモダンの批評にも当てはまる。蓮實重彦、柄谷行人、中沢新一、浅田彰、東浩紀らはそれぞれ扱う対象も理論も大きく異なるものの、総じて唯物論を自己の思想に取り込んできた。例えば、東の『存在論的、郵便的』は、主体の裂け目(=存在論的/ジジェク的/ドイツ観念論的)に加えて、コミュニケーションの失敗(=郵便的/デリダ的/唯物論的)から「不可能なもの」を思考するというアイディアを示したものである。
しかも、彼らは実在論(唯物論)が観念論より優れていると言ったわけでもない。柄谷は1984年のシャープな評論「批評とポスト・モダン」でアルチュセールを引きながら「観念論が革命的な「意味」をもつ時期と場所があるし、唯物論が保守的な「意味」をもつ時期と場所がある」と述べ、ニーチェを参照しながら「主観に問わねばならず、主観に問うてはならない」というパラドックスを引き出す。我々は結局こういうパラドックスから逃れることはできない。さらに、柄谷と近いことを言っていたのはアドルノである。「批判的思想の狙いは、かつて主観が占めていたが今は見捨てられている玉座に客観を据えようということではなく――玉座に据えられた客観など一つの偶像でしかあるまい――、こうした階層秩序を廃棄することなのである」(『否定弁証法』)。実在論か観念論か、客観か主観か、いずれかを「玉座」に据えようとすることそのものが間違いなのである。
■福嶋亮大
1981年京都市生まれ。文芸批評家。京都大学文学部博士後期課程修了。現在は立教大学文学部文芸思想専修准教授。文芸からサブカルチャーまで、東アジアの近世からポストモダンまでを横断する多角的な批評を試みている。著書に『復興文化論』(サントリー学芸賞受賞作)『厄介な遺産』(やまなし文学賞受賞作)『辺境の思想』(共著)『ウルトラマンと戦後サブカルチャーの風景』『百年の批評』等がある。