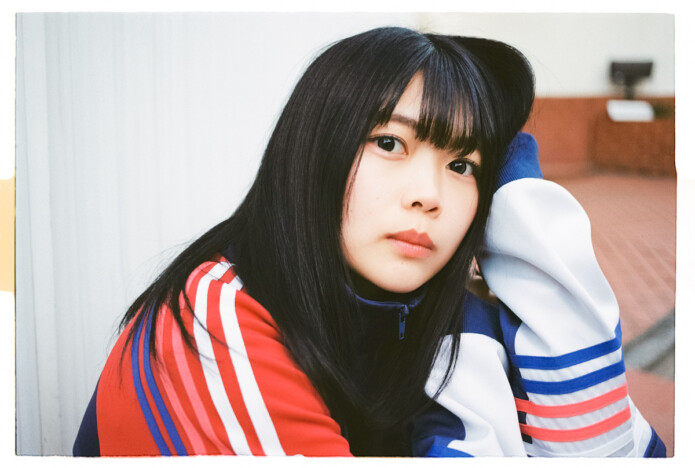「石井恵梨子のライブハウス直送」Vol.1:えんぷていの音楽が呼び起こす郷愁 “ロックバンド”であることへの矜持

コロナ禍以前の活気が戻ってきたライブハウス。人と集まることも声を出すことも禁止されていた時期の反動もあり、ここでは今、若いミュージシャンが次々と面白いことを始めている。私、ライターの石井恵梨子が、ふらっと出会った若手バンドに注目し、ライブレポートを兼ねながら、本人の声も直接聞いてしまおう、というこの企画。以前の連載とは名前を変えてリニューアル再開です。
人の溢れる金曜夜の渋谷駅。そこをくぐり抜けて到着したWWWはとても静かだった。開演前の期待が静寂になる、というのもあるのだけど、流れているアンビエントのBGM、点いたり消えたりを繰り返すフロア照明、あとは時間を置いて流れてくる「まもなく、えんぷてい、『TIME』ワンマンツアーファイナル、東京公演が開演いたします」というアナウンスが、当機はまもなく出発します、みたいな飛行前の気分を演出しているのだ。宇宙旅行だろうか。それとも80年代や70年代へのタイムトリップか。1曲目「whim」が始まった瞬間そんな気分に襲われる。
ゆったりと進むリズム隊、クリアな単音をぽろぽろと紡ぐ2本のギター、音の隙間をそっと埋めていくキーボード。街の喧騒をすっかり忘れるくらい、5人のサウンドはおおらかで、同時にどこか懐かしい。具体的な記憶ではなくて、春が巡ってきた時になんとなく体が喜びを覚え、夏の夕暮れを見るとなぜか切なくなってしまう、DNAに組み込まれた郷愁のようなものだ。さらにメンバーはレトロな背広姿、ギターの比志島國和に至ってはヒッピー風のちりちりパーマなので、一体どこからきたのかわからないところがある。えんぷてい。2020年に名古屋で始動、現在は東京に拠点を構える5人組である。

「聴く音楽は幅広いんです。古いジャズが好きな人もいるし、最先端のアイドルソングが好きなメンバーもいる。ただ、時代を選びたくないっていう意識はずっとあります。いつの時代もいいと感じるものって、あんまり変わらないと思うんですね」(奥中康一郎/Vo/Gt/以下同)
柔らかいサウンドの中心にあるのは奥中の歌である。これまたタイムレスなメロディ。少しだけひねった半音のズラし方。ポップな曲なら大瀧詠一、憂いのある曲ならKIRINJIあたりを引き合いに出したくなるほど上質な歌ものだが、メインシンガー+バックバンドというわけでもないのだ。

たとえば3曲目「TAPIR」。歌が終わった後に始まるのは石嶋一貴(Key)のピアノソロで、奏でる旋律はメロディ以上にロマンティック。さらにギターふたりがドラムのほうを向き即興セッションが始まっていく様子には、バンド特有のダイナミズムが強く感じられる。シティポップやドリームポップと分類されることが多いようだが、ロックバンドであることには人一倍こだわりがある。
「同期を一切入れたくない。5人で完結するところがバンドの格好よさだと思っていて。バンド然としたバンドが好きですね。今あまり言う人もいないけど、この場所で勝負するぞっていう気持ちで東京にきたところもあります」
続く4曲目の「眠らないで」はサイケっぽいギターがループする曲で、メロディがややダーク。2021年に発売された曲だ。翌年に出た1stアルバム『QUIET FRIENDS』までの彼らには、薄靄がかかったように幻想的な曲、ほんのりと寂しさの漂う曲が多かった。バンドで勝負する、などと言い切る人たちには見えなかったが、それはスタートの話と大きく関係があるらしい。
えんぷていの原型は大学の軽音サークルにある。メインで歌う奥中と、当時ギタリストだった赤塚舜(Ba)のバンドが、他の大学との合同ライブのオーディションに応募。1位通過でトリ決定となり、大喜びでさらなるオリジナル曲を作っていた矢先、コロナ禍がきて肝心のライブ自体が消えてしまった。想像を絶する虚しさと悔しさだろうが、これが逆に奥中のバンド魂に火をつけたらしい。
「曲を披露する場所がない、じゃあ学校の外に出てバンドやろうって話になるけど、誰もついてきてくれなかったですね。ひとりになって、初期メンバーの比志島くんと石嶋くんと始めることになって。それも音源作るだけで、やっとライブができたのも半年後くらい。最初はほんと苦しかったですね」