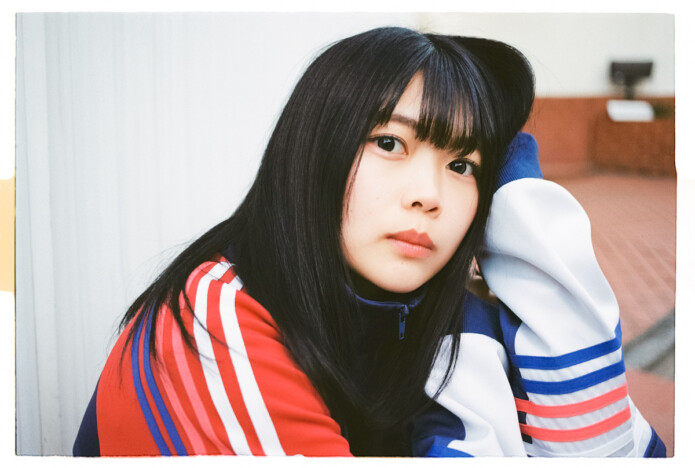Nothing's Carved In Stoneはまだ見ぬ場所へ進んでいく 結成15周年記念日本武道館ライブで確信した強さ

今年15周年を迎えたNothing's Carved In Stoneが、日本武道館のステージに帰還した。10周年イヤーの2018年に初めて武道館に立ち、満場のオーディエンスとともにバンドの歩みを讃えてから約5年。2度目の武道館公演は、ますます進化したNothing’s Carved In Stoneの強さを確信し、彼らのこの先に夢が膨らむ、そんな一夜だった。

何と言っても、リスナーからのリクエスト上位20曲と、メンバー自身が11枚のアルバムから1曲ずつ選んだ11曲を含む合計30曲以上演奏されることが事前に告知されていたことが大きい。そもそも緻密で精細な楽曲が多いNothing's Carved In Stone。卓越したスキルを持つ4人とはいえ、一度のライブで30曲以上の演奏はチャレンジだっただろう。
結果として、楽曲はアンコールを含めて全32曲に及んだ。「ツバメクリムゾン」「You’re in Motion」など武道館を揺らす骨太なロックから、「Words That Bind Us」「Gravity」といったメンバー同士のスリリングな掛け合いが映えるテクニカルな楽曲、軽やかなメロディに体が揺れる「Red Light」「きらめきの花」や、外せないキラーチューン「Like a Shooting Star」「Spirit Inspiration」まで――時代を行き交いながら15年を網羅するセットリスト。メンバーは疲れを感じさせないどころか、どんどんバンドアンサンブルの熱量を高め続け、約3時間に及ぶライブを圧倒的なパフォーマンスで駆け抜けた。音楽を愛する者、とりわけロックとロックバンドを愛する者にとっての理想郷がそこにあった。

幕開けは、15年のバンドの歴史を振り返る映像から。エモーショナルなムードが漂った直後、感傷を断ち切るように生形真一(Gt)の鋭いピックスラッチが響き、「Out of Control」でライブはスタートした。「声、聞かせてくれ!」と村松拓(Vo/Gt)が叫ぶと、拳を上げて応えるオーディエンス。早くも一体となって盛り上がる武道館の光景に、ビジョンに映された4人の表情は喜びにほころんでいた。

続く「Deeper,Deeper」では生形のヘヴィなリフが轟くなか、華麗なフレーズワークで魅せる日向秀和(Ba)と、タイトかつ豪放な大喜多崇規(Dr)のドラミングが絡み合い、無二のグルーヴが会場を席巻。そのグルーヴを乗りこなす村松の歌声も伸びやかで、あっという間に武道館を掌握してみせた。
4人のプレイヤビリティは今さら説明するまでもないが、さらに楽曲の魅力を際立たせていたのが演出面だった。前回の武道館ではシンプルにバンドを立たせていたのに対し、今回は曲によって映像や照明、特効がより駆使され、武道館ならではの光景を生み出していた。

都市の映像をクールにコラージュした「YOUTH City」や、リリックビデオ風の演出が胸を打つ「村雨の中で」、リアルタイムでメンバーの姿が映し出されると日向の眩しい笑顔が会場を熱くする。また、ソリッドなギターリフにリンクしてレーザーが瞬いた「Stories」や夜明けを思わせる色合いに染まった「Walk」など、照明、映像を含めた演出も秀逸。これまでのライブはやはりテクニックやサウンドのよさにまず耳が奪われていたが、演出が加わることで、あらためて楽曲そのものの世界観、歌詞のメッセージ性の奥深さを体感することができた。

もちろん、バンド自身をフィーチャーする演出もたっぷり用意されていた。ド派手に炎の特効が打ち上がるなかでソロを弾く生形は間違いなくギターヒーローであったし、ピンスポットライトに照らされてスティックを掲げる大喜多やベースソロを披露する日向、「In Future」でハンドマイク片手にステージを練り歩く村松と、まさに全員が主人公として並び立つ存在感を堪能した。

もうひとりライブに華を添えた存在が、サプライズゲストのSOIL&"PIMP"SESSIONS・タブゾンビ(Tp)だ。セッションライブなどで特に日向と共演の多い盟友である。ミドルチューン「Walk」の間奏で静かに姿を現し、情熱的なトランペットソロが響くやいなや、大歓声に迎えられた。続く「Inside Out」ではパワフルな音色でバンドサウンドを彩り、後半の「Spirit Inspiration」と「Idols」でも再び加勢。生形と向き合ってソロバトルを繰り広げたり、日向のベースラインと絡んだり、普段ゲストを迎えることの少ないNothing’s Carved In Stoneにとって、新たな刺激となったに違いない。
築いてきたキャリアに甘んじることなく、ストイックな部分はよりストイックに、遊べる余白はより自由に。そうしてバンドの進化が止まらないのは、根底を支えるメンバー間の絆、ファンとの絆があるからだろう。

特にそう感じたのは、本編が終盤にさしかかる頃に披露された「November 15th」だ。村松が「次の曲だけ順位発表しようかな」と告げ、「大切な曲なんです……リクエストありがとうございます、1位の曲です」と紹介されたこの曲は、タイトルの“11月15日”を記念日として毎年ライブが開催されてきたほどの一曲。生形が爪弾く優しい音色から、青い照明が灯り、村松の歌うメロディが静かに心に染み渡る。聴き入るオーディエンスも、丁寧に届けるメンバーも、この曲が演奏されてきた歴史=ともに歩んできた時間に想いを馳せたはずだ。疾走感が高まる曲の後半で金色の紙吹雪が舞い、祝祭ムードをひときわ感じる場面となった。

さらに、バンド結成後初めて生まれた曲「Isolation」を畳みかけたあと、初期の名バラード「BLUE SHADOW」が本編のラストとして贈られた。原点を確かめつつ、楽曲の持つ牽引力も包容力も当時より何倍にも膨らんでいるのが伝わってくる。ビジョンには、4羽の鳥が曇り空から青空、宇宙へと羽ばたいていく幻想的な映像が展開。歴史を愛しく抱きしめながら、未来への希望を繋ぐエンディングだった。