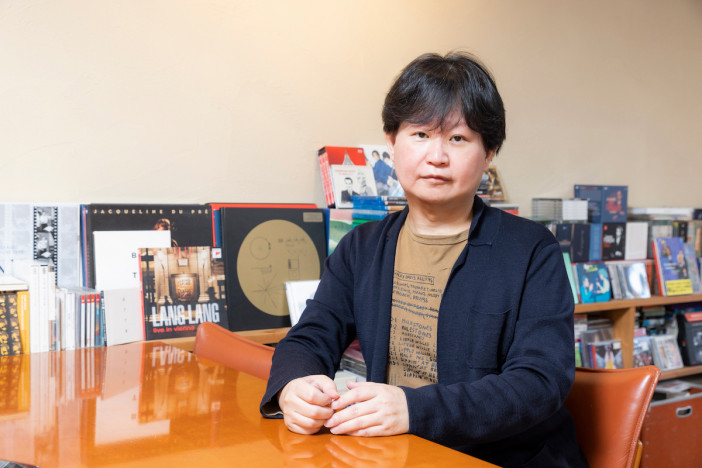矢野沙織、菊地成孔と作り上げたソロアルバム『The Golden Dawn』 20年の集大成に奏でる“祈り”

デビュー20周年を迎えたジャズサックスプレイヤー・矢野沙織がソロ名義では8年ぶりとなるアルバム『The Golden Dawn』をリリースした。ストリングスアレンジを菊地成孔が手掛け、ビ・バップのスタンダードナンバーとオリジナル楽曲が多彩なサウンドを響かせている作品だ。彼女の思うビ・バップの本質が表現されている点にも注目させられる。本作に込めた想い、制作エピソードについて語ってもらった。(田中大)
「今がいちばん暗くて、明るい夜明けがありますように」という願いを込めた

――どのようなアルバムにしたいと思っていましたか?
矢野沙織(以下、矢野):チャーリー・パーカーとオーケストラでレコーディングした『Charlie Parker With Strings』というアルバムがあって、ラグジュアリーな印象で聴く方もいると思うんですけど、私は昔から彼の演奏に対して不安定なもの、畏怖を感じていたんです。そういう足元の悪さのようなものをぜひ自分でも表現したいと思って、菊地成孔さんに相談しました。
――ストリングスが加わった「Rocker」「Autumn Leaves」「I'm In The Mood For Love」は菊地成孔さんのプロデュースですが、プロデューサーさんがついた作品は今回が初めてだったんですね?
矢野:はい。いろいろな相談をさせていただきました。
――菊地さんと具体的には、どのようなお話をしました?
矢野:ビ・バップはスポーツ感覚で明るくなってしまう傾向があるので、そうじゃない風に録りたいというようなことをお話ししましたね。ビ・バップの快楽/多幸感って、本当はドラッギーな雰囲気があったりとかすると思うんですけど、そういう前知識のない子供の頃に抱いたあの印象は――なんと言うんでしょう、不良の音楽とまでは思わなかったけれど、触れちゃいけないものに触れたような感覚だったんです。そういうようなことをお話しして、菊地さんも同意してくださったので上手くいったんだと思います。
――チャーリー・パーカーを含めたビ・バップの名演はスピリチュアル、サイケデリックというか、異世界の扉を開くような禍々しさを持っていますよね。
矢野:おっしゃる通りです。なかなか同意してくださる方がいないんですけど(笑)。私がチャーリー・パーカーに感じるのもスピリチュアルなものなので、それをアルバムでも出したいと思っていました。
――演奏のソロ回しで生まれる感覚はリスナーにとってもトランス状態というか、サイケデリックな体験です。プレイヤー同士がポジティブな意味でバトルしているような感覚も、今回の矢野さんのアルバムから感じました。
矢野:決してマリアージュしていなくて、いい意味で混じり合っていないというか、家庭内別居状態というか(笑)。同じ家に住んでいるのに自分は自分だというような、そういうものが出てよかったなと思っています。
――矢野さんにとってチャーリー・パーカーはジャズに夢中になったきっかけですが、世間の人々の間でなんとなく形成されているビ・バップに対する印象への違和感が長年にわたって蓄積されていたんですね?
矢野:それはありましたね。特にアメリカに行くとハコ付きのセッションのホストだったりとか、ビ・バップ疲れしている一流のプレイヤーがたくさんいるんです。そういう人たちのビ・バップって、暗いんですよね。それは疲れているからなのか、同じ曲をやり続けることに飽きているからなのかはわからないですけど、それくらいビ・バップってスモーキーなものなんです。そういう頽廃感を出したいと思っていました。
――おそらく多くの人のビ・バップの印象は、また別の感じなんでしょうね。
矢野:そうだと思います。ビ・バップの一人者は国内外を問わず「明るく元気よく上手に!」という感じですから。なぜかいつの間にかそうなっていて。ディジー・ガレスピーですらそうなっていて、今やフュージョンとかの超絶技巧のものと変わらなくなってきているような私の体感があったので、「それは違うんですよ」ということを体現したかったんです。
――ビ・バップはビートニク文学ともリンクしていましたし、もともとは既成の価値観への反発というか、アウトロー的な精神性がある音楽ですよね?
矢野:昔はそうだったんですよね。あと、ラップともリンクしている部分が大きいと感じています。クリント・イーストウッドが監督した映画『バード』のようにダメな人からセッションを外されていくような露骨さはなかったけど、ひとりにつき8小節ずつ吹いていって、だんだん有名になっていくというのは本当にそうだったみたいです。当時の空気を吸っている私の師匠 ジェームズ・ムーディから聞きました。それって即興のラップバトルと同じことですよね。そういうなかで出てきてしまったのがチャーリー・パーカーです。
それまでのビ・バップはあんなに速くなくて、ブルースを吹くくらいのものだったそうです。ニューオリンズからNYに波及して発展したそういう文化のなかに急にチャーリー・パーカーが現れて、すべてが大きく変わったんですよね。ムーディはその当時の人たちよりも年下なので、そういう状況になっていた頃にはまだ物心がついていなかったそうですけど。
――ビ・バップは戦後のカウンターカルチャーの源のひとつですよね?
矢野:そうなんだと思います。ビ・バップの最初の頃は1943年とかなので戦争中ですけど。でも、そういうなかで生まれたエネルギーを「元気になるものだ」と曲解してしまっている部分が現代にはあるように感じていて。それはディジー・ガレスピーの大罪だと私は勝手に思っているんですけど(笑)。ビ・バップがアカデミックに体系化されてジュリアード音楽院で教えられるようになったり、チャーリー・パーカーが吹いたことは本当はちょっと違うけど、音楽理論に当てはめて誰でも練習できる教則本になったり。そういうのは偉業ではあるんですけど、弊害とも表裏一体だったのかなと思うんですよね。
――アカデミックに解析できる部分はありつつも、もっと野性的、本能的な衝動に根差したジャズがビ・バップということでしょうか?
矢野:そうですね。私は戦争反対ですけど、戦争の度に飛躍していってしまう面もあって、そういう出来事が起きる時の若者の力ってすごいんだと思います。「俺は兵隊に行きたくないんだよ」「友達が戦争で死んだんだ」という感情を抱くのは決していいことではないですけど、音楽の発展には関連していると言わざるを得ないなと思っています。
――音楽は時代性を反映する部分もありますが、矢野さんの今回のアルバムもそういうものが表れていると感じていますか?
矢野:『The Golden Dawn』というタイトルの由来にもなってくるんですが、「今がいちばん暗くて、このあとに明るい夜明けがありますように」という願いを込めたんです。「今こういう陰謀があるよ」ということを言おうとは思っていなくて、ただ祈る気持ちですね。「夜明け前がいちばん暗い」という美しい言葉があって。“dawn”は“夜明け”としか訳しようがないけど、私は丑三つ時のことを指していると思っています。そういういちばん暗い段階に今いるのかなと。私も20年間音楽をやってきて、16歳でデビューした時に華やかな気分にはなれなかったタイプなんですね。いろんなことを言われましたし、随分いじめられましたし、人種差別も受けました。そうやって20年続けてきて、「今がいちばん踏ん張る時」「今がいちばん暗くて、これから明るくなっていきますように」「私の音楽も含めて、みなさんがそうなっていきますように」という願いを込めたタイトルが『The Golden Dawn』です。どれか特定の曲がそうということではないんですけど、全体的にそういう気持ちで作りました。
――世のなかに少しでもポジティブな何かを届けたいという願いは、音楽活動の原動力になっていますか?
矢野:「世のなか」と言うと分母が大きくなってしまう気がするんですけど、少なくとも音楽を聴きながら感じる何かがあればいいなと思っています。私が小さかった頃にMDがようやく出てきて、ポータブルのCDやカセットプレイヤーが大好きでした。外で初めてジェームス・ブラウンを聴いた時、ただの貧しい生活がいきなり映画になったような感覚だったんですよね。普段、家のステレオで聴いていた時は、そんなことは考えなかったんですけど。私は小さい頃、鉄工所の廃屋が近くにあるような場所で育ったんですが、そのすべてが映画のように感じられたんです。今は音楽を携帯できるのが当たり前になっていますし、私の音楽もそうなってほしいです。聴いた人の見ているものが映画になればいいなと。そういう想いでやっています。
――ジェームス・ブラウンを聴いてそんな感覚になったお子さんって、とても素敵ですね。
矢野:娯楽がなかったんです。家がとても貧しくてテレビもゲームもなかったから、本を読むか窓の外を見るかくらいしかなくて(笑)。だから、音楽が携帯できた時の感覚には、ものすごいものがありました。ジェームス・ブラウンもボブ・マーリーも好きでしたね。英語も好きで、人種によって喋る言葉のリズム、テンポが違うということにもとても憧れました。