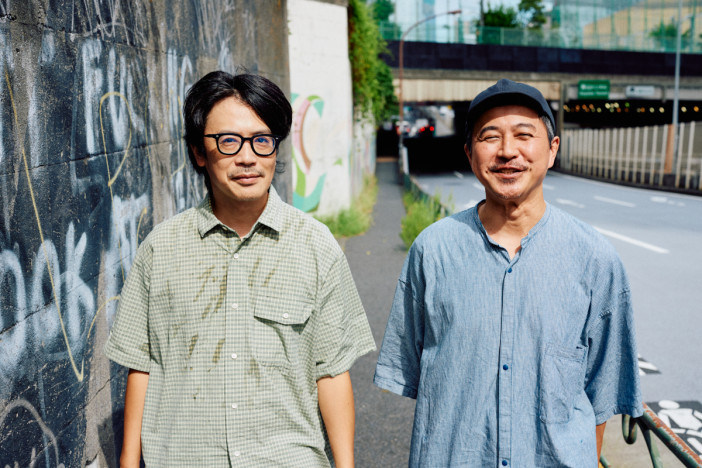くるり×田中宗一郎が語り合う『感覚は道標』が2023年に生まれた意味 オリジナル編成で見出した“原点回帰ではない新しさ”

「50~60年代にやってきたことを、今のフィーリングでやればこうなる」
――こうして作られたアルバム『感覚は道標』ですが、タナソウさんの第一印象は?
田中:「太鼓のレコード」だと思った。そして、最後にバラッドはあるけど、基本リズムのレコードだし、リフのレコード。つまり、まごうことなきバンドのレコード。「俺、ロックンロールって、こういうところが好きだったんだ」ってちょっと思い出しました。
岸田:それを言わせたかった。
一同:(笑)。
田中:ここ10年間、バンドではない音楽ばかりに夢中になっていたけど、ここ2~3年バンドが再定義されつつあるみたいな感覚も自分自身の中にあって、繁くんと「バンドめっちゃありやで」みたいな話もしてるんですよ。
――アメリカのメインストリームな音楽を見ても、ロックが再注目されているのは明らかですよね。
田中:でも、バンドといってもバリエーションがあるし、今のロックバンドって2010年代のデジタルなプロダクションに最適化した後に、もう1回バンドサウンドに回帰するためのストラグルをしているタイミングなんですよね。そんな中、くるりの新作は「50年代や60年代にやってきたことを、今の時代に、今のフィーリングと今のソングライティングと今のアンサンブルでやればこんなものができるんだ」と感じるものになっていた。
岸田:嬉しい。まさにそうだと思います。
田中:なおかつ、1曲目と2曲目でアガるレコードじゃないですか。そこも好きなんですよ。
岸田:そうそう。「絶対にこれは1曲目。これは2曲目」って思ってた。アルバムの冒頭で「The Rolling StonesとThe WhoとThe Beatlesがやってくる」みたいなイメージ。
田中:(笑)。
森:1曲目と2曲目は特にそうなんですけど、今回、僕は本当にドラムの音からインスピレーションを受けましたね。繁くんがもってきたトリクソンっていうメーカーのドラムなんですけど、キックはドワーンと鳴るし、タムは50年代のジャズみたいな音がするんですよ。そうすると、やっぱりプレイもそっちに引っ張られるというか、音からフレージングまでイメージできて面白かったですね。

岸田:数年前にサンフジンズをやっていた時に、奥田民生さんがトリクソンを見つけて買ったんですけど、個体差がかなりあるので「全員買え」という指令が出て、バンドメンバー3人で4台買ったんですよ。
佐藤:民生さんは2台も持ってるんだ(笑)。
岸田:そう。全曲ではないけど、そのドラムを今回のレコーディングで使って。特に「doraneco」に顕著ですけど、26インチの大きなバスドラかつ形状的にちょっと緩めのチューニングになるので、踏んだ時にバーンとボンゾ(Led Zeppelinのジョン・ボーナム)みたいなキックの音がするんですよ。
佐藤:芯がないから、ライブで遠くに飛ばそうと思っても飛ばないし、周りの楽器を邪魔する音なんだけど、ごった煮感があって、好きな人は好きなサウンドなんですよね。
岸田:普通のエンジニアは嫌がるけど、伊豆スタジオのエンジニアは面白がってくれたし、NEVEの卓やヘッドアンプとの相性が良かったですね。ドラムのマイキングも広いスタジオだからできるトップ中心のサウンドで作ってもらいました。
――それが今作の「スタジオ全体が鳴っている」ようなサウンドに繋がっているんですね。
田中:いかにスタジオの環境や楽器、メンバーやエンジニアの関係性が音楽に影響を及ぼすかっていう、ロックバンドによるレコーディングの歴史が証明してきたものが、またここでも証明されているようなレコードだよね。
岸田:そう。現場の効率化や流行によってとっくに失われていたやり方なんだけど、かつて当たり前だったことをやればこうなるんだって再発見があったというか。「知ってることをやろう」と思えたきっかけになりましたね。だから今回ソングライティングに気合いはほとんど入れてないんですよ。
田中:でも、本当に不思議な作品だと思う。「初期メンが集まってジャムで作ってアナログ一発録音で」っていう作品でもないよね。
岸田:そうなんですよ。『天才の愛』(2021年)なんかで培った匠のポストプロダクションを結構丁寧にやりました。「happy turn」はほぼ何もしていないけど、「I'm really sleepy」「In Your Life」「California coconuts」とかは緻密にやってますね。
田中:ギター、ベース、ドラム以外の楽器の音もいろいろ入ってるよね。若々しくフレッシュな作品なんだけど、なんだか20代の鬱屈みたいなフィーリングもあって、やっぱりすごく「不思議だなー」って感じるレコードだと思う。
岸田:今回のリユニオンって、思い出話をしているわけじゃなく、そのまま当時に戻っているような感覚なんですよ。実際にあの頃のくるりをもう一度やっている感じというか。合宿をしていても、当時の関係性はもちろん、空白期間のそれぞれの経験も全部出てきて。それはすごく楽しかったし、宝物のような時間でしたね。

田中宗一郎がアルバム曲を採点 ビートと構成のアルバムか?
田中:自分のテイストでアルバム全曲を三つ星で評価してみたんですけど、満点の曲は「happy turn」「I'm really sleepy」「LV69」「馬鹿な脳」「世界はこのまま変わらない」でした。
岸田:星一つは?
田中:「window」と「doraneco」です。
岸田:なるほど。
田中:すみません(苦笑)。
岸田:いやいや(笑)。でも、傾向はありますよね。
田中:満点の5曲はやはりビートですよね。
岸田:「window」はビートが寝てますよね。「doraneco」は結構ビートミュージックかなと思うんだけど。
田中:そう、「doraneco」は結構好きなんだよね。まあ、あくまで最初に聴いた時の印象でつけた星だから。でも、「決定的な1曲は?」と聞いたら、みんなが違う曲を選ぶようなレコードだと思う。
岸田:うん。決定的な1曲は作れなかったというか、「作らなくていいかな」という感じがあったんですよね。みんな「東京」みたいなのを期待すると思うし、僕もそういうムードになれば書こうとは考えてたんですよ。でも、今回の気分やスピード感、そしてタイミングなんかを考えて、「ここで“良いソングライティング”をしちゃうと、このセッションを壊しちゃう」と思ったんです。
田中:俺はThe Beatles原理主義者じゃないですか。『Rubber Soul』(1965年)、『Revolver』(1966年)、『The Beatles (White Album)』(1968年)という名盤において、決定的な1曲はどれかというと……。
岸田:ないです。
田中:でしょ? アルバムの醍醐味ってそれじゃないですか。シングル曲の醍醐味と、やっぱりアルバムの良さは別だと思うので、今回のくるりのアルバムには「いいアルバムというものは、こういうものだ」という感じがある。「THE アルバム」ですね。
――「東京」みたいな曲がないからこそ、ロックンロール・レコードとして聴けますよね。
田中:『さよならストレンジャー』(1999年)が「東京」で語られることが嫌なんですよ。俺みたいな、ひねくれたくるりファンは。
岸田:レビューを読んでそれは伝わりました(笑)。
田中:もっと言えば、シングル『東京』(1998年)において「尼崎の魚」のことが語られないのが、気に入らない(笑)。
一同:(笑)。
田中:それってオルタナティブな価値観かもしれないけど、ポップミュージックの歴史はオルタナティブな価値観が支えてきたものであるので。今回のアルバムは、くるりがそこに接続したキャリアを積んできたっていうことの証明にもなっていると思います。

――「LV69」の歌詞〈サビの無い曲〉を聴いて「きたー!」って思いました。前回の対談記事(※2)の話題とも繋がっているというか。
岸田:僕、くるりの曲にはサビが結構あるって思っていたんですけど、「サビないですね」って言われることが最近増えてきたんですよ。「いや、あるけど」って(笑)。
田中:ここ数年で「これは新しい」と思った音楽が2曲ぐらいあって。それは構成の話なんだよね。まず、デュア・リパの「Levitating」は、昨今の北米圏の音楽らしく4つのコードの繰り返しのループなんだけど、その上でコーラスに聴こえるフロウが5~6種類あるっていう。
岸田:なるほど。
田中:北米の音楽は相変わらずループ主体で、ビートの抜き差しをしながら、その上に乗るメロディのフロウが変わっていくというのが基本なんだけど、その中でも「Levitating」は一番今っぽい構成だと思います。そして、ピンクパンサレスの「Boy's a liar」も、アイス・スパイスのラップが入らないオリジナルバージョンの時点で、どれがコーラスかわからない構成になっている。でも、メロディもリズムもどんどん変わっていくから、誰もがそのどれかを好きになるし、その変化自体を好きになるっていう曲。
岸田:行って楽しいスーパーマーケットみたいな。
田中:そうそう。J-POPはここがサビっていうのが明確にあるけど、今の北米圏の音楽は「楽しい楽しい」って感じのまま終わって「どこが一番楽しかったっけ」となる感じ。
――今回のアルバムだと「世界はこのまま変わらない」はそれに近いものを感じましたね。メロディ的には〈Hello my friend〉の部分がコーラスっぽいけど、僕の感覚では歌い出しの部分こそがコーラス的な立ち位置です。
岸田:ああ、あの曲はそうですね。結果的に〈Hello my friend〉をサビっぽくしたけど最初はブリッジのつもりで、歌い出しを一番盛り上げようと書いてました。その一方で「doraneco」はヴァースしかないんですけど、あれは今回のアルバムの中で唯一ジャムセッションじゃなく、伊豆を散歩している時に頭の中で流れていた、自分の頭の中で書いた曲ですね。あとは「I'm really sleepy」もBメロ始まりになっていて、「California coconuts」もいわゆるコーラスが真ん中に1回出てくるだけなので、シンプルなアルバムに見えて、構成の冒険はちょこちょこしたかもしれませんね。
田中:くるりって、コーラスよりもバンド演奏とヴァースでの高まりを軸としたソングライティングをやってきた、日本語圏では数少ないバンドの一つなんですよね。そもそもは英語圏もそうだったんだけど、ラップソングに歌が入ってきて、その部分が「フック」と呼ばれるようになった頃からJ-POPの構成に近づいてきたんです。で、それに影響を受けたポップスでもコーラスらしいコーラスがなくなり始めて、デュア・リパみたいな「全部フック」という構成になっていった。
岸田:うんうん。
田中:だから、2023年って、くるりがやってきたことと英語圏のループミュージックがやってきたことが、期せずして似通った位置に来てる不思議なタイミングと言えるかも。
岸田:このアルバムは時代感がよくわからないことになってる。

――今日のタナソウさんはBlurのTシャツを着てますけど。
田中:そう。21世紀は時間軸がねじれたんですよ。2010年代まではポップミュージックには最新のモードがあって、ミュージシャンはそれにある程度アジャストした上で自分自身のオリジナルを見せるのが必須だった部分があったと思うんです。でも、2023年現在、一週間単位でトレンドが生まれて一週間後には忘れられ、大きなトレンドにはならないものの常に流行が変わり続けるという状況なんですよね。そして、それがあちこちで積み重なって、時代がモザイク状にねじれている。チャートアクション的にも、TikTokで生まれるヒット曲を見ても、突然20年前の曲が流行ったと思ったら、次はまた別の時代のものが流行り始めるっていう。
――なんでそれが流行ったのか解明できない時代ですよね。
田中:だからこそ、今は何をやってもありで、「やりたいことをやったやつの勝ち」っていう気分はある。2023年の面白いレコードを見ても、それはやりたいことやっている作品なんだよね。
岸田:あー、それはわかる。
田中:だからBlurの新作(『The Ballad of Darren』)もダメなレコードなんですけど、超いいのよ。ライブ(『SUMMER SONIC 2023』)も本当にダメだったんですけど、超感動したし。