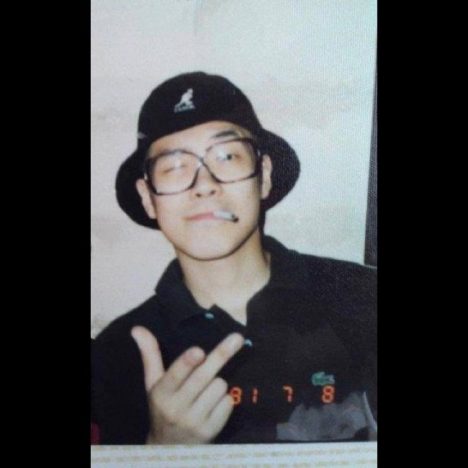荏開津広『東京/ブロンクス/HIPHOP』第1回
荏開津広が日本のヒップホップ/ラップ史を紐解く新連載 第1回:ロックの終わりとラップの始まり
ポピュラー・ミュージックの歴史のタイムラインで起こっていたのは次のようなことだ。1970年代後半、ロンドンでのパンクの登場がロックの死を宣言し、さらにポスト・パンクがロックをばらばらに解体した。ほとんどの人間はそれを真剣にとっていたのかどうか怪しかったが、実際にロックのイデオロギーは映画にあるスロウ・モーションの場面のように天井ごと崩れ落ちていって、ダンス・ミュージックとラップの時代がやってきたのであった。
ロックは決してなくなったのではない。だが、金坂健二に『幻覚の共和国』だと呼ばせ、日向あきこに『原始の心』と形容させ、渋谷陽一に雑誌『rockin’on』を創刊させた“共同幻想”としてのロックの役割が終わっていったことの再確認はしておきたい。そこに現れた隙間に埋め込まれたのがヒップホップ〜ラップ・ミュージックだった。つまり、その頃、中村とうようが慣れ親しんでいたブラック・ミュージックも溶けていった。ポップ音楽全体が変わった。
ヒップホップは、「現代の異民族、アメリカの時だ。暴力、横暴、浪費、拝金主義、はったり、群衆本能、愚昧、下劣、無秩序だ」(註1)と叫ばれた時代のアメリカに、すべての人々が嫌って忘れようとした一画、ニューヨークのサウス・ブロンクスから生まれた新しい言葉とビートだ。日本語ラップはその空間の延長線上にある。こうしたことに関心のない人々が日本語ラップを軽視し、嘲笑う。
時間の話をするなら、日本語ラップの前にあったのは「人殺し 銀行強盗 チンピラたち(中略)/誰の胸にも 少年の詩は」といった叫びだった。THE BLUE HEARTSは善と悪の間で揺れ動く“青い心”を持つ不良少年たちのサウンドトラックであり、もっというなら彼らは映画『仁義なき戦い』で描かれたブラック・マーケットのやるせない生や、深沢七郎が描いた『東京のプリンスたち』の子孫たちでもある。その場所にDJとMCがやってきたのは偶然ではない。
日本を代表するラッパーZeebraのライブDJでもあるDJ CELORYが言う通り「起きてから寝るまでヒップホップ・ミュージックのことを考えていた。知らないラップ・ミュージックを聴きたいし覚えたい、そういう追求したい衝動に駆られていた」子供たちが日本語ラップを始めた。
それがいつどのように始まったのか、ここに既に書いたように幾つもの伏線があるけれど、そのうちのひとつは坂本龍一、高橋幸宏、細野晴臣の3人がYellow Magic Orchestraというグループで「Firecracker」という曲をカヴァーした瞬間だ。
註1:エメ・セゼール『植民地論』(平凡社/1997年)
註2:THE BLUE HEARTS「ブルーハーツのテーマ」(1987年)
■荏開津広
執筆/DJ/京都精華大学、立教大学非常勤講師。ポンピドゥー・センター発の映像祭オールピスト京都プログラム・ディレクター。90年代初頭より東京の黎明期のクラブ、P.PICASSO、ZOO、MIX、YELLOW、INKSTICKなどでレジデントDJを、以後主にストリート・カルチャーの領域において国内外で活動。共訳書に『サウンド・アート』(フィルムアート社、2010年)。
『東京/ブロンクス/HIPHOP』連載
・第1回:ロックの終わりとラップの始まり
・第2回:Bボーイとポスト・パンクの接点
・第3回:YMOとアフリカ・バンバータの共振
・第4回:NYと東京、ストリートカルチャーの共通点
・第5回:“踊り場”がダンス・ミュージックに与えた影響
・第6回:はっぴいえんど、闘争から辿るヒップホップ史