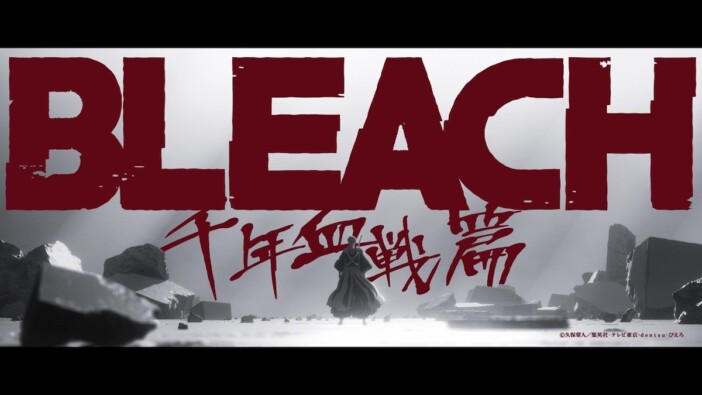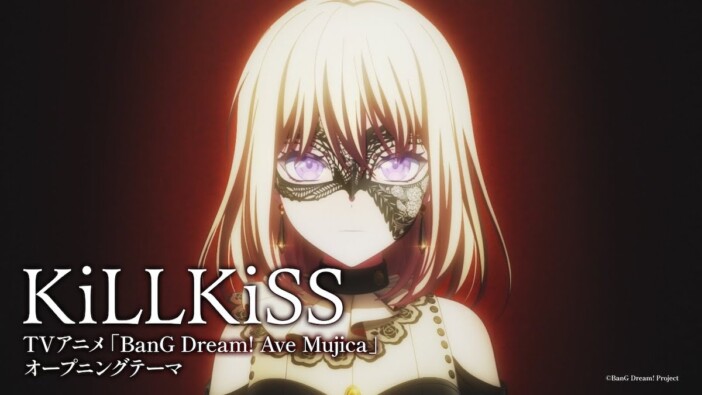magicHourに初インタビュー “サイバーパンク的な空想力”から生み出す新しい音楽とポピュラーカルチャー

20代のシンガーソングライター/音楽プロデューサー/サウンドエンジニアであるmagicHourが、1stアルバム『MAGICHOUR』を完成させた。ビルボードNo.1ヒットからジャズスタンダードまで長年に渡り支持されてきた良質なサウンド、そしてサイバーパンク的な表現に影響を受けた彼が目指すのは、「モダンとトラディショナルを融合させた新しい音楽」だ。
今回リアルサウンドでは、アルバム収録曲「Sunday, Monday」が映画『BLUE FIGHT ~蒼き若者たちのブレイキングダウン~』の劇中歌に起用されるなど活動の幅を広げつつあるmagicHourに初インタビュー。作詞・作曲・編曲・ミキシング・マスタリングのすべてを手掛けるという楽曲制作の手法や生成AIを用いたMVなど『MAGICHOUR』についての話題はもちろん、創作のルーツや今後の展望についても語ってもらった。(編集部)
“機械好き”からのめり込んだDTMの世界
ーー“magicHour”というアーティスト名の由来について、特別な意味やきっかけがあれば教えてください。
magicHour:夕焼けが1日で一番綺麗な時間帯のことを"マジックアワー"と言うんですけど、僕の楽曲を聴いてくださった方が僕の音楽を聴いた時に「夕焼けが目に映る」とおっしゃってくれたのを聞いて「なるほどな」と思ったんです。僕自身もその時間帯がすごく好きなので、アーティスト名にしようと思いました。
ーーDTMで楽曲制作をされていますが、どのようなきっかけで興味を持ったのですか?
magicHour:DTMを始めたのは13歳の頃です。僕の姉がもともと歌手活動をしていて、そのお手伝いを始めたのがきっかけでした。小さい頃から機械いじりが好きで、物が壊れたら自分で直してみたり、パソコンをいじるのも好きだったり、DTM自体にも興味があったんです。それで自分にできることがないかなと思って、DTMを始めました。最初は当時姉が持っていたDAWを使っていたのですが、DAWをいじればいじるほど、できることがどんどん広がっていくのがすごく楽しくて、DTMにのめり込んでいった感じですね。
ーー作詞、作曲、プロデュース、レコーディングまで全て一人でこなされているとのことですが、いつもどのような制作プロセスで楽曲制作をされているのでしょうか?
magicHour:普段からインスピレーションが湧いた後に曲を作っています。例えば、街を歩いてる時にぱっと頭に浮かぶようなものもあれば、ピアノに向き合って弾いている中で出てくるメロディもあります。また、映画を観ている時に「このシーンにこんな音楽が流れたらいいんじゃないか」と思ったことがきっかけになってインスピレーションが湧くこともありますね。アイデアが出てこない時は、とりあえずフリーライティングというか、歌詞でもなんでも何かを書いてみることを大事にしています。
ーー楽曲制作の工程を全て1人でこなしている理由は、DTMから楽曲制作を始めたことが関係していますか?
magicHour:実は先ほどの姉の手伝いというのが、作曲よりも先にミキシングをするというところから始まっていて。楽曲制作において、よくミキシングが苦手だという人もいますが、僕はエンジニアリングが得意だったんです。そこから作曲だけでなく、ミキシングなども含む楽曲制作の全工程を自分1人でできるようになっていきました。ミキシングにしても、マスタリングにしても、使うソフトやプラグインの理解が深まれば深まるほど上手くできるようになるのは、そういったツールを使っていると自然と自分でもわかってくるんです。だから、楽曲制作は難しいものという感じではなく、感覚的には遊びの延長みたいなものではありましたね。
ーー楽曲制作において、どんな作業が一番好きですか?
magicHour:制作作業の最後に自分のアイデアが形になった曲を聴き、心の中で「これだ!」と思う瞬間が一番好きです。ただ、次の日に完成した曲を聴くと思っていたほどではないなと思うこともあります。そういう時はちょっとだけミックスのバランスを変えてみたり、ズレていると感じる部分を修正したりします。基本的には最初に自分の中からアウトプットしたものを大事にしたいので、大幅な修正ではなく、そこをキープした上で気になったところだけを修正するという感じですね。
ーー普段からノートパソコン1台で制作されているそうですが、使用しているDAWを教えてください。
magicHour:インストゥルメンタルを作る時はFL Studioを使っていますが、録音はCubaseを使うことが多いですね。例えば、僕が楽曲制作を始めた時点では、他のDAWには「VariAudio」というピッチ修正のプラグインが入っていませんでした。でも、Cubaseにはそういった機能が搭載されていたので、それが必要だったこともあってCubaseを使うことにしたのですが、それ以来録音ではCubaseを使い続けています。
ビルボードNo.1ヒットからジャズスタンダードまで…magicHourを形作る音楽
ーーマイケル・ジャクソン、Queen、ルイ・アームストロングといった海外アーティストから影響を受けているとのことですが、それぞれどのような影響を受けましたか?
magicHour:まず、マイケル・ジャクソンは、パフォーマーとしてすごくかっこいいアーティストだと思っています。また、そのプロデューサーとしてクインシー・ジョーンズがいるんですけど、この2人に関しては割と自分の感覚と近いというか。特にマイケル・ジャクソンのリズム感、それとクインシー・ジョーンズのアレンジのバランス感の良さがすごく好きで、そこに僕は共鳴するものがあります。そこから自分の楽曲制作のインスピレーションが湧くことが多いですね。ルイ・アームストロングに関しては、僕がジャズが好きだということも大きな理由ですが、彼が演奏した音楽はジャズスタンダードとして何十年間も愛されていて、今聴いてもメロディの良さを感じます。Queenに関しては、シンプルにパフォーマーとしてのかっこよさがありますよね。
ーーJ-POPやアジアのアーティストからの影響はありますか?
magicHour:父親がすごく好きだったので、小さい頃から山下達郎さんの音楽を家でずっと聴いていました。あとはORANGE RANGEが流行っていたので、おそらくそれもどこかで自分の音楽のインスピレーション源になってるのかなと思いますね。他には、ONE OK ROCKやAcid Black Cherryがすごく好きだったので、そのあたりの音楽からも何かしらの影響を受けていると思います。
ーーマックス・マーティンやアーヴィング・バーリンからも影響を受けているとのことですが。
magicHour:まず、マックス・マーティンに関しては、2000年代~2010年代にかけて、多くのビルボードのNo.1ヒットを手掛けた実績を持つプロデューサーです。そういった楽曲の中にヒット曲を作るヒントがあるはずだと考え、どうやって彼が音楽を作っているのかをたくさん勉強しました。その結果わかったことが、”音楽を複雑に作らない"ということです。マックス・マーティンの音楽はすごく面白いんですけど、その一方でいろいろな人が理解できるというか、わかりやすさを大事にした音楽なんですよね。それにアリアナ・グランデからBackstreet Boys、ザ・ウィークエンドまで全然タイプの違うアーティストを手掛けていますが、それぞれの特徴をしっかり理解して、その人らしい曲を提供するのが上手いんです。一方、アーヴィング・バーリンはジャズスタンダードをたくさん手掛けてきたアーティストです。彼は戦時中にロシアからアメリカにやってきた移民なんですけど、そうした人生の中でもとにかく曲を書き続けて生活をしてきた人なので、その精神力をすごく尊敬しています。この2人に関しては、あまり深く考えすぎず、音楽としてみんなが共感できることを大事にする音楽家だと思っているのですが、その部分に影響を受けていますね。
人間の感情のぶつかり合いや葛藤はテクノロジーが発展しても消えることはない

ーー1stアルバム『MAGICHOUR』では、「都市のドラマと予期せぬ魅惑への招待状」というテーマを掲げていますが、アルバムのコンセプトはどのように生まれたのでしょうか?
magicHour:今回のアルバムのコンセプトの下地になっているのは、サイバーパンクの世界観です。どんなにテクノロジーが発展しても人間がその世界に存在するというのがサイバーパンクの世界なのですが、そこに注目しました。これからの社会では、AIの発展が予想されていますが、その中で一番大事になってくるのが人間性だと思うんです。もっといえば、人間の感情というか、いろいろな人が混じり合う中での感情のぶつかり合いや葛藤が、人間の中で一番美しいと僕は思っています。そして、それはこれから先、どんどんテクノロジーが発展していったとしてもいつまでも消えないものだと思うんですよね。どんなに未来的な世界になったとしても、そこは決して失われない。それを今回のアルバムのテーマにしました。
ーーアルバムにはストレートなラブソングからファンクポップ、シティポップまで多様なジャンルの楽曲が収録されていますが、『MAGICHOUR』の最大の魅力はどこにあると思いますか?
magicHour:『MAGICHOUR』は、いろいろなジャンルの音楽を収録しながらも、コンセプトとしてはさっきも言ったようにサイバーパンクを軸にしつつ、エレクトロな表現に乗せた人間ドラマを多方面から見ることができるようになっています。そのストーリーが最終的に行き着くところにアルバムの最後の曲「MAGIC HOUR」があるというイメージですね。誰か特定の1人に焦点を置いたものではなく、いろいろなシーンで別の人の視点からストーリーを描いているんですけど、どのシーンでも最終的に平和な結末に行き着くようストーリーラインをデザインしています。そこがこのアルバムの大きな魅力だと思いますね。
ーーアルバムには英語詞と日本語詞が混在する楽曲が多く収録されていますが、言語の選択はどのように決められたのですか? また、歌詞においてメッセージ性など特に大事にされているのはどのような部分でしょうか。
magicHour:それに関しては、日本語と英語を話すバイリンガルというか、日本人でありながらも海外で生活しているという僕のアイデンティティが関係しています。普段から自然に出てくる言葉がそもそも英語と日本語の両方なので、それが自然と歌詞作りにも反映されているという感じです。それと歌詞の内容に関しては、自分の意思を伝える、僕自身が新しいと思うことを伝えることを大事にしています。僕が今までSNSであまり発言をしてこなかったのも、音楽を通じて自分の意見を伝えたいという思いがあるからなんです。
ーーアルバム収録曲で特に思い入れのある曲や、制作時に印象的なエピソードがあれば教えてください。
magicHour:印象的な曲でいうとやっぱり「MAGIC HOUR」ですね。この曲はすごく粘って作った曲というか、いっぱいいろいろな曲を作った中で、このアルバムの最後の1ピースとして、何がハマるのかと考えながら作りました。結果的に曲が完成するまでの期間は短かったんですけど、いろいろな曲を試行錯誤した末に行き着いた答えのような曲なので思い入れもありますし、自分にとってもすごく好きな曲のひとつになりました。