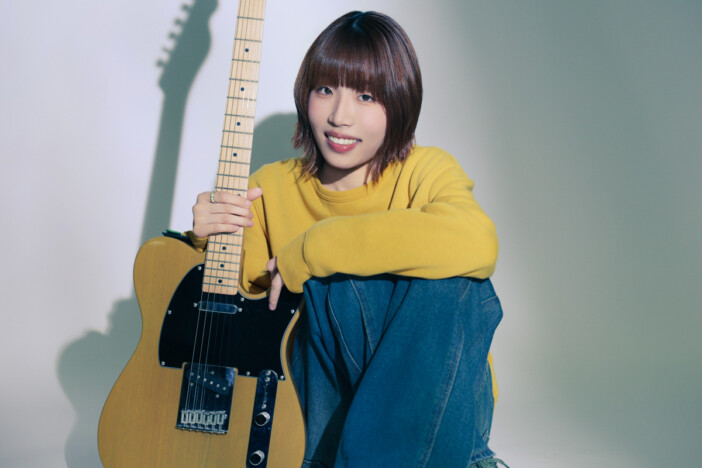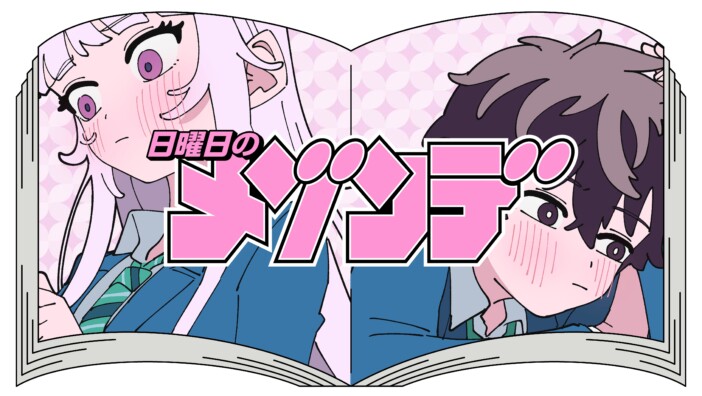『MUSIC AWARDS JAPAN』とSpotify Japanに共通する“2つのミッション” 野村達矢氏×トニー・エリソン氏対談

2025年3月13日、音楽関係者5,000人が投票に参加する国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN」(以下『MAJ』)の全62部門の詳細と、約3,000に及ぶエントリー作品が発表された。『MAJ』を主催するCEIPA(カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会)は、同賞をきっかけに、日本の音楽が国内だけでなく海外で聴かれるための認知拡大や、アーティストの海外進出の支援拡大を目指している。
これまで日本の音楽業界は、長年、国内市場に目を向けてきたが、『MAJ』は現代の世界基準である音楽サブスクリプションを意識した初めての音楽賞だ。日本の業界団体と音楽企業、そしてSpotifyなどのグローバルストリーミングサービス企業が連携して開催する初の取り組みであり、日本人アーティストの海外進出のさらなる推進や、音楽市場の拡大に期待が高まっている。
今回は、そんな『MAJ』の賞の中から「一般投票部門」にフォーカス。Spotifyユーザーの投票でベストソングが決定する2つの部門賞(ベスト・オブ・リスナーズチョイス:国内楽曲 powered by Spotify、ベスト・オブ・リスナーズチョイス:海外楽曲 powered by Spotify)、および主要6部門のひとつである「Top Global Hit From Japan」のノミネート作品選定の投票は、Spotify搭載の「投票機能」を活用して行われる。
リアルサウンドでは、CEIPAの理事として『MAJ』実行委員会 委員長を務めるヒップランドミュージックコーポレーション代表取締役社長、日本音楽制作者連盟理事長の野村達矢氏と、スポティファイジャパン代表取締役のトニー・エリソン氏にインタビュー。『MAJ』とSpotifyの投票における連携や、海外リスナーにおける日本の音楽に対する関心、日本の音楽業界が目指す世界進出について話を聞いた。(ジェイ・コウガミ)
『MAJ』一般投票部門にSpotifyの機能が使われた経緯

ーー今回、『MAJ』とSpotifyが音楽賞の一般投票で連携することとなった経緯を教えていただけますか?
野村達矢(以下、野村):まず、『MAJ』開催にあたり、かなり早い段階でお声がけいただいたのがSpotifyさんでした。Spotifyさんからは、ここ数年、海外で日本の音楽の再生が増え続けている話を何度も伺ってきましたし、Spotify Japanのトニーさんが度々、日本音楽の海外進出の支援について積極的に発言されている場面も拝見してきました。『MAJ』は、日本の音楽が世界で認知が広がり、一人でも多くの人に多様な邦楽を聴いてもらう、ストリーミング時代を意識した取り組みの一つです。こうした背景もあり、グローバルサービスのSpotifyさんと連携して取り組んでいく話が進みました。
トニー・エリソン(以下、トニー):Spotify Japanのミッションは2つあります。一つ目は、日本国内の音楽需要を拡大させること。二つ目は日本音楽の海外輸出です。『MAJ』は、Spotifyのミッションと合致していると感じまして、参加を決めました。今回、グローバルプラットフォームの私たちに何ができるかを考えていた時、ちょうど昨年、Spotifyのグローバルチームが、「投票機能」という新しい機能を開発したばかりでした。この投票機能は、じつは2024年末に日本テレビの一般視聴者の方々が投票できる特番でもご利用いただきました。視聴者を巻き込んだ参加型番組の根幹となる機能を提供できたことで、私たちも手応えを感じていました。そこで、CEIPAのみなさんに、アワードで一般リスナーが参加できるカテゴリーを設けて、私たちの投票機能を使うのはいかがでしょうか、と提案させていただきました。
野村:『MAJ』の投票は、約5,000人以上のアーティストをはじめ、作詞作曲家やプロデューサーなどのクリエイター、音楽ビジネスに関わる様々な方によって行われます。ですが、私たちは当初より、アワードには一般の音楽リスナーの方々の参加が不可欠、と考えていました。リスナー参加型の方法を模索していた時、トニーさんからSpotifyの投票機能の話をいただきました。アワードでは、全62部門の投票カテゴリーを設けていますが、その中の2部門を、Spotifyの投票機能を使って一般リスナーが投票して決定する部門にしました。それが、Spotifyの全世界のリスナーに日本の音楽について投票してもらう「ベスト・オブ・リスナーズチョイス:国内楽曲powered by Spotify」と、日本以外のアーティストの楽曲に投票してもらう「ベスト・オブ・リスナーズチョイス:海外楽曲 powered by Spotify」の2部門です。さらに、主要6部門のひとつである「Top Global Hit From Japan」のノミネート作品の選定は、Spotifyの海外リスナーからの投票で行います。『MAJ』は「グローバル」と「ストリーミング」を意識した音楽賞です。ですので、Spotifyさんの投票機能は、海外のリスナーの参加を目指した私たちのニーズとすごく合致しました。投票機能以外でも、Spotifyさんとは相互連携していきます。エントリー作品やノミネート作品をプレイリストにして、誰でも聴けるようにしたり、SNSでも様々な情報を発信するなどして、日本の音楽への関心を国内外で高める取り組みをしていきます。
ーー一般リスナーや海外リスナーからの投票、大規模なオンライン投票システムなど、これまでの日本の音楽業界のクローズドな賞とは一線を画す取り組みが進んでいますが、『MAJ』のリスナーズチョイスの投票結果ではどんな反響を期待していますか?
野村:海外で聴かれる邦楽は、まだまだ発展途上にあると思っています。ですので、日本の音楽をどれだけ身近に感じてもらえるかが大事だと感じています。リスナーの方々からの投票で、アワードを一緒に作り上げていくことは、大きな意味があると思っています。今までの音楽賞と言えば、業界内で関係者が決めた投票結果を見るだけでした。『MAJ』では、リスナー自身が投票できることで、参加意識を持ってもらえると嬉しいですし、日本の音楽をポジティブに感じてもらいたいと期待しています。
トニー: 国内と国外参加者の投票結果の違いにも興味があります。過去には、海外ではアニメに関連した邦楽でないと成功しない、と言われてきましたが、それだけではありません。昨年だけでも、多彩で多様なジャンルの国内楽曲が、海外で受け入れられ始めました。海外のリスナーが、どんな国内楽曲に投票してくださるか、注目しています。
野村:本投票のほうには、アーティストに積極的に参加していただきたいですね。各カテゴリーで5票まで投票できます。1票は自分の作品や自分が関わった楽曲に投票してもらっても構いませんが、残りの4票は、自分以外のアーティストや作品にも投票していただけます。私たちは『MAJ』を、他のアーティストからの賞賛が見える機会にしたいと考えています。アーティスト同士がお互い賞賛し合える機会は、今までの日本の音楽業界にはほとんどありませんでした。このような場面が増えれば、今後の音楽活動に活かせますし、アーティストの価値も高まるはずです。より良い形で音楽の未来に繋がっていくことに期待したいです。
「サブスクリプションでの音楽利用」に価値を置くことの意味

ーー『MAJ』を起爆剤に、国内外で日本の音楽への関心を高めていく取り組みが求められていますが、音楽サブスクリプションを意識した業界共通の取り組みが、なぜ重要なのでしょうか。
野村:ストリーミング時代における音楽業界の共通の課題ですが、日本人アーティストや日本の音楽業界が売上を伸ばすには、再生数だけではなく、ストリーミングを有料で利用するサブスクリプション会員を増やさないと、収益も増えないのが現状です。CD時代は、各社が個々のアーティストの収益を伸ばすため、個別のプロモーションや施策を頑張ってきましたが、それだけでは今の時代、売上に結びにくいことは認識しています。ですので、SpotifyさんのようなDSP(デジタル・サービス・プラットフォーム)に課金する人を増やす、サブスクリションを伸ばすことをCEIPAでは意識し、ミッションの一つと捉えています。サブスクリション会員数が国内、世界で伸びなければ、日本の音楽業界や音楽市場も広がりません。今回のアワードでは、Spotifyのサブスクリプション利用者であるリスナーに投票してもらうことは、大きな意味があります。
トニー:投票プロセスの話に戻りますが、ここで注目していただきたいのは、有料サブスクリプションのSpotify Premiumユーザーは1日3票まで投票できることです。無料ユーザーは1日1票です。先ほど野村さんがおっしゃったとおり、サブスクリプションでの音楽利用に価値を置きたい、サブスクリプション利用を促したい、という私たちの強い想いに加えて、業界共通の課題を少しでも変えたいと考えました。そのため、投票方法もPremiumユーザーと無料ユーザーで変えています。
ーー『MAJ』では、投票ルール開示を含めて、「透明性の確保」がアワードのテーマの一つとして掲げられています。
野村:これは音楽業界に限った話ではないと思っています。時代が変わっていく中で、倫理観にも変化が求められています。その中で、透明性の確保は重要です。今までの日本で開催されてきた音楽賞は、長年続けていると、密室政治と言われても仕方がないようなやり方が世間から指摘されてきました。リスナーや業界を見守る方々の期待を裏切ってしまうこともなかったと言い切れません。そのため、『MAJ』では、投票から透明性を担保することを重要視してきました。投票方法やルールの情報開示などは当然ですが、リスナーや一般の方々からの信頼と支持を集めるアワードとして定着させたいと考えています。
ーーSpotifyは、アメリカの『グラミー賞』やイギリスの『ブリット・アワード』など、世界中の音楽賞でパートナーを長年務めています。Spotifyでは、音楽賞に対して、どのような向き合い方があるのでしょうか。
トニー:Spotifyでは、どの国の音楽賞であっても、その価値と重要性は理解しています。音楽賞の主役はアーティストです。その中で、Spotifyの役割は、様々な形式でファンの熱量を可視化し、音楽を応援することです。始まったばかりの『MAJ』を他の国の音楽賞と比較することはできませんし、音楽賞の考え方や位置付けも日本と海外では大きく異なります。ただ、どの音楽賞においても私たちが意識しているのは、ファンの参加を促し、業界と連携して音楽への注目を高めることをフルサポートすることです。それは『MAJ』でも変わりません。アワードを盛り上げるために、Spotify社内でも、グローバルチーム同士で連携を取り合ってコラボレーションしています。