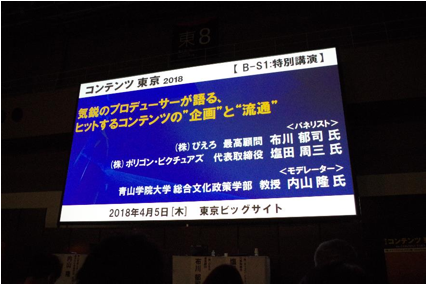新しい朝ドラの予感!? 永野芽郁×北川悦吏子『半分、青い。』未知数の面白さ

なんて彩り豊かな世界だろう。4月2日よりスタートした連続テレビ小説『半分、青い。』(NHK総合)を観て、そんな衝撃を覚えた。
ヒロイン・楡野鈴愛(永野芽郁)は、小学生のときに左耳を失聴するも、失敗を恐れずユニークでポジティブな発想を持つ女の子。第1週「生まれたい!」は、授業が終わり学校を出ようとする鈴愛のシーンから始まる。外は雨。傘を持っていない鈴愛が雨が止むのを待とうかと困っているところに、幼なじみの萩尾律(佐藤健)が「ほい」と傘を渡し、自分はカバンを頭に乗っけて去っていく。

受骨が折れたビニール傘を、不恰好と思うか、変な形でちょっと面白いと捉えるかはその人次第だ。半分、青い。それは、鈴愛の生きている世界そのもの。左耳の聞こえない彼女は、左側に降る雨の音は聞こえなく、右側だけに雨が降っている。これを鈴愛は、悲観的に思わず、ちょっと面白いと感じ取る。タイトルバックが流れるまでの1分50秒の中には『半分、青い。』の世界観とメッセージ、鈴愛と律の関係性とこれからを想像させる余白が詰まっているように思えた。
朝ドラ98作目となる『半分、青い。』は、その斬新かつユーモアな作品性から、“朝ドラっぽくない”という声が挙がっている。それをネガティブな意見に思うか、先鋭的と捉えるかは自由だが、第1週において、これまでに全く類のない演出が、鈴愛と律による“胎児ナレーション”だろう。

第1週で描かれるのは、1970年から1980年までの、鈴愛がまだ胎児の頃から小学校3年生まで。ふくろう商店街の岡田医院で同じ日に生まれ落ちた鈴愛と律は、同じ時間軸にて物語が進行していくが、視点は楡野家と萩尾家で、シーンによって異なってくる。

胎児の頃の自分を青年になった鈴愛と律がナレーションをするという形で物語は進んでいく。「お母さんの顔見たいです! 私、私生まれたい!」「あっ、私、お腹の中の赤ちゃんです。名前はまだない」「マジですか? という言い方はまだこの時代にはしませんね」。夏目漱石著『吾輩は猫である』の一節を引用する鈴愛のナレーションはまだ生まれていないにも関わらず、マイペースな彼女のキャラクターが伝わってくる異彩を放っている。

対して、律は「何、この猿」「まだ名前もないときに、僕たちは出会った」「こんにちは、おじいちゃん」と冷静かつ上品なナレーション。後に、萩尾家は由緒ある写真館を受け継ぐ、洋館に住む品格のある家族だということが分かるが、律の話し方からもそのイメージはすでに醸し出されている。1980年になり2人が幼少期になると、ナレーションは、他界する鈴愛の祖母・廉子(風吹ジュン)が家族たちを天から見守るという設定でバトンタッチとなる。「空から喋っております」「ピンピンコロリで逝きまして」と鈴愛の祖母らしいシュールな笑いを届けながら、当たり前にある“ふるさと”の大切さも聞かせる語り部として、鈴愛と律とはまた一味違った色を放っている。