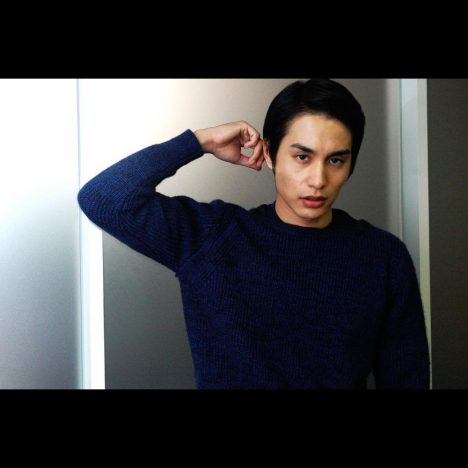本田翼と山本美月、“17歳の痛々しさ”をどう表現した? 『少女』の生々しい演技を考察

「私、見ちゃったんだ。親友の死体」。その一言は、17歳の少女を刺激するには充分すぎた。膨らむ“死”への好奇心。日常生活でよく耳にする“死”という言葉。“死”とは一体何なのか。少女だからこその“死”への異様な執着。映画『少女』は、剥き出しの傷を抉るようなおぞましさがある。
無邪気ゆえの残酷さ。17歳という大人でもなく子どもでもない、宙ぶらりんな“何か”。自意識という泥沼にハマり、もがけがもがくほど深く、深く、沈んでいく。尖りすぎた感受性が自分の首をジリジリと絞め、呼吸もままならない。終りが見えない“闇”の中で、一歩間違えばその先は“死”。まさに、17歳の少女たちは“夜の綱渡り”をしているのだ。

『少女』の桜井由紀(本田翼)と草野敦子(山本美月)を見ていて、私は妙な懐かしさを覚えた。本田翼と山本美月が“思春期特有の棘”を鮮烈に表現しているからだ。あの、敏感すぎるからこその痛々しさ。常に何かに怯え、震えている。だが、自我の強さゆえに、“ワタシ”が主人公であるストーリーを信じて疑わない。「みんな、“ワタシ”のために生きている」と言わんばかりの身勝手さ。多くの人たちが一度は通ってきた道ではないだろうか。だからこそ、目を背けたくなるほど痛々しい。
由紀は親友の敦子をいじめから助け出すことができずにいた。そんな中、由紀なりの手段を使って救おうとするのだが、思いがけない人物に踏みにじられる。その瞬間、由紀の中で何かが砕け散るのだ。17歳の少女を壊すには充分すぎる事件。芽生えた憎悪、怒り、屈辱…様々な負の感情が爆発し、ぐちゃぐちゃに混ざり合い、渦巻く。そして、元々彼女の心の片隅にあった“闇”をほじくり返すのだ。由紀の目には光がなく、どこまでも冷たい。“これが本田翼なのか?”と疑問に思うほど今までの彼女のイメージからかけ離れている。だからこそ、怖い。何をするのかわからない不安定さ。由紀は、その脆くて危ない雰囲気を全身から発している。
そんな由紀を見て“不安”を抱える敦子。表情がどんよりと薄暗く曇っている。ただでさえいじめにあっていて孤独なのだ。そんな中、幼い頃からの親友、由紀すらも失ってしまったら、想像しただけでゾッとする。「死にたい」と口にし、今にも消えてしまいそうな弱々しい敦子。そんな敦子の第一声を聞いたとき、あまりに繊細すぎる声にハッとした。山本の声と17歳の敦子の声がピッタリと合致したのだ。“声”を聞いただけで鳥肌が立つ。“声”とともに少女の恐怖、絶望が私の体内に流れ込んでくるようであった。
規律出しい女子高という特殊かつ閉塞な空間がすべてである少女たち。その世界から外に出ることはできない。だからこそ、おぞましい。たくさんの“嘘”により、コーティングされた世界。様々な“嘘”が知らない世界の“真実”を作り上げていく。リアルと虚構の間にあるようなどこか幻想的な映像は、“真実”と“嘘”が入り混じり境界が曖昧になっていることを象徴しているかのようだ。