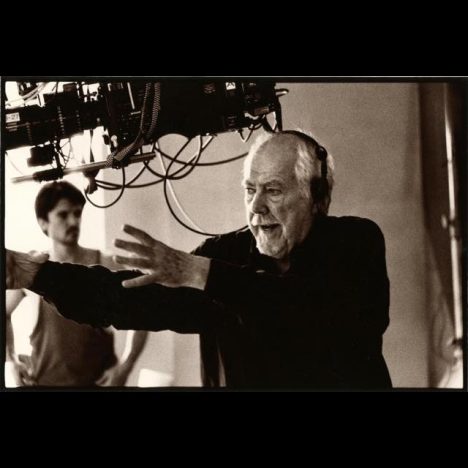『キングスマン』が切り拓いた“スパイ映画の新境地”とは? 荒唐無稽な作風の真価

『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』、『007 スペクター』、『コードネーム U.N.C.L.E.』、そして本作『キングスマン』など、これから公開される作品を含め、スパイ映画大作ラッシュが続く。そのなかで『キングスマン』は、シリーズやリメイク作として過去の実績がある他の大作と異なり、監督マシュー・ヴォーンの過去作『キック・アス』と同じく、マーク・ミラー作のコミックを原作としており、監督自身が原案にも関わる、実質的なオリジナル作品である。だが、その知名度の低さにも関わらず、世界各国で予想外の大ヒットを記録し、早くも次回作の製作が決定している。
マシュー・ヴォーン監督は、ユーモラスでありながら倫理観ギリギリのヴァイオレンス描写と、手堅い手腕の娯楽表現が魅力だが、本作『キングスマン』は、内容の面でも彼の過去作を大きく凌駕し、評価の高いサム・メンデス監督の新ボンド映画や、トム・クルーズの勝負作である『ミッション:インポッシブル』シリーズと同格として扱うべき、充実の作品に仕上がっている。
この面白さの理由は、劇中でも語られているように、かつての「007」シリーズに代表されるような、60年代のひたすら荒唐無稽なスパイ映画を良しとして、その魅力を再興させる娯楽描写に満ちているからだといえる。だが、本作のすごさは、むしろそれを同時にぶち壊してしまうような破壊的精神にこそある。今回は、スパイ映画の新境地を拓いた『キングスマン』の真価を追求していきたい。
驚きに満ちたスパイ映画の登場
ロンドン中心部に実在する紳士服店街、サヴィル・ロウ。ジェームズ・ボンドが「スーツならサヴィル・ロウで仕立てるのさ」と言うように、ここで高級スーツをオーダーメイドすることは、リッチで洗練された英国紳士の証だ。そのひとつの店舗の奥の部屋に、国家に属さない最強スパイ組織「キングスマン」の活動拠点があるというのが、本作の設定だ。この時点で、現実感を無視した作品であることは予想できる。
アーサー王伝説、円卓の騎士を模した組織キングスマンのトップに君臨するのがマイケル・ケイン演じる「アーサー」である。実際に騎士(ナイト)の称号を持つマイケル・ケインは、かつてスパイ映画「国際諜報員ハリー・パーマー」シリーズに主演したことで人気を得た名優だ。諜報員ハリー・パーマーのファースト・ネームと、トレードマークである大きな黒縁メガネは、本作の主役であるキングスマンのベテランスパイ、ハリー(コリン・ファース)に受け継がれている。
ハリーは、自分を救い殉職した仲間の息子である、荒んだ家庭環境から、道を踏み外してしまった不良青年エグジー(タロン・エガートン)の成長を遠くから見守っていた。伝説にのっとって、キングスマンのスパイ達には円卓の騎士の名と席が与えられる。席に空きが出ると、新しい騎士がそこに座るのだ。キングスマン候補生を指導する教官(マーク・ストロング)のコードネームが「マーリン」なのは、騎士がその席に相応しいか判断できるのが魔術師マーリンのみであったからだ。ジェームズ・ボンドにそっくりでダンディーなスパイ「ランスロット」が殉職したことで、かつてそのコードネームを持っていた、エグジーの父親への恩を果たすべく、ハリーはエグジーへのスパイ教育を開始し、ランスロットの席を与えようとする。ちなみにコリン・ファースは、ちょうどブロードウェイ版「マイ・フェア・レディ」で、下町娘をレディに育てる教授を演じることが決定しており、劇中でそれが茶化されている。
本作にはマーク・ハミルが出演しているが、まさに彼がルーク・スカイウォーカーとして主演した『スター・ウォーズ』のような、使い古された成長物語に、中盤までは退屈に感じられる部分があるのは確かだ。しかし甘く見ていると、物語の雲行きは怪しくなっていき、マシュー・ヴォーン監督らしい悪趣味演出が、これまでにないスケールで炸裂し始め、エンターテイメント映画における倫理観を逸脱するような展開に突入していく。スパイ映画の常識を打ち崩す驚愕の展開の行方は、本作を観てもらうとして、ここからは、このような反逆的な作品を作った意図を探っていこう。
ボンド映画の歴史への挑戦
『キングスマン』は、数々のスパイ映画のパロディーに満ちている。『007 ロシアより愛をこめて』の毒ナイフが飛び出す靴、英国趣味を前面に押し出したTVドラマ「おしゃれマル秘探偵」の仕込み傘、「電撃フリント」シリーズのハイテク・ペンなど、古風なガジェットが現代的にアップデートされ登場し、ロジャー・ムーアがボンドを演じていた、最も荒唐無稽な時代のボンド映画を想起させる、パラシュート・アクションや大気圏外のミッション、秘密基地での銃撃戦などなど、それら娯楽活劇への好意にあふれている。
かつて、スタンバーグやヒッチコックなどの名匠によって、スパイ映画はスタイリッシュなサスペンス作品として撮られていた。そのヒッチコックが自ら『北北西に進路を取れ』によって、スパイ映画を大衆的な娯楽活劇として甦らせている。その楽しさを、さらに大衆的に振り切ったものにしようと企画されたのが、イアン・フレミングの大衆小説を原作とした英国映画、007シリーズだ。批評家からは俗悪で下らない作品だと酷評される反面、ボンドのキャラクターは観客から支持を受け、以後、映画史を代表する長寿シリーズとして、スパイ映画のみならず、世界中の娯楽作品に影響を与え、皮肉や気の利いた台詞を吐くハリウッドのアクション・ヒーローの祖ともなっている。
ジェームズ・ボンドは、学生時代にケンブリッジとオックスフォードで学び、スコッチやシャンパンの銘柄年代に精通し、洗練された高級スーツを着こなす。そして無類の女好きであり、殺しの許可証とワルサーを携行した、体制側の愛国的エリートである。反抗する女は、一発頬を引っぱたくか、熱いキスで黙らせる。貧しい物売りの子供を河へ叩き落したこともある。ボンドが大衆から支持されたのは、このような当時としても保守的な、反近代的ともいえる価値観が、ある種痛快なマッチョ志向に通じていたためでもあるだろう。その素朴なあこがれには、人種的な偏見や反フェミニズム的な思想が見え隠れしている。ボンドであれば、たとえ仔犬を銃で撃つことさえも容易にこなすだろう。
本作は、自分だけ生き残ろうとする、選ばれた一握りの富裕層達や、アメリカの白人至上主義のキリスト教会を悪として描く一方で、スパイ組織「キングスマン」そのものの、階級を重視する主義、ここでは、マイケル・ケインに演じさせているエリート的なスノビズム(貴族趣味の俗物根性)を断罪もしている。つまり社会の悪は、根っこではジェームズ・ボンドのエリート意識や蔑視的価値観ともつながっているというのである。
「ウォッカ・マティーニ。ステアせずシェイクで」と、ボンドがバーでキンキンに冷やしたカクテルを注文するときの台詞は、007のファンの多くに知られているが、『キングスマン』では、ハリーがエグジーに「正しい注文」をレクチャーし、「ジンをベースにステアで」と頼むという、007に対する挑発的な場面がある。マティーニを注文すること自体にはボンドへの尊敬が表れているが、これは、伝統を受け継ぎ、変えるものは変えていかなくてはならないというメッセージに聞こえる。かつて大衆映画だとバカにされた007シリーズが、ある種の格式と権威を感じさせる作品となったことへの反抗も含め、それら保守性を打破しようというのが、『キングスマン』の試みであろう。