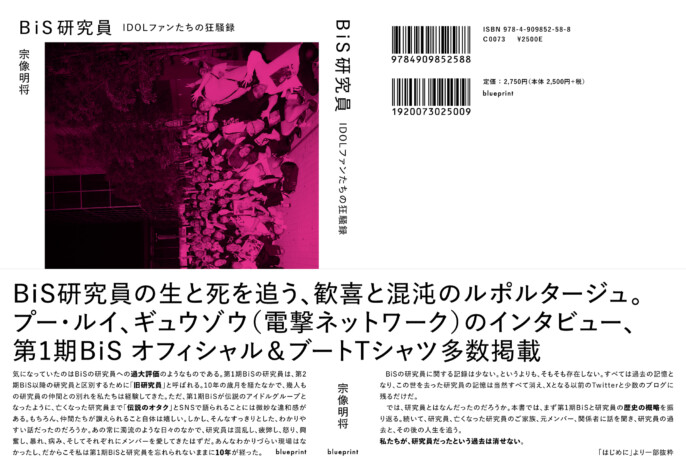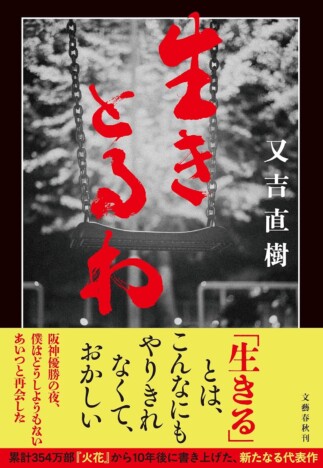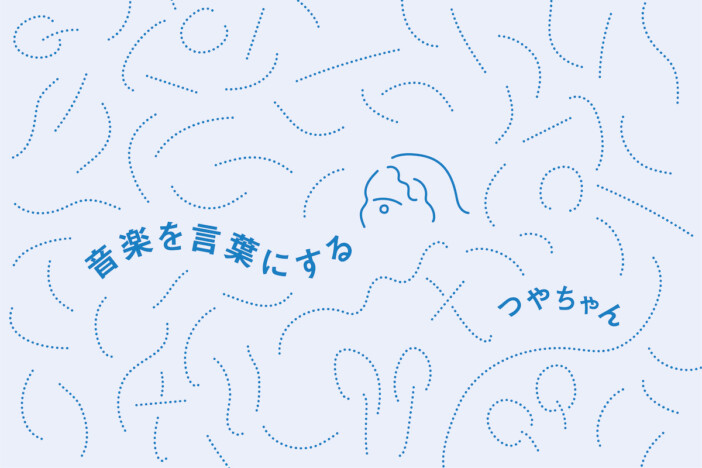【新連載】柳澤田実 ポップカルチャーと「聖なる価値」 第一回:孤独なポップスターの音楽に聖性は宿る
3.ポップスターの傷つきやすさ(Vulnerability)と供儀
内省的なアーティストが好む儀式的なライブ空間の実現のためには、巨大スクリーンの質の向上や、照明技術の進歩などテクノロジーも大きく関わっていそうだ。例えば近年のザ・ウィークエンドの神秘的なステージは、優れた映像技術なしにはあり得ないものばかりだ。2025年にリリースされるニューアルバム「Hurry Up Tomorrow」のお披露目として10月にブラジルのサンパウロで行われ、同時刻に生配信されたスタジアム・ライブには70000人以上が現地で参加していたそうだ。このサンパウロのコンサートではDJのANYMAがクリエイティブ・ディレクターを務めたそうだが、門が開き、神々しい光の中からザ・ウィークエンド(エイベル・テスファイ)が登場する冒頭から、バロックの騙し絵を思わせる凱旋門、雲、巨人、そして巨大な目へと展開する一曲目の「Wake Me Up」の映像は、圧巻だった。同時に感心させられるのは、このような巨大スペクタクルが、その前にたった一人立ち、歌うエイベル本人とのコントラストを強調するようにデザインされている点だ。真紅の光の中で黒いローブをまとい、巨大な像の前に屹立し、しばしば空を仰ぎながら歌う彼は、壮大な儀式の司祭のように見え、また捧げられる供犠(いけにえ)のようでもあった。
この投稿をInstagramで見る
巨大な空間に一人のアーティストが身一つで降り立つことで生じる儀式性は、最近通例化してきたリスニング・イベントにも感じられる。コンサートに比べカジュアルなリスニング・イベントでは、偶発的な要素が多く、アーティストはより生身の姿を露呈しているように見える。例えば今年数回開催されてたアルバム「Vulture 2」を聴くYeのイベントでは、彼の子供たちが突然呼ばれたり、ダンサーとの連携が取れないラフな瞬間も見られた。同じく今年ニューアルバム「ヒットミー・ハード・アンド・ソフト」のリリースに合わせ開催されたビリー・アイリッシュのリスニング・パーティでは、愛犬とビリーがスタジアムの中を走り回る場面もあった。またビリーのイベントでは、リビングルームのようなソファーセットをそのまま巨大なスタジアムに置くことで、意図的にコンサートとは全く違う空間を演出していた。非日常のなかに日常的空間が突如出現するそのセットは、本来手の届かない大スターが、ファンの前に無防備に現れるというネット空間の倒錯が再現されているようでクールだった。
Yeもビリーも敢えてチル(chill)な姿を見せてファンサービスをしているとも言えるのだが、その無防備さ、傷つきやすさの露呈によって独特な聖性が表出していることを指摘したい。彼らは、典型的なスターのビヨンセやマドンナのように激しいダンスを完璧に踊ったり、観客の前に支配者のように君臨するのではなく、ソファーに倒れ臥したり、スタジアムをランダムに走り回ったりする。トップアーティストの象徴の一つ、スーパーボールのハーフタイムショーにおいてさえ、エイベル(ザ・ウィークエンド)は、傷だらけの姿にこだわり、顔に包帯を巻いた分身たちと踊ってみせた。
孤独なポップスターたちは、「傷つきやすさ(Vulnerability)」を隠さず、むしろ自分は傷つき得る存在であることをオーディエンスやリスナーたちに呈示する。彼らは自分の心身の病や不調も隠さない。ビリーはトゥレット症候群や不安症を患っていることをインタビューで語り、エイベルもパニック発作や鬱についてインタビューで語っているが、自殺願望や希死念慮について歌うアーティストも少なくない。セレブリティであることの苦悩や代償について歌うことも珍しいことではなくなった。Yeは双極性障害を公表し、ここ数年は反ユダヤ主義をはじめ、多くの人を傷つける差別発言をすることもあった。それでも彼を観るために、未だに大勢のオーディエンスがスタジアムに集まる。その中には野次馬も含まれているだろうが、孤独で内省的なアーティストの音楽を体験しに集まる者たちは、無意識的にであれ「宗教的」とも言える領域に踏み込んでいると私は思う。彼らは、例えばYeが、最愛の母を失い、音楽業界、ファッション業界、世論などに次々に戦いを挑み、深く傷ついていることを理解し、だからこそYeとその音楽を愛し、崇拝している。彼の問題行動は一部のオーディエンスを遠ざけたかもしれないが、逆にカリスマ性を強化したことは否定できない。
この心理は単なる共感や同情以上に深い何かだ。宗教学や進化心理学の議論を前提にこの現象を見るならば、人々が、ポップスターを「犠牲」、言い換えれば供犠、生贄として神聖視していると解釈できる。多くの宗教が何らかの犠牲者を祀ることから興るように、この供犠の聖化は宗教を成り立たせる最も根源的な心理である。
4.ポップスターという現代の「キリスト(救世主)」
供犠とは、動物や食物など自分たちにとって大切なものを犠牲にして、神に捧げることだが、この儀式はかつて世界各地に存在していた。社会が階層化する過程で人身供犠を行っていた民族や国も少なくない(※5)。そのメカニズムについては諸説があるが、供犠が社会を安定させるために行われていたという点については多くの学者が同意している。人身供犠がある社会は、もしかしたら自分が犠牲になるのではないかという恐れによって統制される。こうしたことが遠い過去の出来事だと思えないのは、集団化して誰かを犠牲にするという振る舞いは、人間の社会から一向になくならないからだ。2020年代を生きる私たちにとって、その最も身近な例の一つはインターネット上の言説だろう。インターネット上の議論は被害・加害の単純な二項対立に陥りがちで、そこでは常に誰かが批判の矛先になったり、反対に犠牲者として祀りあげられたりしている。こうしたネット言論が現実の政治を動かすという事態が増えていることからもわかるように(※6)、私たちは変わらず供犠のある社会に生きている。
思想家のルネ・ジラール(※7)は、人間の集団は、集団内のストレスを解消するために誰かをスケープゴート(犠牲)にし、そのスケープゴートを聖化することで共同体を維持しようとすると論じた。人は誰かを犠牲にする暴力に加担しておきながら、犠牲になったスケープゴートの価値を反転させ、神聖視し始める。なぜなら彼らにとってスケープゴートとは、文字通り暴力を被るかもしれなかった自分の「身代わり」だからだ。こうした犠牲=スケープゴートの再生産を止めることができるのは、暴力の放棄と愛だけだとジラールは言う。彼にとって、愛の実践者の模範とはイエス・キリストだった。今日の社会にあって、孤独や痛みを身をもって示しながら愛を歌い続ける内省的なポップスターたちは、キリストに近い意味合いを引き受けているように私には見える。Yeが2016年にローリング・ストーンズ誌の表紙で見せ、ケンドリック・ラマーがアルバム「ミスター・モラル・アンド・ザ・ビッグ・ステッパーズ」のジャケ写や「N95」のPVで見せた、茨の冠を被ったキリストのコスプレは、今日のポップスターは必然的に集団の供犠だという自覚を示す、極めてわかりやすい表現だったと言えるだろう。
地球規模のパンデミックが起こり、世界の複数の場所で戦禍が広がっている2020年代、「傷つきやすさ」や孤独を、優れたポップソングへと昇華できるアーティストたちは、今日も世界中に暴力と痛みがあることを体現し、同時に、それでもなお愛が存在しうることを歌う。その姿に神聖さを感じ取るリスナーたちは、彼らに自分の「身代わり」を見出し、何らかの「救い」を得ている。アメリカでも特定の宗教に属さない者たちの多くが、音楽にスピリチュアリティを見出しているという調査結果がある。洗練されたポップスという現代的な形を取りつつ、「犠牲」を神聖視するという人類の古くからの心理に基づく「救い」に、インターネットを介して数百万、数千万の孤独な個人が与る。そのような時代に、あなたも私も生きている。
(※5)15世紀まで人身供犠を行っていたアステカ文明が有名だが、神をなだめるために人間を生贄にする儀式は、カナダ北極圏、中南米、オーストロネシア、アラビア、アフリカ、インド、中国、日本の歴史資料に記載がある。ダンバー、81頁。
(※6)被害者意識・被害者性(Victimhood)という言葉は、米国の言論では2010年前後から頻繁に見られるようになり、日本でもここ数年、頻繁に見られるようになっている。参考:柳澤田実「怒りは希望を生むのか」『Voice』10月号、PHP研究所、158-165頁。
(※7)ルネ・ジラール(1923~2015年)はフランス人の文学者・思想家であり、アメリカに渡り、スタンフォード大学等で教え、ピーター・ティールらリバタリアンにも大きな影響を与えた。