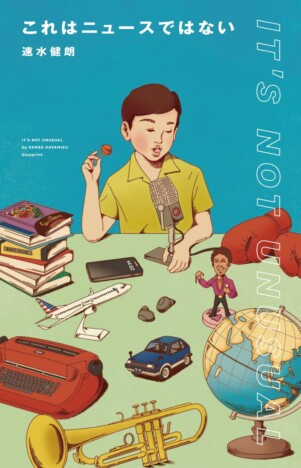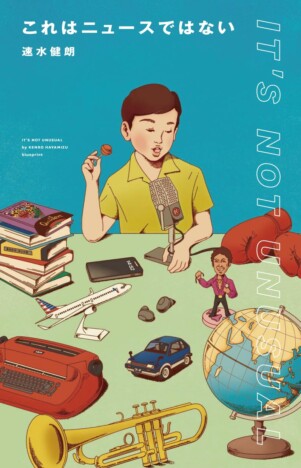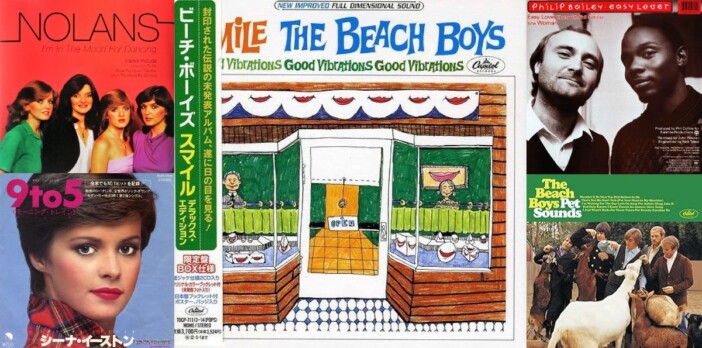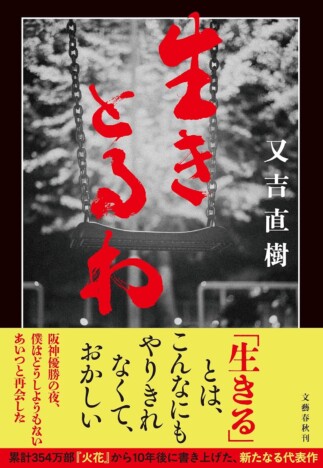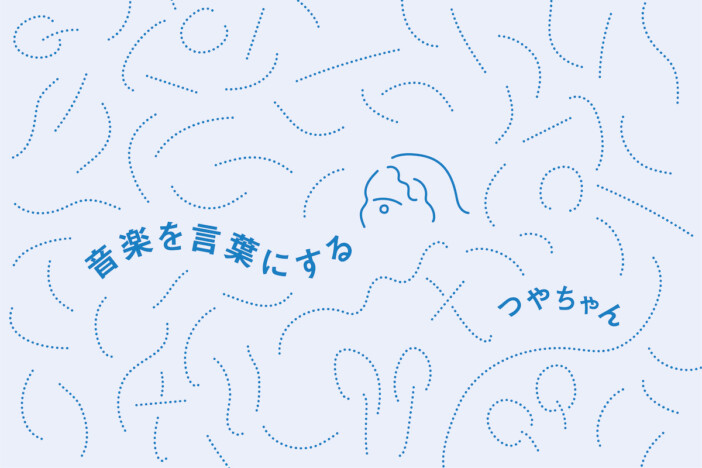【連載】速水健朗のこれはニュースではない:フェラーリとディズニーに学ぶ王国のつくり方

ライター・編集者の速水健朗が時事ネタ、本、映画、音楽について語る人気ポッドキャスト番組『速水健朗のこれはニュースではない』との連動企画として最新回の話題をコラムとしてお届け。
第11回は、王国と映画『フェラーリ』について。
書籍『これはニュースではない』刊行記念トークショー開催決定!
だけど王族は生きていて、ときおり表に出てくる
王国は、国民に追い出されて一度滅びた。制度としての王国の話。だけど王族は生きていて、ときおり表に出てくる。
6月末のテレビ討論会でバイデンのおじいちゃん化問題が前面に出てきた。最初に応援資金を取り下げると言い出したのは、アビゲイル・ディズニーなる人物。高額献金者の筆頭にディズニー創業一族がいて、ここぞというときに声を上げる。いや、もちろん滅びたとまでは思っていなかったが、まだ創業一族が強い影響力を持っていたのかと驚いた。
思い出したのは、日本の20年前のある事件だ。ホリエモンがフジテレビを買収しようとしたときに登場した鹿内家だ。フジサンケイグループの黎明期からいるオーナー一族。社内のクーデターで追放されていたが、このときに表に出てきて、誰もが驚いた。日本のメディア王的な話。
映画『フェラーリ』を見た。第二次世界大戦から12年経っている1957年だから、イタリアの高度成長期前夜の話。敗戦国イタリアの戦後の物語は、日本のそれと大して変わらない。どん底から輸出と内需によって経済成長を遂げる。もとより力のあった製造業が底力を見せた。1957年は、その復興から成長へという転換の時期だ。
登場人物は、創業者のエンツォとその妻ラウラと愛人リナ・ラルディ。中盤でそれぞれが別の席でオペラを見て涙を流すシーンがある。ラウラは、若くして死んだ息子と夫との日々を思い出して涙する。リナは、フェラーリの工場が戦火で亡くなって起ち上がろうとするエンツォとの出会いの頃を思い出している。そこから12年で色々変わってしまったのだ。
このシーンがうまいのは、登場人物たちの年齢を一気に把握できること。12年前にエンツォとラウラの息子は10歳程度(のちに20代で病死)。リナとの間にできた隠し子のピエロは、まだこれから生まれてくる。このオペラの回想シーンがなければ、この年齢関係がピンとこなかった。
この物語は、フェラーリの名は誰のものかを巡る物語。エンツォは、ピエロにフェラーリの名を託そうとするが、それが妻にばれて、一悶着が起きる。ただ男と女の対立を短絡化させているわけでも、女と女の対立をみにくいものとしても描いてない。登場人物全員に思惑と立場があり、ドラマが生まれている。
イタリアの国民的ブランドを継承する家族たちが「その名」を巡って分裂するところは、この映画が"ハウス・オブ・フェラーリ"であるということに通じている。主演のアダム・ドライバーが『ハウス・オブ・グッチ』に出演しているから、すぐに浮かぶ構図だ。
テレビと量産
イタリアの高度成長期前夜という時代と結びつく重要なキーワードが2つある。1つ目はテレビ、2つ目は量産。
車のレースがテレビでも中継されるようになり、スポンサーはレースの結果を重視するようになる。フェラーリは、そもそも王族や金持ちにしか車を売らない。だが時代の風は、テレビ=大衆時代に向かって吹いている。フェラーリにとってもテレビは無視できない存在だがなかなか受け入れ難い。
テレビは、家族の関係を示す映画的な道具としても使われている。妻と母の対立は、テレビを挟んだものとして描かれる。互いに相手がやって来たタイミングで興味がない顔をして、テレビをオフにする。あとから来た側は、それを無視してテレビをオンにする。テレビのスイッチで不満を示すのは、万国共通の家族の喧嘩マナーなのだ。テレビジョンエイジの喧嘩術。