小説編集者の仕事とはなにか? 京極夏彦や森博嗣のデビューを世に問うた編集者・唐木厚インタビュー

『小説編集者の仕事とはなにか?』(星海社)は、1990年より講談社ノベルスの編集を担当し、京極夏彦や森博嗣のデビュー、メフィスト賞の立ち上げに携わった唐木厚が、自らの経験や編集術を語った内容を構成したものである。主にかかわってきたミステリ小説について、編集という仕事について、彼はどのように考えてきたのだろうか。(円堂都司昭/5月29日取材・構成)
編集者は自らが編集企画を作り、それを当てることが仕事
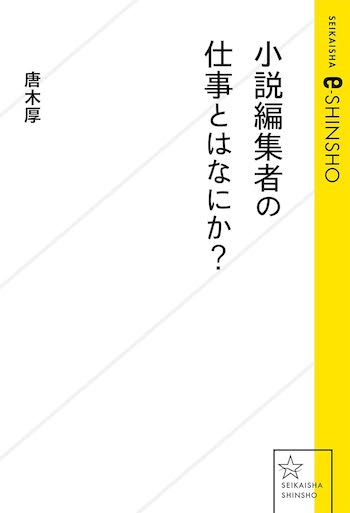
――唐木さんは1988年に講談社に入社されましたが、京都大学在学中はアイドル研究会に所属し、アイドル雑誌の編集者になりたくて出版社を目指したそうですね。アイドルのどんなところを研究していたんですか。
唐木:僕は、楽曲研究とかにはあまり興味がなくて、イベント会場にどんなタイプの人がきているかとか、ファンに関心があったんです。1980年代の終わりごろから握手会の現場がどんどん面白くなってきて、そんな状況に興味があった。年季の入った感じのファンの方に「いつぐらいからアイドル・ファンなんですか」などとインタビューしたこともあります。
――1990年より異動した文芸図書第三出版部(1987年発足の部署。通称・文三。改組を経て現在は文芸第三出版部)は、当時は講談社ノベルスを刊行する部署で(1994年に雑誌「メフィスト」創刊。2000年代以降は徐々にノベルスから単行本中心に移行)、1980年代末から綾辻行人、我孫子武丸、法月綸太郎など、京大推理小説研究会出身の作家たちを中心に新本格ミステリのムーブメントを巻き起こしていました。在学中に推理小説研究会と接点はあったんですか。
唐木:もちろん存在は知っていましたけど、所属しようというような気持ちはなかったですね。当時はミステリ・ファンではなかったんですよ。
――『小説編集者の仕事とはなにか?』では、編集者はプロデューサーの役割に近いと語られています。プロデューサーといった時に真っ先にイメージしているのは誰ですか。
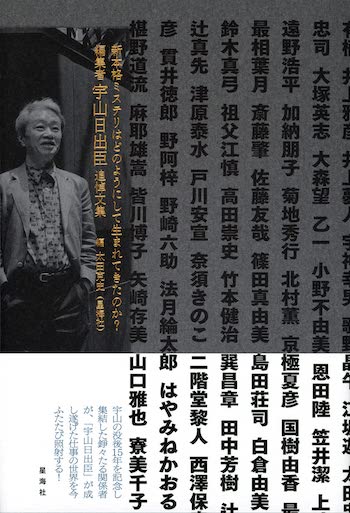
唐木:それはもう即答できます。音楽や映画のプロデューサーではなく、新間寿さんです。新日本プロレスの営業本部長を務められ、アントニオ猪木対モハメド・アリ戦を実現させた方です。新間さんのプロデュースの要は、そこで必ずなにかが起こる、そこを見ていなきゃいけないという気持ちにさせる場所作りです。そういうわくわくさせる感じを作りあげた点で、新間さんと、文三の先輩で新本格ミステリの仕掛け人といわれた宇山日出臣さんは似ていると思います(宇山の業績や人柄については太田克史編『新本格ミステリはどのように生まれてきたのか? 編集者宇山日出臣追悼文集』星海社刊に詳しい)。
――なるほど。猪木・アリ戦のように異種格闘技戦は、ルールをどうするんだとなるし、プロレスや格闘技は流儀の違いで分裂抗争も発生する。そのへんは、定義や流儀の違いで論争が起きがちな本格ミステリ界隈に近い気がします。
唐木:僕は、新間イズムと宇山イズムは通ずるところがあるととらえているので、そのあたりはつながっているかもしれませんね。
――文三ではミステリを多く担当されましたが、異動した頃に勢いのあった新本格ミステリは、旧来のミステリ界からバッシングされたとよくいわれます。それは編集者として感じていましたか。
唐木:まあ、そういった話は、自然と編集部にも伝わってきていました。
――新本格ミステリ、1995年から募集を始めたメフィスト賞の受賞作の一部などは、ミステリの作家、評論家、ファンの間でしばしば賛否両論が沸き起こり、それでも文三は我が道を行く姿勢を崩さず、打たれ強い印象があったんですが……。
唐木:べつに打たれ強くはないですよ(笑)。みんな、好き好んで打たれたくはない。ただ、当時は新しい才能を生み出すんだという気持ちしかなかったんです。先ほど申したように、なにかが常に起きている場所だとイメージしてもらわなければいけない。本格ミステリのファンの方に、この場を見ておかなければと思っていただきたいので、とにかく次から次へ新しい才能を見つけ、送り出そうとしました。
それから、宇山さんは、「異形の才能」が好きでした。教科書的によくできた作品より、欠点はあるけど飛びぬけたところがある作品が好きだった。そうなると賛否両論はしかたがない。でも、宇山さんは気にしなかったですね。前しか向いていない感じの部長だったので。
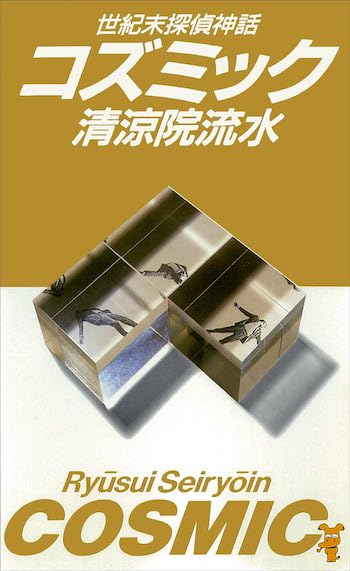
――なかでも話題になったのが、第2回メフィスト賞を受賞した清涼院流水『コズミック 世紀末探偵神話』(1996年)。今回の本でも触れられていますが、唐木さんは応募原稿を読んだ時、必ずしも肯定的ではなかったそうですね。
唐木:『コズミック』はもっとべつの解決の形がありうるのになぜそこへ行かなかったのかと、僕は勝手に考えて、不満に思っていました。でも、流水さんが後の世代に与えた影響は大きいし、自分にはその才能が見えていなかった。そうした自身の目の至らなさについては、この本の中でも明言しております。
――作家や評論家ではなく、編集部で選ぶメフィスト賞は、たとえ部員同士で評価が分かれても賞を与え、何度もヒット作を生んできている。
唐木:宇山さんは合議制が嫌いだったんです。合議制にしちゃうと尖った部分がなくなるから、1人の編集者が本にしたいと思い、部長を説得できたら世に出すシステムにした。
――同じく講談社から受賞作が刊行される江戸川乱歩賞では、私も過去に下読みをやりましたが、同賞は書評家たちの予選と、作家たちの最終選考で二回、合議を経る。合議だとどうしても欠点を指摘しあうことになりがちだし、だいぶ違うでしょうね。
唐木:僕は必ずしも宇山さんほど合議制に否定的ではありませんでした。作家や評論家でないと見られない視点が確実にあるし、編集者とは違う見方をするでしょう。議論の中で見出される才能もある。いろいろな形があればいいと、これは心から思っています。
――ほかの賞で興味を持っていたものはありますか。
唐木:僕がメフィスト賞にかかわっていた時期とはズレますが、システムが独特なものが、やはり気になります。その意味で『このミステリーがすごい!』大賞ですね。メフィスト賞が編集者だけで選ぶのに対し、このミス大賞は評論家が選ぶ。あってしかるべき形の賞が出てきたなと思いました。
編集者は自らが編集企画を作り、それを当てることが仕事なんです。編集者が選ぶうえで大きなポイントは、その作品は当たるのかということ。これは作家や評論家とは違う視点だと思います。編集者も自分なりの小説理論や文学観を持っていますが、それをあまり言語化しない。
それよりも、まず自身の考えを編集企画に結実させ、実際に雑誌や本の形にしてヒットさせる。形にして成果を出すところにどうしても頭が行く。今回はたまたま書籍化の機会があったから、自分の頭を整理して理論めいたことをまとめたりもしたんですけど、編集現場にいる時は私もそういうことはしませんでした。評論家の方々は逆に、自身の文学観や小説理論を言語化するのが仕事なので、作品を選ぶうえでもそうした視点がダイレクトに反映されるのだろうと思うのです。






















