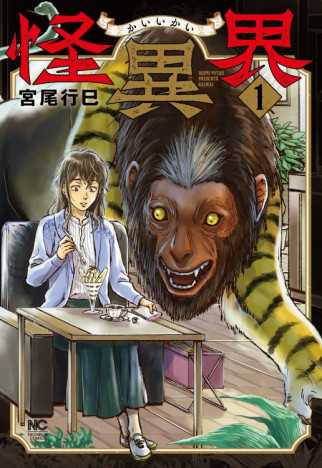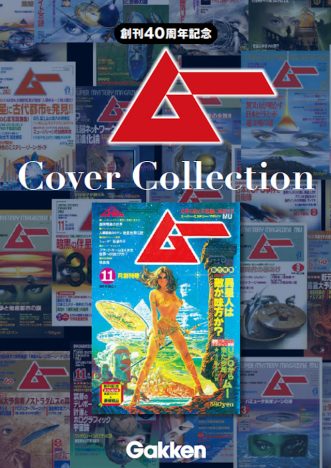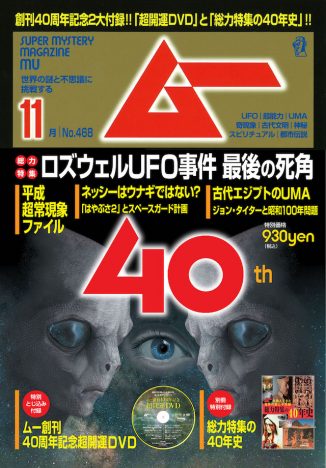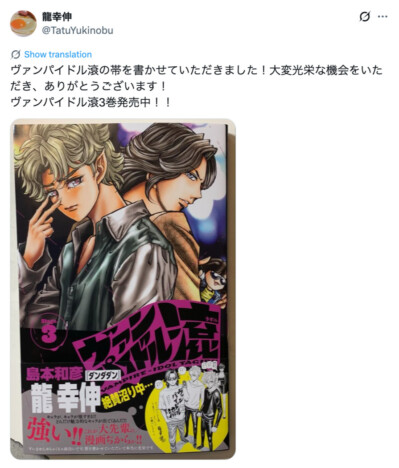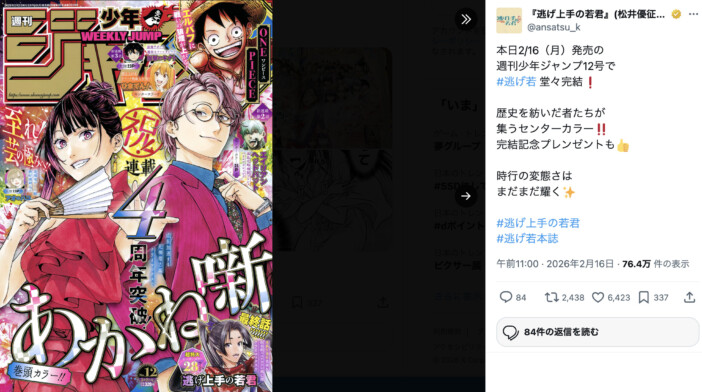ポップカルチャーと都市伝説の関係とは? 人気漫画『呪術廻戦』『虚構推理』……デフォルメされる怪異や怪物たち
■都市伝説とは何か?
都市伝説はアメリカの民俗学者、ジャン・ハロルド・ブルンヴァンによって広められた概念だ。
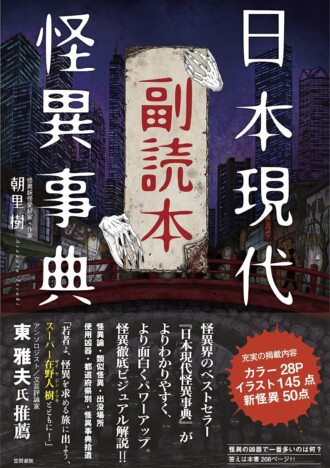
都市伝説(英: Urban legend)という名前の響きから想像のつく通り、伝統的な口承や神話ではなくもっと現代的なものである。在野の民俗学者としてとりわけ都市伝説で高名な朝里樹氏の『日本現代怪異辞典副読本』の年表をみると、主だった都市伝説の発祥はほぼ1970年代以降だ。有名なこっくりさんもカシマさんも口裂け女もムラサキカガミもケサランパセランも噂の発生が確認できるのは1970年代以降だ。
大辞林第二版によると「都市伝説」とは「口承される噂話のうち、現代発祥のもので、根拠が曖昧・不明であるもの」らしいが、実際のところその範囲は辞書の定義づけよりもかなり広く、「現代版の怪談、民話、伝承、神話、伝説など怪しげなもの全般」といった方が適切だろう。
都市伝説はポップカルチャーに題材として頻繁に登場する。現役作品であれば、現在アニメが放送中の『怪異と乙女と神隠し』、少年ジャンプ+の人気作で2024年10月よりアニメ化作品の放送が決定している『ダンダダン』、『虚構推理』、『裏世界ピクニック』などがその例にあたる。古典的なところであれば様々なメディアミックス展開がされている『学校の怪談』シリーズ、『地獄先生ぬ〜べ〜』シリーズなどが都市伝説を題材にした作品の典型例である。今回は都市伝説と都市伝説を扱ったポップカルチャーについて紹介していく。
■伝承の多い国・日本 古代から現代へ姿を変える怪異たち
物語は基本的に何もないところからは生まれない。極論すると、現代に存在する創作はすべて何かのパロディーやオマージュ、極端な言い方をするとパクりである。「映画100年の歴史は盗作の歴史」と、筆者がかつて参加していたシナリオ講座の講師が語っていたが、筆者にとって「人類の創作の歴史はほぼすべて盗作の歴史」である。
古来より日本には伝承、口承、伝説、神話の類が豊富に存在する。日本は世界最古の国家の一つであり、歴史が非常に深い。歴史が深ければ多くの物語が発生するのは必然である。えいとえふ/朝里樹(著)『日本怪異伝説事典』には北海道から沖縄までのすべての地域の怪異伝説が収録されているが、このような書籍が存在できるのはわが国のすべての地域に採録するに足るほどの伝説が存在することの証左である。田中康弘(著)『山怪: 山人が語る不思議な話』シリーズは著者の田中氏がマタギから聞いた山にまつわる怪異譚を集めたものだが、それだけジャンルを絞っても本が数冊書けるのだからすごい。
これほどまでに伝説の数が多いと、怪異の中には忘れられた存在も出てくる。
肥後の国(現在の熊本県)に伝わる疫病封じの妖怪・アマビエはその例である。2020年より始まった新型コロナウィルスに関する一連の騒動の際、ネット上でにわかに注目を集めたことから現代の都市伝説と思われている方もいらっしゃるかもしれないが、アマビエ伝説の記録は江戸時代後期のものである。アマビエは調査に現れた役人の前で「今後は豊作になるが病が流行るので、自分の絵姿を皆に広めよ」と語ったと記録されている。
古来の日本では疫病の原因は疫神や妖怪の仕業と考えられており、ほかにも絵姿を見たり貼ったりすれば厄除けとなる妖怪の伝説は複数存在する。江戸後期の伝説に登場するコレラを予言した佐賀の伝説「神社姫」、慈恵大師が鬼となって疫病を防ぐ滋賀の伝説「角大師」、加賀の白山に現れ疫病を防ぐ「ヨゲンノトリ」などがその例である。コロナ騒動ではこれらの中からアマビエが注目を集めることになったが、ほかの伝説が注目を浴びていた可能性もあったことだろう。
伝説はもともとあったものが形を変えることもある。「消える乗客」はその典型例である。都市伝説の有名な例だとタクシー幽霊がそれに相当する。墓場の前などで拾った客がいつの間にか消えており、座席がびっしょりと濡れているというパターンのアレである。現代都市伝説では、乗り物がバスだったり電車だったりするパターンもあるが、平安時代の伝承には馬に乗せたモノの正体が鬼だったとのものがあり、江戸時代には駕籠に乗せた客が幽霊だったの話が残っている。また、アメリカにはヒッチハイクで自動車に乗った客が実は幽霊で、乗車中に姿を消す「消えるヒッチハイカー」という都市伝説が存在する。やはり同じ人類、考えることは似てくるのだろう。