恩田陸「才能にはいろいろな発露の仕方がある」 渾身のバレエ小説『spring』が描く、新たな天才の姿
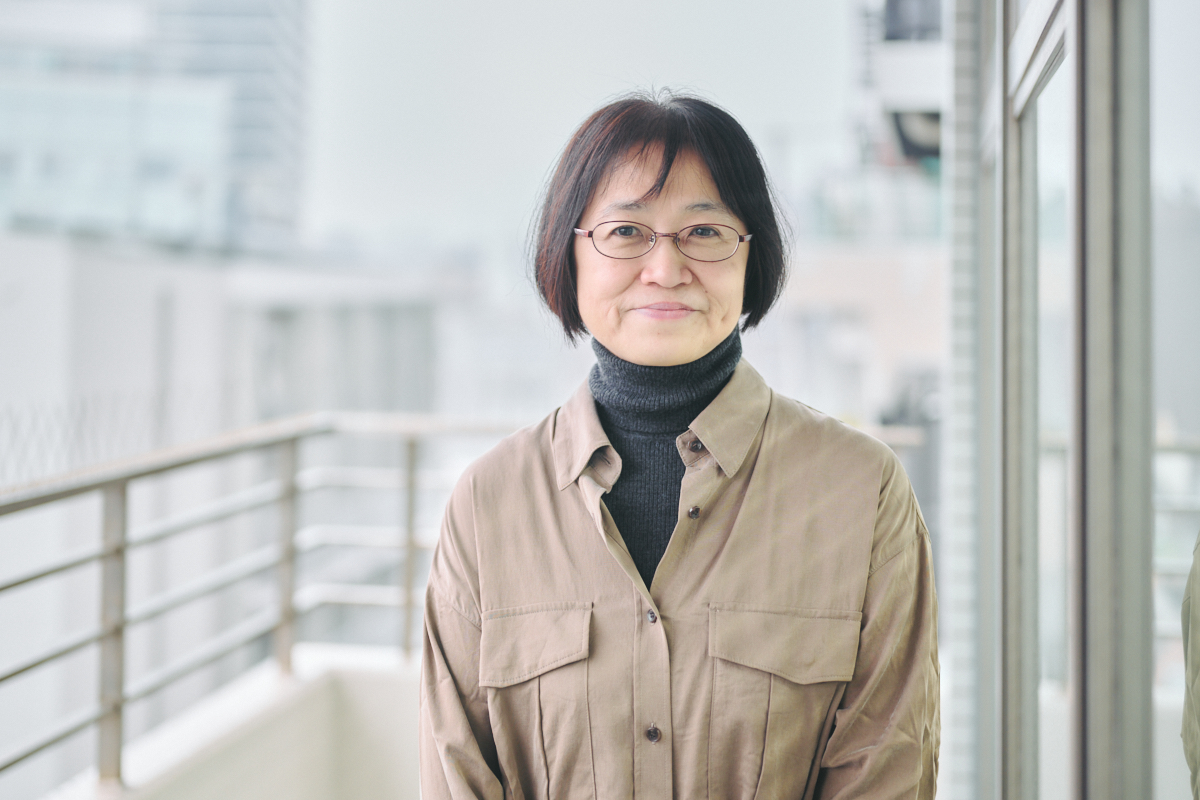
構想・執筆10年。恩田陸が筑摩書房から3月22日に刊行した『spring』は、無二の舞踊家であり革新的な振付家の萬春(よろず はる)を主人公にした著者渾身のバレエ小説だ。春の周りにいる親友のダンサーや作曲家、導き手となったバレエ教師に親しい家族といった人たちの目を通して、ひとりの天才の姿が浮かび上がらせる。読めば目の前にバレエの舞台が浮かんでくる『spring』の執筆経緯や読みどころを著者に聞いた。(タニグチリウイチ)
バレエ用語を使わずに情景が浮かぶように

恩田陸(以下、恩田):そう言っていただけると本当に嬉しいです。やっぱりそこが一番気になる部分ですから。
――踊っているところが目に浮かぶのは、ダンスの動きや振り付けなどの演出がしっかりと言葉で描写されているからだと思います。本来は目で見て耳で聞く芸術であるダンスを、言葉で書く際に気をつけたところや工夫したところはありますか。
恩田:いわゆるバレエ用語は使わずに書こうというのは決めていました。読者がみなバレエを知っている訳ではありません。そうした読者が読んで場面が想像できるようにするということをすごく考えました。バレエのポーズとか動きにはいろいろな名前がついているのですが、バレエ教師が指導する時もステージの様子を描写する時も、そうしたバレエ用語をなるべく使わずに、どうすれば情景が浮かぶかを考えました。
――書いていて難しかったところはありますか。
恩田:やっぱり最後の「春の祭典」(イーゴリ・ストラヴィンスキーが作曲した三大バレエのひとつとされる演目)をどのように書くかをものすごく考えましたし、いちばん苦労したところです。他にないものにしたかったんです。だからひたすら「春の祭典」のスコアを見て、頭の中でここはこう踊ってこういう場面にして……といったことを考えました。
――天才的な振付家の春が演出した舞台という設定ですから、それを創作する際の苦労も相当あったかと思います。人間の肉体がどれくらい動くのか、どのようなポーズやダンスなら可能なのかを考えるのは、バレエを観ていない人にはまるで見当がつきませんから。
恩田:そこは想像ですね。取材をし過ぎる逆に書けなくなってしまいますから。7割8割は取材して、あとは想像するくらいの案配が良いと思います。ただ反響は気になります。連載中から面白いと言ってくださっている方はいましたし、リアリティがあるとも言っていただけました。それで自信がつきましたが、刊行されたこれからが本番なので、今は結構ビクビクとしています(笑)。
――大丈夫ですよ。恩田先生は、芝居のオーディションに挑む人々を『チョコレートコスモス』(KADOKAWA)で描いて、ピアノのコンクールに臨む若者を『蜜蜂と遠雷』(幻冬舎)で描いてと、芸術を小説で発表することを続けてきました。『spring』でバレエに挑んだのも、そうした芸術への興味からですか。
恩田:お芝居を書いて次にピアノコンクールを書いたので、次は何だろう、さらにハードルを上げるとしたら踊りかなと思っていたところに、編集者からバレエの小説について書きませんかと言われたのがきっかけです。もともと大学でジャズバンドをやっていて、ミュージカルも見るようになり、それでバレエのコンテンポラリーのダンスを見るようになっていました。ただ、全幕のクラシックバレエを見るようになったのは『spring』を書くにあたって取材をし始めてからですね。
春=springに込めた想い

恩田:やはりクラシックを観ないと、バレエを全部理解できたことにならないのではないでしょうか。バレエについて書くならクラシックも観なければということで、しゃかりきになって観ました。クラシックが踊れない人はコンテンポラリーも踊れない、これがすべての基本になるということをすごく実感しました。ただ、観れば観るほど分からなくなる部分があって、なかなか書き始める踏ん切りが付かなかったんです。どうやって書けばいいんだろうということを、ひたすら考えていました。
――いよいよ書くとなった時、何か踏ん切りが付くようなことが起こったのですか。これなら書けるといった啓示のようなものが降りてきたとか……。
恩田:それはないです(笑)。理解したと思うところまで待っていたら、いつまで経っても書けないなと感じたので書き始めました。もう見切り発車ですね。
――それで書き始めたということですが、一口にバレエを書くといってもいろいろなフォーマットが想定できます。山岸凉子先生の『アラベスク』のように女性を主人公にする場合とか、萩尾望都先生の『ローマへの道』のように男性のダンサーが主人公のものとか。『spring』はどのように設定を決めていったのですか。
恩田:男性で、ダンサーだけれど振り付けもする人を主人公にするということ、最後にストラヴィンスキーの「春の祭典」を踊るというところまで決めていました。それだけしか決めてなかったとも言えますが。
――ストーリー上の展開は連載しながら考えていかれたということですね。4章構成にして、それぞれを異なる登場人物の視点から描くということも、書きながら決めていった感じですか。
恩田:「spring」というタイトルだけは決めていたんです。スプリングにはいろいろな意味がありますよね。春だけでなく泉だとかバネだとか。跳ねるといった動詞としての使い方もあって、そうしたスプリングが意味する動詞を各章の題にしようと決めていたんです。主人公の名前もspringだから春でいいかといった感じで決めました。
――4章にしたのは、春が四季のひとつだからという訳ではないんですね。確かに章題は「跳ねる」「芽吹く」「湧き出す」「春になる」とspringから読み取れる動詞になっています。
恩田:あとはやっぱり「春の祭典」からですね。バレエ小説を書くならタイトルはこれしかないというのはもう、ずっと思っていました。






















