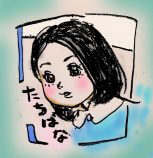前川ほまれ × 駒木結衣『藍色時刻の君たちは』対談 「被災地出身の自分にしか書けないこともあるのではないか」

駒木「地元のことを伝えていく姿勢を大事にしていきたい」

ーー本作は2011年に震災が起きるまでを描いた第一部と、2022年に大人になった三人が東京で再会する第二部とに分かれています。
前川:震災を経た今、当時はヤングケアラーだった子たちはどう成長したのかという姿を、変化した被災地の街並みと重ねて描いてみたくもありました。それに、資料を読んだりいろんな方にお話をうかがったりしていると、親のサポートを終えても悩み苦しんでいるケースはたくさんある。現状をどうにかするだけでなく、その後もふくめ、中長期的にサポートすることが必要なのだということも、物語にこめたかったことです。
駒木:震災「後」が描かれたことで、「忘れない」ことがすべてじゃないんだなということを痛感しました。たとえば凛子ちゃんは、一生懸命忘れようとすることでどうにか前を向くことができている。風化させたいんだ、って彼女の言葉に、ああそうか、と胸が衝かれる思いがしました。3.11の時期が近づくと「忘れない」という言葉が頻繁に使われるけれど、そのせいで痛みから抜け出せずにいる人もいるのだということも、ちゃんと心にとどめておかなくてはいけないのだ、と。でもそれは、前川さんが津波の現実を真正面から、しっかり描いてくださったからだとも思います。実際に人がどんなふうに飲み込まれていったのか、水を含んだご遺体がどんなふうに膨張したのか……。なかなか想像だけでは及ばないこと、なんとなく知ったような気になっていることを伝えてくれるから、簡単に「忘れるな」とは言えなくなってしまう。
前川:僕自身は、3.11のときは東京にいたので、当時の資料をかなり読み込んで書いたものなんです。当事者ではなかったからこそ、そのとき何が起きたのか、ちゃんと知りたいという思いもあって。
駒木:私も、震災当時は仙台市内にいて、津波を経験してはいないんです。だから石巻の友人たちとはどこか壁を感じてしまっている自分がいて……。自分だけが安全な場所にいた、まぬがれてしまった申し訳なさがぬぐいきれないんですよね。前川さんにも同じ思いがあるのかな、とあとがきを読んでも感じたのですが。
前川:ありますね。ぬぐいきれない、罪悪感はずっとありました。その瞬間、僕が被災地にいたところで何もできなかったと思うんですけど、それでも、東京で何をすることもできなかった自分に対する嫌悪というのは定期的に感じます。だからこそ震災を書くことに慎重になっていた……というか、書きたいという思いはありながら、どんなふうに書けばいいのかずっとわかりませんでした。ノンフィクションではなく小説で、ただのフックとして扱うのではなく、当時の人々の想いをちゃんと伝えるものにするにはどうしたらいいのか、って。
駒木:その想いに小説を通じて触れて、私も気が引き締まりました。仕事柄、地震や津波についてのニュースに触れる場面もあるんですが、いつも、こみあげる気持ちをぐっとこらえながら、淡々と伝えるようにしていたんです。でも、自分の罪悪感からも逃げないで、地元のことを伝えていく姿勢を大事にしていきたいなと思います。
前川:小説にも書いたことですが、痛みの向き合い方は人それぞれでいいと思うんです。当時を知りたい人は知ればいいし、語りたい人は語ればいい。ただ、防災の観点からいうと、駒木さんのような立場の方がニュースを通じて、折に触れて振り返ってくださるのは、重要なことなんじゃないかなと思います。
駒木:難しいですよね。凛子ちゃんのように、忘れなければ生きていけない人もいるけれど、本当に忘れてしまってはいけない。一方で、小羽ちゃんは、津波の直前で別れ別れになった青葉さんのことをずっと覚えて、探しているけれど、体験を身近な人に語ることはなかなかできなかったりするじゃないですか。私の父も、そうでした。先ほど話したとおり、当時の父は石巻の病院で働いていて、次々と運ばれてくるご遺体が廊下に積み重なっていくのを目の当たりにしているんですね。「本当に言葉では言い表せない」と言っただけで、それ以上は何も語ろうとしません。家族の間でも触れないまま、十年が経ちました。だけど小羽ちゃんが、同居の渚ちゃん(義理の妹)にぽろっとこぼすシーンを読んだとき、時間の経過によっていつか話せる時がくるのかもしれない。でもこなかったとしても、それはそれでいいのかもしれない、と思いました。
前川:難しいですよね。どうしても人は、自分の営みを続けていかなくてはならないし、そのためにメンタルのバランスを保つことも重要ですから。
前川「過去を乗り越えたとしても、大なり小なり悩みを抱えている」

駒木:航平くんは、わりとさらっと話すタイプの子でしたね。それも、意図的に書き分けたのでしょうか。
前川:はい。これもまた、いろんなかたちがあっていいと思いました。正解なんてないし、個人として向き合っていければそれでいいんだよ、ということを書きたくて。
駒木:再会した航平くんが、また違う過酷な状況に身を置かれていて、驚きました。でも、ひとつ辛いことを経験したらそれでおしまいってわけにはいかないのも、人生なんですよね。この小説には、LGBTについての描写もあって、震災とヤングケアラーにとどまらず、社会全体について考えさせられることも多かったです。
前川:セクシャルマイノリティを、特別なものとして描きたくなくて。カミングアウトの有無を踏まえても、きっとあなた達の周囲にいるよって感じで描きたかったんです。震災とヤングケアラーについての小説だから、それ以外の事象については描かないなんてこともないし、ふつうに存在して、ふつうに生きているなかで、結婚できないとか偏見にさらされるとか、生きづらさを抱えることがあるということを、並行して描きました。
ーーそれは最初におっしゃっていた、一面的にラベリングしない、という思いとも重なりますね。被災者だから、ヤングケアラーだからといって、画一的に存在している人なんて一人もいないのだと。
前川:そうですね。過去を乗り越えたとしても、今は今でみんな、それぞれ大なり小なり悩みを抱えている。それがあるからこそ、人の個性は生まれるのだと思います。
駒木:すごく印象に残っている場面があるんです。震災が起きた日の夜に、避難所で小羽ちゃんが「星、凄いね」とつぶやきますよね。あれはきっと、多くの人が感じたことなんじゃないかと思います。停電して、まっくらで、悲しみと絶望のなか、星だけが冷酷にも輝いている。あの光景は、仙台にいた私の目にも焼き付いていて、今でも忘れられません。石巻や女川、三陸では、星を見る余裕なんてなかった方々のほうが多かったとも思うのですが、それでも夜空を見上げて、星になった人たちの輝きにも重ねて、いろんなことを思ったんじゃないのかな……と。
前川:先ほども言ったとおり、僕は海沿いの町に住んでいて、小さいころからしょっちゅう海に行っていたんですけど、日没や夜明け、早朝のきれいに色づいている空が心象風景のように残っているんです。東京と宮城では空が違う、と青葉さんが言う場面もありますが、それは僕自身の実感としてもあって。主人公たちの「大人でも子供でもない年齢」と「日没でも日の出でもない空の色」を重ねて、タイトルは最初に『ブルーアワー』とつけていました。最終的には人生の時刻を重ねて『藍色時刻の君たちは』と。
駒木:この小説で描かれた、陽がのぼる直前の希望は多くの人たちの心を救ってくれると思います。読ませていただき、本当にありがとうございました。
■書籍情報
『藍色時刻の君たちは』
著者:前川ほまれ
判型:四六判仮フランス装
ページ数:350ページ
初版:2023年7月28日
装画:かない
装幀:アルビレオ
出版社:東京創元社