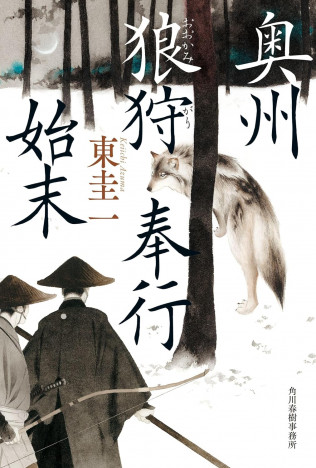書評家・豊崎由美が指摘する「物語」に隷属してしまう危険性 初の時評集『時事書評』を杉江松恋が読む

こうした時評の弱点は、題材に対する評者の論が優先順位では絶対のものになってしまい、その他が従属させられてしまいがちだということだと思う。豊崎の愛する文学が、時評のための従属物となってしまっては本末転倒なのだ。しかしそこははっきり自覚的で、豊崎は松田青子の短篇「物語」(『男の子になりたかった女の子になりたかった女の子』中央公論新社所収)を紹介して、自らの中にあるかもしれない、「物語」で誰か/何かを解釈してしまうかもしれない傾向について書く。
元になる松田の短篇では、物語と「物語」が区別されている。物語とは昔話や小説など、人を楽しませ、心を豊かにしてくれる古来から存在するそれのことだ。「物語」は「物語界のファストフード」で「すぐ手に入」り、技術革新によって拡散が容易になったばかりではなく、誰もがそこに参加できるようになった。そのため民衆は「『物語』を主食として喰らう怪物と化した」のだという。
この「物語」が何を指すかは明白だろう。豊崎は、誰もがこの「物語」に隷属してしまう危険性を指摘し、「『物語』を批判するときに他の『物語』を用いてしまっては、『物語』から逃れるどころか『物語』に呑み込まれることになりかねない」と書く。世界は「物語」に満ちていて、自分を縛る「物語」は自身のものではなく誰か/何かの「物語」になってしまっているかもしれないのである。
「昭和のがさつなおじさんにNO!を突きつける」の章では、「物語」への強い忌避感が表明されている。同時に気づくのは、豊崎がそうした「物語」と、本来の物語を厳密に分別して扱っていることだ。物語、すなわち文学の次元を「物語」のそれと混同することへの危惧が豊崎の中にはあるはずだ。文学は文学として現実と切り離して見ない限り、それが持つ本来の輝きを受け止めることはできない。それが本書を貫くもう一つの主題なのである。文学を自分に引き寄せず、自分を文学の側に近づけることで見えてくるものを見よ。そのための視座をどう持つべきかを、本書は教えてくれるはずだ。