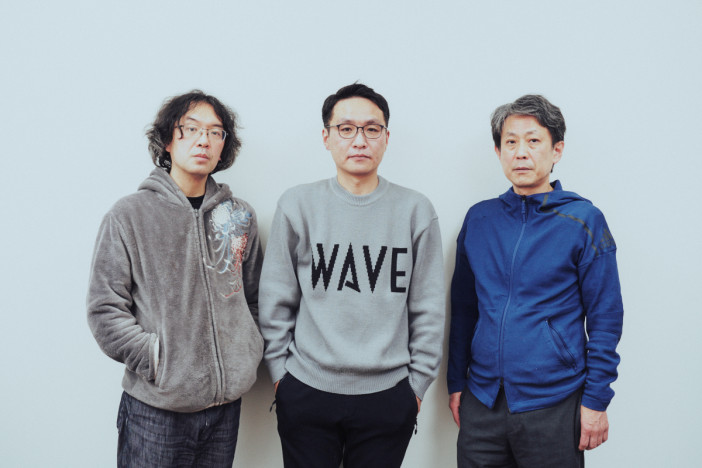朝ドラ『ブギウギ』笠置シヅ子とはどんな人物だったのか? 自伝から音楽史まで、関連書を読み解く

上田賢一『上海ブギウギ1945 服部良一の冒険』(アルテス)

そんなわけで笠置についての記述は少ないのだが、ドラマ『ブギウギ』では死角になっていると思われるもう一つの物語を知り、立体的に楽しむためには良い副読本になる。
生前の服部良一および服部一家をはじめとして関係者の証言が多数集められていて史料性も高いが、本書の独創は、日本の大衆音楽の発展に関して、オルタナティブな視点を提示したことにある。
米国の音楽であるジャズの影響を血肉化して日本の流行歌に敷衍し、モダンな作品を生み出した作曲家。服部良一の定評はおおむねそういったものだろう。ジャズからブルース、そしてブギウギへという展開は、米国ポピュラー音楽の受容とそのローカライズとして比較的単線的に解釈されてきた。
本書がフィーチャーする上海時代の服部は、その単線的な理解に揺さぶりをかける。服部流ブギウギ誕生の背景には、東洋、すなわち中国の音楽家らとの交流と影響があったことが示されるからだ。
1944年、陸軍に招集された服部は上海に送られた。恐る恐る趣くと、服部は自分に「特殊任務」が課されていると告げられる。それは「音楽を通じて日本陸軍、日本政府が地元の市民と融和を図ることを目的とした活動」だった。(p107)まるでドラマのような話である。服部は中国人音楽家らと親交を深め、その中に「夜来香」で知られる上海トップの作曲家・黎錦光もいた。
服部は、東洋最大のヒット曲と言われる「夜来香」を素材に、オリジナル歌手である李香蘭を迎え、ジャズ・シンフォニーに構成した音楽会『夜来香ラプソディ』を企画した。この音楽会は終戦間際の上海で大評判を取る。本書のハイライト・シーンだ。音楽会の締め括りに服部はブギウギを取り入れ、李香蘭に歌わせた。
日本大衆音楽を支えた二巨頭ながら、対照的な音楽性ゆえ水と油と思われている服部良一と古賀政男が、実は互いに尊敬し合い、親しく付き合う仲だったというのも意表を突く事実で面白い。服部は古賀を「天才」と評していたという。
輪島裕介『昭和ブギウギ 笠置シヅ子と服部良一のリズム音曲』(NHK出版新書)

戦後大衆音楽の歴史は、GHQ占領下の進駐軍キャンプを起点に語られてきた。米軍キャンプで演奏していたジャズメンから渡辺プロが生まれて…という具合だ。この史観には、戦前と戦後の日本大衆音楽には断絶があり不連続である、という認識が潜んでいる。
だがそれは違うんじゃないか、東京中心主義的で一面的な見方じゃないかと輪島は言う。輪島がドラマ『ブギウギ』に合わせて発表した『昭和ブギウギ 笠置シヅ子と服部良一のリズム音曲』(NHK出版新書)は、「大阪」の大衆芸能の歴史をひもとくことで、東京中心主義的大衆音楽史観に更新を迫ろう、ひいては明治に始まる西洋芸術音楽受容史としての日本音楽史に見直しを迫ろうという野心の下に書かれているという。
なんかでかい話である。著者本人も、読者からすれば「なんでこんな大それた野望の片棒を担がされるのか」と「なんのこっちゃだろう」(p16)と照れ隠しのセルフ突っ込みを入れている。もっとも「日本大衆音楽の戦前戦後の連続性」というのは最近わりかし言われることで、大谷能生との拙共著『ニッポンの音楽批評』(立東舎)もその認識を共有している。

宝塚歌劇を発祥とし、笠置のいた松竹歌劇など関西方面で発展したレビューでは、歌舞伎や日本舞踊など近世以来の日本の芸能と、ジャズやダンスなど西洋の文化とが雑然と同居する「和洋折衷」が進み、映画や寄席などとも連携して新しい上演形態を作り上げていった。
そうした土壌でキャリアを積んだ服部と笠置は、西洋芸術音楽を規範とし旧来の日本文化を上書きするように上から改革が進められた中央の「音楽」とは違う、日本の文脈に西洋文化を自在に取り込み下から発展した「音曲(おんぎょく)」の担い手として育ち、東京へ進出した。
輪島が示すのはそんな物語だ。「音曲」とは「開国以前から現在まで、寄席や芝居小屋や大道で日常的に演じられてきた娯楽的な歌や踊りや楽器演奏」(p15)であると定義されている。服部と笠置による一連の「ブギウギ」は、いわば「関西インヴェイジョン」として、東京ひいては全国を席巻したという見立てである。
輪島の本は論点が多いが、もう一つ注目したいのは、「服部良一のブギウギは果たしてブギウギなのか?」問題に回答を試みていることだ。上田賢一も『上海ブギウギ1945』で、服部の「別れのブルース」は今日知られるブルースではないが、だからと言って偽物ではない、という微妙な評価の仕方をしている。
今日の我々の耳には、どうもそれらしく響かないことも多い服部のブルースやブギウギだが、それは服部が、音楽の特徴をどこに見出していたか、音楽の「進化」をどのように考えていたかに関わっている問題なのだ。これもまた、日本人の西洋音楽の受容について興味深い視点を差し出しているように見える。
ということで、最後のほう、若干固くなってしまいましたが、ドラマ『ブギウギ』も早第3週に突入。楽しみに鑑賞していきましょう!