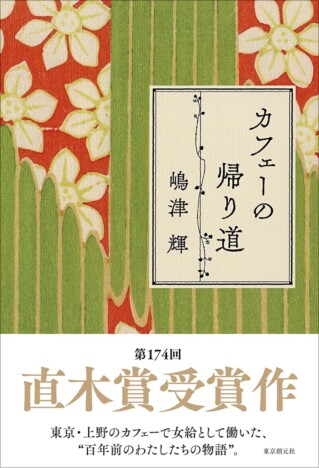早乙女太一×青崎有吾『ノッキンオン・ロックドドア』対談後編 同い年の二人が語り合う、倒理&氷雨に通じる“バディ”の存在

松村北斗(SixTONES)演じる【トリック=不可能】専門探偵・御殿場倒理と、西畑大吾(なにわ男子)扮する【動機や理由=不可解】専門探偵・片無氷雨は、得意分野も性格も真反対。誰よりもその腕を信じる相棒でもあり、一方で誰よりも負けたくないライバルでもあり……そんな一言では形容し難い2人がバディを組んで、難事件に挑み、大きな話題となったミステリードラマ『ノッキンオン・ロックドドア』(テレビ朝日系)。併せて気鋭のミステリー作家・青崎有吾による原作小説にも注目が集まっている状況だ。
同じ大学のゼミ仲間として出会った倒理と氷雨。そこには、女性刑事の穿地決(石橋静河)、そして犯罪コンサルタントとなった糸切美影(早乙女太一)もいた。学生時代には仲の良かった4人。だが、ある事件をきっかけに犯罪を暴く者、犯罪を捕らえる者、そして犯罪を作る者へと道が分かれてしまったのだった。彼らに一体何が起こったのか。美影が氷雨に告げた「君は相変わらず、倒理に殺されたがってるね」の意味とはーー。
そんな先の読めない本作を生み出した青崎有吾と、物語の重要人物・美影を演じた早乙女太一による対談。二人にとってのバディ的存在にアクション愛、同い年ならではの“あるある”で大いに盛り上がった後編をお届けする。(佐藤結衣)
※前編はこちらから
早乙女太一×青崎有吾『ノッキンオン・ロックドドア』対談前編 魅惑のキャラクター“糸切美影”はいかにして生まれたのか
【記事の最後に、早乙女太一さんのサイン入りチェキプレゼントあり】
背中を任せられる弟と、背中を押してくれる同世代の作家たち
――『ノキドア』の大きな魅力のひとつは、やはり倒理と氷雨の関係性にあると思います。一見ドライでありながら、深い信頼で結ばれたバディのような関係。お二人には、相棒でありライバルのような方はいますか?
早乙女:僕にとっては弟(※俳優の早乙女友貴。舞台をはじめ、早乙女太一と多くの仕事を共にしている)ですかね。普段は2人で出かけることもないし、飯に行くこともないし、もはや喋ることすらないんですけど(笑)。でも、子どものころからずっと一緒にやってきていて、それこそ役割分担がしっかりあるので。
青崎:弟さんの分野は、もう全部任せられるなみたいな気持ちでいますか?
早乙女:そうですね。僕が舞台の演出や構成を作るようになったので、そういったところで、より明確に分けていった感じはあります。なんて言うんでしょう、僕が先頭で思いっきり走ってるところを、弟がうしろから冷静に穴を埋めてくれるような感じというか。
青崎:なるほど、それはいい関係性ですね。僕はライバル的な存在でいうと、同世代の作家さんたちですかね。僕はデビューが大学3年生のときだったので、この業界では早めのスタートだったんですけど。あとからデビューした作家さんたちの熱量がすごくて。
例えば、斜線堂有紀さんとか、阿津川辰海さんとか。年に5〜6冊みたいなペースで新作を発表されたり、読書量もすごくて、尊敬していますし刺激を受けてます。ほかの同世代に置いていかれたくないな、というのが、ここ数年の仕事のモチベーションで一番比重が大きいかもしれないです。
――作家さん同士の交流はあるんですか?
青崎:家が近い方たちとはちょくちょく集まります。そもそもミステリー作家は人数も少ないし界隈がすごく狭いから。年齢が離れていてもデビューした時期が近いと「同期」みたいな感覚ですね。そういう意味では、俳優さんって「同期」の感覚ってなかなかないですよね?
早乙女:そうですね。また僕はちょっと特殊でして……。それこそデビューが4歳のころと、早かったので。あんまり同世代の方からも仲間には見られていないですね(笑)。なので、僕自身も他の人を意識したこともなくて。
青崎:そこもちょっと“美影感”がありますよね。我が道を行くというか。
早乙女:そこは大事にしたいなっていう部分でもありますね。自分ができることを、っていうのを。もちろん、刺激を受ける方はたくさんいらっしゃいますけれど。お芝居に関しては勝ち負けもないですし。たくさん出ているからといって羨ましいというものでもなくて。むしろ、僕はそんなに働きたくないから(笑)。
青崎:ああ、わかります。僕も小説は好きだけど、自分で働きたくはない(笑)。
――まさかの「働きたくない」という共通点が(笑)。ちなみにおふたりは、どんなふうに休日を過ごされているんですか?
早乙女:最近はサウナですね。身体的にもオフになりますし、ふだんよりも脳を使わなくていい瞬間があるので。
青崎:僕の周りでもサウナはブームです。でも、僕は生命の危機を感じて怖くて行けない……(笑)。僕自身は仕事場を家とは分けているので、そこがオンとオフの切り替えになっている感じです。仕事柄、本をたくさん読まないといけないんですけど、それも最近は喫茶店とかファミレスとか外でまとまった時間を取るようにしています。だから家に帰ったらYouTubeで毒にも薬にもならないような動画をずーっと流して。あとは天井をボーっと見つめてるときが一番長いかもしれないです。
早乙女:天井をボーっと(笑)。僕も家にいるときは何もしないので、近いですね。
楽しくも難しい、アクションの作り方
――せっかくの機会なので、お互いに聞きたかったことはありませんか?
早乙女:何を聞いていいかちょっとわかんないですけど。とりあえず、僕は作家さんに対して圧倒的に尊敬があるんですよ。原作小説『ノキドア』を読んでいても思ったことですが、やっぱり0から人物を作って、ストーリーを作るって、ものすごいことだなと。僕がしている職業も、まず本がないとできない仕事だし、もう無条件に尊敬があるから……逆に今日はお会いしてちょっと意外な印象でした。「THE小説家」みたいな感じの方なのかと思っていたので。
青崎:もっと変わったタイプの人間かなと思いました?
早乙女:そうですね。『ノキドア』には変わった人がたくさん登場してきたので、青崎先生がそのなかでもトップを行くくらいの変わり者だったらどうしよう……と少し身構えていたところもあったので(笑)。
青崎:アハハハ。でも、小説家によってお話の作り方は様々ですからね。「その作り方でどうして書けるの?」っていう方もいらっしゃいますし(笑)。僕は自分がインプットして「面白い」と思ったものを、自分なりに組み立て直すという作り方が多いので、実体験を反映するというよりは、「こういうヤツがいたらいいな」という感じで全部頭の中で生み出しています。
早乙女:すごい。ネタ切れとかしないんですか?
青崎:しないですね。というのも僕は書くのがかなり遅いので、アイデアばっかり溜まっていってしまって。それがもどかしいです。
――逆に青崎先生から早乙女さんに聞きたかったことはありますか?

早乙女:そうですね、やっぱり演じている人の性格をまず考えますね。この役柄なら、こういうところを見るだろうし、こういう攻撃になるだろうな……って。僕はアクションというのは「言葉」と同じだと思ってるので。なので殺陣を作るときは、ちゃんと会話に見えるようにっていうのは意識してますね。
青崎:その人その人の個性がやっぱり出るんですね。
早乙女:個性と、あとはストーリーですね。前のシーンがこうだから、このぐらいかなとか。そういうところを考えていくのが、やっぱりアクションは楽しいです。ボクシングとかでも一緒だと思いますが、本当に0コンマ何秒で駆け引きをしてるというか、フェイントもそうだし、逆に隙を作って、そこを攻めさせるとか。
青崎:僕の中ではアクションも謎解きの一種だという感覚があって。どういう道筋で敵を倒すか、答えを探していく詰将棋的な。一応、お話の中でも相手の腕が上がってるから下を狙う、みたいな理屈を立ててつつ作るんですけど、それを実戦の人たちは一瞬で考えるんだなと思うと、すごいですよね。
早乙女:また難しいのが、映像と舞台でも結構変わってくるところなんですよね。映像だと1シーンをめちゃくちゃ細かく切って撮っていくんですが、舞台だと一連の流れでできるというか。だから、僕は流れで全部できる舞台の方が楽しいんですけどね。
青崎:実戦的なアクションと魅せるアクションとでもまた違いますしね。リアルなところで言うと僕、坂口拓さんもすごく好きで。ドラマ『封刃師』も大好きでした。
早乙女:わー、本当にアクションお好きなんですね。坂口さんは実戦タイプの方ですね。魅せるというより、めちゃくちゃリアルな。練習もあんまりしたがらないし(笑)。
青崎:やっぱりそうなんですね。噂は本当だったのか!
早乙女:殺陣の振り付けを「手」って言うんですけど。本番でリハーサルとは全然違う手で来るから。もうほぼフリースタイルっていう(笑)。坂口さんとご一緒したとき、僕は防御が基本スタイルの役だったんで、とにかくその場で避ける一方で!
青崎:ほとんどアドリブ状態(笑)。それこそ、もう実戦ですね。この話を聞いてから坂口さんのアクションを見るとまた印象が変わりそうですね。ありがとうございます、行為者の個性によって取る動きが変わってくるのは、なるほどなと勉強になりました。