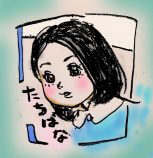金原ひとみ「泣いて怒って悩んで逡巡し続けながら幸せに生きてほしい」 他者の視点から描いた新刊小説『腹を空かせた勇者ども』

恋愛の善し悪しを判断するなんてもってのほか

――玲奈にとって、「自分」から離れるきっかけをくれるのが母親で、理解できない相手がそばにいるって大事なことなんだな、とも思いました。あんなお母さんがいたら……たぶんイライラすることも多いでしょうけど、読んでいると、羨ましいです。
金原:彼女は、私が理想とする女性像の一つですね。つまらないものにはとらわれない人である、ということを徹底して書いていたので、爽快でした。
母親が玲奈に「あなたのなかに概念として存在したい」っていう場面があるじゃないですか。あれは私自身が思っていることで、私がそこにいなくても「お母さんだったらなんて言うだろう」と考えたとき、予想できるような存在でありたいと思っているんですよね。
私も、生きて出会った人たちに限らず、たとえばドストエフスキーやバタイユなどの作家や、彼らが書いたキャラクターを思い浮かべながら、「あの人だったらどうするだろう」と考えたり、時には相談したりして、参考にしているところがある。概念としての他者を心のなかに住まわせていることが、自分を救うことってあるだろうなと思うんです。
――「概念として存在したい」に、母親の娘に対する深い愛みたいなものも感じました。それは、母親視点ではないからこそ描けたことでもあったんでしょうか。
金原:そうですね。彼女自身のモノローグで同じことをやろうとしたら、もうちょっとゴツゴツした手触りになっていたんじゃないかと思います。でも玲奈視点だからこそ、「なにそれ、変なの」と一蹴されるような軽やかさをもって書けたと思います。
――ちなみに、母親を公然不倫している人間として描いたのはなぜだったのでしょう。
金原:彼女もまた自身をコントロールしきれていなくて、自分が何を求めているのかあやふやな不安定さを抱えているという側面を描きたかったというのが一つ。玲奈が何事にも私はこう、私はこう、と明瞭なタイプであるのに対し、人間の複雑さや多重性といった余白をもたせたかったというのもあります。不倫や離婚といったものに対する偏見や嫌悪が日本では強いので、本人たちが了承していれば何も問題はないし、多少の複雑さを抱えていても幸せな家庭は築ける、と証明したかったというのもありますね。
あと、男性の不倫は女性の不倫のように断罪されない風潮への憤りもあって、基本的にすべての女性には公然不倫ぐらいしていてほしい、あるいはそれくらい不謹慎とされることをしていてほしい、という気持ちもこもっていますね。
――それぐらい自由であってほしい?
金原:そうですね。不倫とか個人的なことで騒ぐのとかマジでやめてほしいって、社会に対して心の底から思ってます。小説内でも書いていますが、人が人の恋愛の善し悪しを判断するなんてもってのほか、感想を漏らすだけで滑稽だと思います。
先日、アニー・エルノーの『シンプルな情熱』という小説を読んでいたら、若い愛人に熱をあげる主人公が、たまに自分の家に泊まりにくる元夫との間の子どもたちに対して「愛人が家に来ると電話してきたときは、すぐにここから立ち去ること」と、約束させたという描写があったんです。学生とあったので子どもはまあまあ大きいのでしょうが、そこ以外に子どもに関する描写はほぼなくて、主人公はずーっと愛人のことと書くことについて考え続けているだけです。日本では袋叩きにあいそうな女性の描写だけど、日本に住んでいる身としては非常にスカッとする部分でした。アニー・エルノーはスカッとしたと言われても意味がわからないでしょうけどね。
思春期の玲奈にとって、母親の不倫は深刻に葛藤する事案だけれど、母親は自分とは違う考え方をもつ別の人間で、彼女だけの人生を生きているのだという前提が備わっているから、他者に思いを馳せながら成長していくこともできたんじゃないかと思います。
――決して傷つかないわけじゃないけれど、母親も含めて「他者」との折り合いをつけながら強くなっていく彼女の姿は、ものすごく打たれるものがありました。彼女は全然かわいそうなんかじゃないし、外野があれこれジャッジするべきものでもない、と。
金原:そうですね。離婚家庭の見え方ひとつとっても、外側からと内側からとではいかに違うか、ということも書けてよかったなと思います。
人というのはどうしたって変化していくもの

――タイトルにもあるように、玲奈はいつもお腹を空かせていて、食べる描写がすごく多いじゃないですか。ペペロンチーノ二人前とか、山盛りのフライドチキンとか。成長期だから、という以上に、そこに彼女の健やかな渇望と、すべてを吸収して大人になっていく可能性、みたいなものも感じられて、読みながら愛おしくなりました。
金原:玲奈は開けっぴろげで、理詰めで考える母親と違ってまっすぐにしか進めないタイプなので、ただお腹が空いたから食べるという描写を重ねることで、その本質を表現したかったというのはありますね。
大人の場合、お腹が空くとまず、作るか、買うか、外食するかという選択肢が生まれ、そこに「でも太るよなあ」とか「明日は会食で何料理だから……」とかの検討の末に、何を食べるのかに着地する。でも玲奈の場合、「お腹空いた→ペペロンチーノ」みたいに欲望が直結している。そういう、複雑なものが絡まない純粋な食欲をもって、食べたいものをガツガツ食べ、どんどんでかくなっていく清々しさみたいなものも、書きたかったんです。
――成長期の玲奈を通じて物語が描かれることで、どんなに変わらないものを望んでいても人の関係性は変わっていくし、必ずしも考え方が一貫している必要もないのだということが伝わってきて、読みながら救われるような気持ちになりました。
金原:自分自身の作品を振り返ると、初期の作品は強い共鳴を抱くタイプの主人公が多かった。自分の何かを託せる友達や、子どもをつくっているような気持ちで主人公の設定をつくっていました。でも次第にその枠では書きたいこと、書かなければと思うことが収まらなくなり、一人称多視点で書くようになっていきました。
そして今回は初めて、自分から遠くかけ離れた性格と考え方の、完全な他者の目線で世界を描きました。人というのはどうしたって変化していくもので、そうでなきゃいけないとも思うんです。自分はこう、と一度決めたことに凝り固まってしまったら、そこで死んでしまったも同然だし、こうでありたいと願う理想像も更新していかなければ、この変化し続ける世界で本当の意味では生きていかれないとも思います。
これまでの主人公は、一人称多視点であったとしても、どこか自分のなかに内包され続けて積み重なってきたような印象があります。でもここまでかけ離れた存在の玲奈には、「ここにいなくていいよ」と背中を押したい。彼女には、もっともっと見てもらいたい景色がある。いろんなことに泣いて怒って悩んで逡巡し続けながら、どこか遠いところで幸せにやっていてほしいと思うんです。