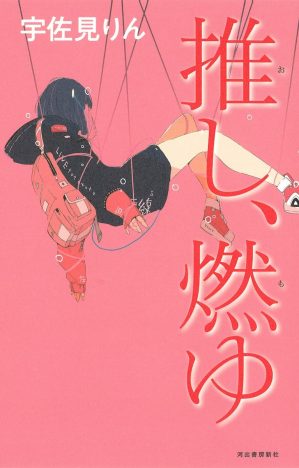カンヌ国際映画祭で脚本賞受賞の『怪物』ノベライズ版が曝した、誰もが”怪物化”しうる現代社会のリスク

「怪物だーーれだ?」と何度も繰り返す幼い声、学校の床に滴り落ちる血、燃え盛る炎。その映画の予告編を初めて目にした時、言いようのない不安感に襲われた。
実際に起こった“新生児取り違え事件”を題材にした『そして父になる』(2013年)や、寄せ集めの家族が生きるために法を犯す『万引き家族』(2018年)など、自身の作品で社会に蔓延る問題を可視化させてきた是枝裕和監督と、生きた人と言葉を描き、熱狂的なファンを持つ脚本家の坂元裕二。さらに数々の名曲を遺し、今年3月に惜しまれつつこの世を去った音楽家・坂本龍一がタッグを組んだ映画『怪物』がついに公開となった。第76回カンヌ国際映画祭で脚本賞とクィア・パルム賞を受賞した本作をいち早く観ようと6月2日の公開日当日から多くの人が映画館に駆けつけ、すでに興行収入は3億を達成している。
そんな『怪物』のノベライズ本(著・佐野晶)が宝島社文庫から映画の公開に先駆けて発売されており、Amazonで同レーベルの売れ筋本第1位を堂々と獲得した。正直なところ、この作品はできる限り前情報なしで挑む方が楽しめるが、結末に触れない形でレビューする。ただし、途中の内容については核心に触れるため、映画や本をまだチェックしていない方はご注意いただきたい。
本作は周囲を山に囲まれ、大きな湖のある静かな町が舞台だ。温泉が湧き出す観光地でもあり、まもなくゴールデンウィークで多くの人が訪れようとしていたある日、繁華街にあるガールズバーなどが入った雑居ビルで火災が発生。その前後で起きる二人の少年・麦野湊と星川依里の変化とそれに気づいた大人達の焦燥が描かれている。
物語は夫を早くに亡くし、湊を女手一つで育てている母親・早織の目線から紡がれていく。湊は思春期に入ったばかりの小学五年生。そっけない息子の態度を寂しく思いながらも、早織はそれも成長の一過程と前向きに捉えようとしていた。しかし、ある時から湊が突如自分で髪の毛を切ったり、片方だけスニーカーをなくす、Tシャツを絵の具で汚して帰るなどの不可解な出来事が続き、疑心暗鬼に囚われていく。そうなると、どうしても脳裏をよぎるのが“いじめ”の三文字だ。早織はそれでも当初はしばらく湊をよく観察することに徹したが、彼が自殺未遂と思われる行動を起こしたことで事態は一変。「湊の脳は、豚の脳と入れ替えられている」と担任の保利に言われたと湊が証言したのだ。
そんなの、子供を愛する親が黙っていられるはずがないだろう。早織はすぐさま、事実確認のために学校を訪れる。だが、孫を亡くしたばかりだという校長の伏見はまるで壊れたロボットのように頭を下げるだけ。生徒への体罰や暴言が疑われる保利も“謝罪パフォーマンス”をただこなすのに必死で、自分が悪いという認識はなさそうだった。それは早織の立場になって想像するだけで身震いするような場面だ。事なかれ主義に陥りやすい教育現場の問題は現実世界でも度々取り上げられ、そういうことが現実にあるとは理解していても、実際に自分が親として直面したらたまったものではない。誰だって心からの謝罪が聞けるまで、あの手この手で間違いを認めさせようとするはずだ。結局早織は弁護士に相談することを決意し、学校は保利は担任を外れたのちに退職する。遺恨は残したものの、問題はこれで一旦解決した……はずだった。
先ほど物語は早織の視点で紡がれていくと書いたが、本作は映画と同様に3部構成となっており、視点が第2部では保利、第3部では湊に移る。すると全く別の真実が浮かび上がってくるのだ。同じ出来事を経験したはずの者たちが語る話が微妙に食い違い、聞く人を混乱させる、いわゆる“羅生門効果”が本作には使われている。その中で特に印象付けられているのが、“豚の脳”という言葉。豚の脳を移植した人間、つまりは人ならざる者、化け物、怪物であると子供たちを脅した者がいる。それは誰なのか、そいつが本当の“怪物”なのではないか。実は、そう読者に思わせることが作り手の狙いなのである。
物語の冒頭で起きる雑居ビル火災は放火の疑いがあった。誰かが火をつけ、周辺には野次馬がどんどん集まってくる。同じような光景を近年、誰もがネットの中で毎日のように目にしていることだろう。SNSが普及し、今や誰もが不特定多数の人に情報を発信できるようになった。様々な被害に遭った人たちが泣き寝入りすることなく、声を挙げられるようになった。狡い言い方にはなってしまうが、それ自体を良い悪いで語ることはできない。ただ問題なのは、好奇心でそこに火をつけ、さらに誰かが油を注ぐことで物事の本質が煙で見えなくなってしまうことだ。被害者を守るという名目のもとで加害者と思われる者をあぶり出し、石を投げ、徹底的に叩き潰す。果たして、その時の顔は“怪物”になっていないだろうか。
「怪物と戦う者は、その過程で自分自身も怪物になることのないように気をつけなくてはならない。 深淵をのぞく時、深淵もまたこちらをのぞいているのだ」というニーチェの言葉がある。まさに本作は、そのたった二行の言葉から膨らませたかのような物語だ。
最初は全ての元凶に思える保利が雑居ビル火災を見学しに行った際、そこにはバニーガールの姿をした女性がいた。ガールズバーの従業員だろう。彼女の怯える様子を目撃し、保利は急に野次馬根性の自分が恥ずかしく思える。その後、彼はまた別の“炎”に焼かれるのだが……。怪物に仕立て上げられる者、自分でも気づかずに怪物となっている者。私たちは常にどちらの立場にも置かれうる人間だ。