「ジャーロ」編集長インタビュー 「評価がある評論家さんが、売れる本を書けないとは思えない」
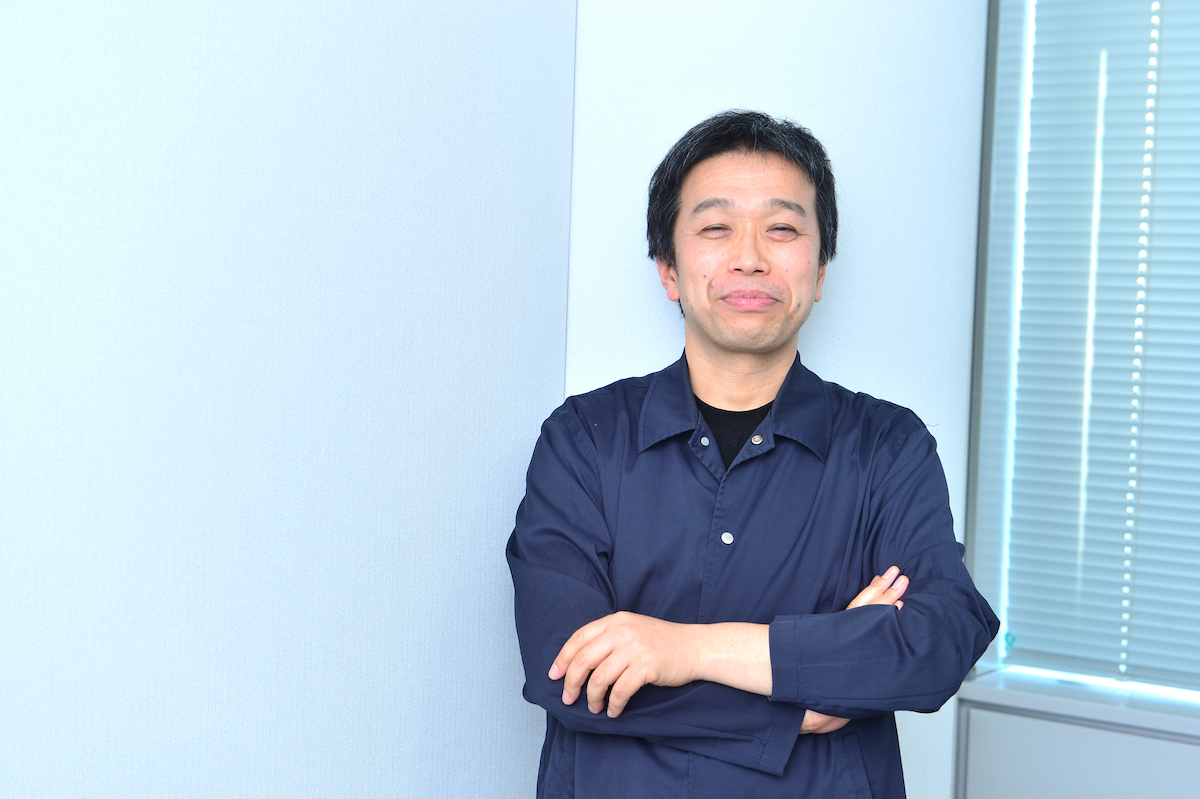
評論家さんが売れる自著の企画を考える場所があったほうがいい

鈴木:それは、円堂さんの本がきっかけです。
――ん、私の?
鈴木:僕が書籍編集を担当した『「謎」の解像度(レゾリューション) ウェブ時代の本格ミステリ』(円堂都司昭。「ジャーロ」連載後、2008年書籍化)は、本自体は面白かったし、第62回日本推理作家協会賞評論その他の部門を受賞したけど、同時受賞だった栗原裕一郎さんの『〈盗作〉の文学史 市場・メディア・著作権』ほどは売れなかった。円堂さんの本は作家論集で、作家たちのファン以外に広がりにくかったけど、盗作がテーマの栗原さんの本はとりあげられた作品を読んでいない人の興味も引いた。企画の差なんだと思いました。評論を売ることはできるはずだと考えたんです。
一部で「評論家は他人のふんどしで仕事をしている」という声を聞くことがあって、気になっていたんです。「ジャーロ」に書評や時評を掲載することに意味がないとはいわないですけど、小説も掲載している媒体ではプロモーションの色合いが強く、言葉は悪いですが、たいこもちの印象が拭いがたくなります。版元の立場では、自分たちの作った本をけなしてほしくはないですし。フラットな形で書評活動をするのなら、専用の媒体なり同人誌でやる方が公平なようにも思います。その意味で「道玄坂上ミステリ監視塔」(杉江、千街も参加する国内ミステリの連載短評コーナー)をリアルサウンドでやるのはいいことだし、逆にリアルサウンドで小説を載せるのは難しいでしょう。役割が違うんです。
――私がその後、小説誌を出していない青土社で『戦後サブカル年代記 日本人が愛した「終末」と「再生」』、作品社で『ディストピア・フィクション論 悪夢の現実と対峙する想像力』という評論書をまとめたのは、そういった環境を意識した面があります。
鈴木:僕は「ジャーロ」に書評を増やす気はないですけど、評論家さんが売れる自著の企画を考える場所があったほうがいいと思って、評論を増やしたんです。では、評論の価値を高めるにはどうしたらいいか。文学賞を含めた、お墨つきがあった方が、安心して読んでもらえるという面はあると思います。身も蓋もありませんが、「この人、売れてるから、いいこといってるに違いない」と思わせるのが、手っ取り早い。「ジャーロ」では稲田豊史さんが連載中ですけど(「ミステリーファンに贈るドキュメンタリー入門」)、始まった時には『映画を早送りで観る人たち』が光文社新書でベストセラーになるとは予想しませんでした。ですが、ヒット作を持つ方に書いてもらうことで、全体の注目度が上がれば、と思っています。円堂さんにも『バンド臨終図巻』(速水健朗、栗原裕一郎、大山くまお、成松哲との共著)というヒット作がありますし。
評論家さんは研究成果も大事だからそちらに意識がいく方も多いかもしれませんけど、売文業であることも確かなんだからヒットを狙ってほしい。一定以上の評価がある評論家さんが、売れる本を書けないとは思えないんです。たくさん本を読んでいて、いろいろ語れるから重宝するというのではなく、「ジャーロ」では売れる文章を書けることを示してほしいと思っています。僕が編集長の間に結論は出ないでしょうけど、その方針で考えないと小説誌に評論家が執筆する意味がなくなっちゃう。
過去作の継承が新たなヒット作を生むきっかけになりやすい
――光文社は、光文文化財団で「わが国のミステリー文学の発展に著しく寄与した作家および評論家」に贈る日本ミステリー文学大賞を催しています。 「ジャーロ」では昨年から、第1回の佐野洋氏を皮切りに歴代受賞者を振り返る「日本ミステリー文学大賞の軌跡」(探偵小説研究会メンバーが交代で執筆)の連載を始めました。
鈴木:それも僕の発案です。同賞は作品ではなく人に贈るから、賞というよりは殿堂入りに近く、書店店頭でアピールしにくいのが悩みでした。マスター・オブ・ミステリーを繰り返し顕彰する必要があると考えて、新潮文庫の「文豪ナビ」シリーズに憧れつつ、受賞作家に関する読書案内を意図して企画しました。有栖川有栖さんをはじめ、多くの後進作家が影響を公言していることもあって鮎川哲也さん(第6回特別賞を受賞)の名は若い読者にも比較的知られていますが、初期受賞者の多くは知られていないですから。
――最近、徳間文庫の「トクマの特選」から有栖川さんのセレクトで笹沢佐保作品が刊行されたりしています。ああいうことをやらないと、忘れられてしまう。
鈴木:洋楽誌「ロッキング・オン」では、ロックの古典のビートルズを毎年表紙にして載せてもいいことになっているじゃないですか。そのようにクラシックを振り返ることもありなのが、ジャンル・エンタテインメントのいいところだし、ミステリもそうであっていい。「歴史街道」が、繰り返し徳川家康を特集するのと変わらない。生活の実感やリアリティ、読者の共感が重視される側面のあるストレート・ノベルとは違って、ジャンル・エンタテインメントは、過去作の継承が新たなヒット作を生むきっかけになりやすい。ミステリやSFは、これまでどんな作品が書かれてきたか、あの作品のようなことが書きたい、あれがありなら俺はこんなことが考えられるといったところから始まると思っています。だから、過去の作品をレビューする意味があるんです。
――小説家の新人発掘についてはどうですか。
鈴木:日本ミステリー文学大賞新人賞(光文社の公募新人賞)は、僕が文芸に移る前年にできました。この賞にかかわって、社業としての選考の難しさを実感し続けています。総合力で判断されるからか、突飛な発想を持った応募作が未熟さを突かれてしまい、どうしても優等生的な作品が最終選考に残るし、高齢者が多くなる。魅力的な新人賞に育てていくための試行錯誤は、まだ続いています。たとえば講談社は、多くの新人賞と同じく、幾度かの予選を経て最終の選考会をもつ江戸川乱歩賞と、編集部が直接選ぶメフィスト賞の二本立てで、多彩な新人作家を輩出しています。光文社でも同様のことができないかと相談して、編集者が選ぶKAPPA-ONEを2002年から始めました。それは、光文社文庫で刊行されていた短編ミステリの公募アンソロジー『本格推理』の常連投稿者に長編発表の場を与えられないかと、社内で相談があったのがきっかけです。でも、運営のしかたがわからないまま「公募ガイド」で募集したら膨大な投稿がきて編集部がパンクしました。
――KAPPA-ONEのデビュー作家では誰を担当したんですか。
鈴木:僕は、東川篤哉さん、詠坂雄二さん、樹月弐夜さんを担当しました。KAPPA-ONEは2007年で休止しましたけど、やはり日本ミステリー文学大賞新人賞とは違うチャンネルが欲しくて、東川さんの新刊プロモーションで地方へ同行した時、「KAPPA-ONEを再開したいので 選考委員をやってもらえませんか」とお話したら引き受けてくださった。やるならば石持浅海さんと一緒がいいというお話になり、「KAPPA-ONE第一期のデビュー作家2人が選考委員をやるんだから「カッパ・ツー」がいいんじゃないですか」と東川さんが名付けてくださいました。
――カッパ・ツーは編集部ではなく2人の作家が決定する形で、これまで阿津川辰海、犬飼ねこそぎという存在を送り出した。阿津川さんは注目作家になりましたけど、デビュー作『名探偵は嘘をつかない』(2017年)は、応募時から大幅に改稿しての書籍化だったそうですね。それが可能だったのは通常の新人賞と違う形だったからでしょうか。
鈴木:KAPPA-ONEもカッパ・ツーもしつこく「新人発掘プロジェクト」と呼び続けているのは、賞ではないから。賞金もないですし、無冠のデビューという扱いです。ですから、贈賞式もありませんし、納得のいくまで時間をかけて改稿してもらっても構わない。それでも、阿津川さんの改稿は編集部の予想以上の分量と品質でしたが。カッパ・ツーは、当初から一期につき応募は10作から15作くらいで、変わっていません。だから、誰も知らないプロジェクトなんだけど、阿津川さん、犬飼さんほどの才能を見出せるならそれでかまわないでしょう。今後、新しい公募企画を始めるならば、頑張って探さなければ見つけられないところで募集するのがいいのかもしれません。
――その方が、猛者がくるのかもしれません。ウェブでの展開も含め「ジャーロ」というプロジェクトで今後やりたいことはなんですか。
鈴木:計画段階で詳細が決まっていないので、あえて口に出してしまいますと、「ジャーロ」は現在88号を制作中ですが、100号は紙版を出したいと思っています。完全読み切りの一冊にできればと。
また、小説ができるまでを刊行後の反響も含めて当事者に語ってもらう「アフタートーク 著者×担当編集者」(聞き手・構成は円堂)を現在連載していますけど、『きのう何食べた?』みたいなノリで、この雑誌で書くならどんな小説にしたいかを作家同士で対談してもらう「「ジャーロ」でなに書く?」ってタイトルの企画を妄想しています(笑)。「アフタートーク」は、僕が企画を立てたんですが、ヒット作・話題作が構想・執筆され、書籍として発表されるまで、あるいは発表されてからの販売戦略や映像化等々に、編集者がどうかかわっているのか、ずっと前から、興味があったんです。他のひとはどうやっているんだろう、と。小説そのものが面白いだけでなく、小説の周辺も面白いよという思いがあります。それを読んでもらえるのが雑誌の良さではないでしょうか。多くの作家さんとやりとりをしていて、「こんな小説書きたいんだよ」と話されている時が一番楽しそうだから、「「ジャーロ」でなに書く?」もぜひやりたいですね。
■関連情報
「ジャーロ」公式サイト

























