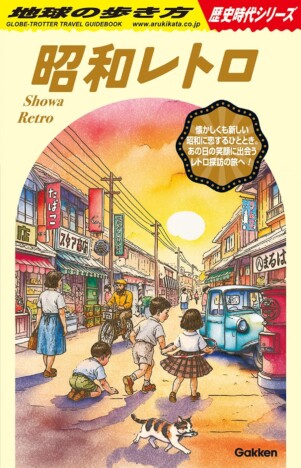【今月の一冊】現代若者論から文学賞受賞作まで、各出版社の「新人作品」を紹介

『鴨川ランナー』グレゴリー・ケズナジャット

日本語を母語としない作家による新たな越境文学が誕生した。グレゴリー・ケズナジャットの小説『鴨川ランナー』(講談社)だ。
表題作は米国出身で日本に住む男性が異文化のなかで感じる葛藤が描かれている。最初に日本に憧れを抱いたのは、高校時代の京都旅行。鴨川は「まるで御伽噺の光景だ」と感嘆した。米国の大学卒業後に夢の京都で暮らし、英語の先生として働く。しかし「外国人」という記号で、部外者のように扱われることに違和感を深めていくーー。
本書の特筆すべき点は、著者の人生との重なりを感じさせる作品でありながら、「きみ」という二人称で書かれていることだ。読者は常に「きみはどうだろう?」と問われているように感じるだろう。
「きみ」は大学時代のガールフレンドに「オリエンタリスト」だと指摘されたことが忘れられない。すぐさま否定したが、後に日本女性に恋心を抱いた時に「御朱印巡り」をする姿を想像してしまう。一方で相手(=きみ)の側はどうだろう? 女性は初めて体を重ねた後に「海外の匂いがする」と漏らす。彼女も過去のニュージーランド留学が忘れられず、「海外」「外国人」という記号に翻弄されていたのだった。二人の逢瀬は長くは続かなかった。
異文化への接近の不可能性を鋭く繊細に描き出す本書だが、ある種の救いが描かれている。やがて東京に転居した「きみ」はふと「京都に帰りたい」という言葉が内から出てきたことに驚く。生まれ故郷でない地に「帰る」とは、日本語の文法としては間違っていた。しかし、オリエントとしての京都(=きみ)が、複数の人と出会い過ごした時間の蓄積を経て、新しい「故郷」になった瞬間だったと言えるだろう。それは鴨川のように常にそこにあるものだったし、川の水のように流れゆくものでもあった。
「外国人」を色物の「他者」としてばかり扱ってきた日本社会において、「きみ」の故郷を描いた本書は広く読まれるべきだと思う。(篠原諄也)