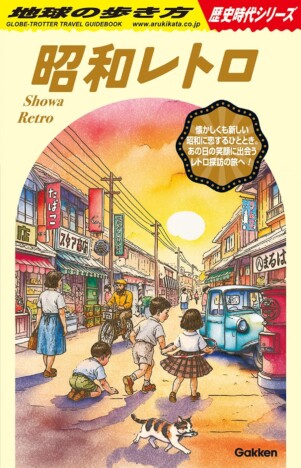【今月の一冊】現代若者論から文学賞受賞作まで、各出版社の「新人作品」を紹介

『birth』山家望

筑摩書房と三鷹市の共同主催による文学新人賞「太宰治賞」。2021年、過去最多となった1548遍の応募作から同賞に選ばれたのが、山家望『birth』だ。
一ノ瀬ひかるは幼い頃、母に棄てられ、施設で育った。彼女にとって、手元に残された母子手帳が唯一の母とのつながりであり、自分の存在と、愛されていたはずの過去を証明してくれる、心の拠り所だった。高校を卒業し、社会に出て、持病の治療もままならない、余裕のない生活を送っていたある日、ひかるは公園で、誰かが落としたと思しき母子手帳を拾う。母親の名前は、松島”ひかる”。名前どころか、生年月日まで同じだ。その母子手帳をクリニックに届け、どんな人物で、どんな母親なのか見届けようと待ち続けるが、ようやく現れた松島ひかるは、思いも寄らない行動を見せて……。
断片的で時に曖昧な母との記憶と、母子手帳に刻まれた確からしい記録。それを頼りに生きる主人公は、母親に会いたいという思いを抱えながら積極的に行動に移すことなく、独白も基本的に淡々としていて、自身の“恵まれなさ”を強調することもない。持病により喉に溜まっていく膿と、心につっかえたしこりは、経済的な事情と彼女自身の性質からともに容易には解決されず、通奏低音として鈍い痛みを訴え続ける。
そんななかで、偶然に出会ったもうひとりの「ひかる」とその子どもの両方に、自分が歩んだかもしれないパラレルな人生を追う姿が、ある種の欠落を感じさせながら、切実に描かれる。それが前向きなものか、後ろ向き、あるいは奇異ともいえるものかは読者の感覚に委ねられるが、物語の終盤、“産みの苦しみ”に相当する体験とともに、大声をあげて泣く自分の姿を想起する一ノ瀬ひかるは、確かに“再生”を果たすのだろう。
空洞化していると指摘されて久しい「家族」をテーマに、『birth』という切実なタイトルがつけられた本作は、多くの人にとって、いま読むべき小説の一遍と言えるかもしれない。(橋川良寛)