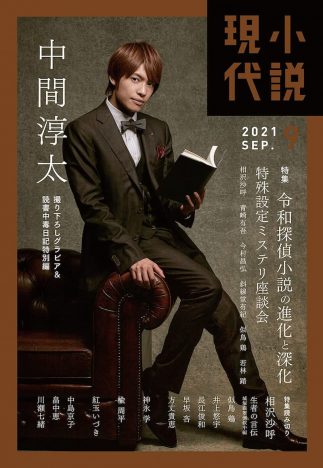講談社はいかにして日本を代表する総合出版社になった? 魚住昭が語る、文化の作り手としての矜持

国際企業としての講談社
――敗戦後、「講談社中興の祖」と呼ばれることになる高木(野間)省一が、左衛の嘆願で二代目社長・恒の未亡人である登喜子と結婚し、野間家に入ります。省一は、日本初の国際企業だった南満州鉄道で将来を期待されたエリートでしたが、満州における書籍の不足を目の当たりにして問題意識を抱いていたこともあってか、講談社に入ることを決意したようです。清治を信奉していた講談社社員にとっては、外から来て社長に就いた省一を快く思わない向きもあったようですが、結果として省一は講談社を総合出版社として立て直すことに成功します。改めて、省一にどんな印象を抱いたかを教えてください。
魚住:資料を当たっていて特に印象的だったのは、編集者の一人が「これは我が社の目玉商品です」と言ったときに、省一が怒り出したというエピソードです。省一は、本は単なる商品ではなく文化財であるという意識を持った人で、営業のものが言うならまだしも、編集者が自分の作った本を「商品」と言うことは許さなかったそうです。
省一には雑誌社だった講談社を総合出版社化したという功績がありますが、その根底には世界からブックハンガー(図書飢餓)を無くすという大きな使命感がありました。利害を越えて、アジアやアフリカなどの発展途上国に協力し、本気で出版を通じて世界を平和にしようと考えているところがあった。僕は決して、野間省一という人物を全面的に賞賛するつもりはありませんが、掲げた目標の大きさには感嘆せざるを得ませんでした。
省一が力を注いでいた国際交流事業は、彼の代ではビジネスとして成り立ちませんでしたが、二十一世紀に入って講談社がグローバルにビジネスを展開する上で礎となりました。中国の出版監督官庁が、講談社は昔から付き合いがあるからといって、北京に100%子会社のKBCをつくることを許可したのは、省一の代から中国出版界との草の根の交流を続けてきたからです。その意味で講談社は、省一の掲げたヴィジョンの恩恵をいまだに受けていると言えます。
――文芸誌の『群像』がなかなか軌道に乗らずに赤字続きだったころ、編集長を務めていた大久保房男に対して、省一が「君は『群像』の権威を高めることだけを考えててくれればいいんだよ」と語ったエピソードも心に残りました。
魚住:少なくとも、単純な目先のそろばん勘定だけで物事を判断するタイプではなかったはずです。赤字である『群像』を前面に押し出すことによって、講談社の社会的な立場を高めていき、他の雑誌や書籍の価値も上げていくという遠大な考え方は、普通の経営者ではなかなかできないことだと思います。省一は理念や主義の面でも、会社の建て直しをしました。おそらく彼は満鉄時代、アジア主義的な思想を持っていた人で、それが戦後になって形を変えて表れたのが「出版を通じた世界平和」だったのでしょう。
現在、七代目の社長となった野間省伸さんは、ロンドンの銀行に勤めてグローバルな視野を養った方で、講談社はいま、国際化とデジタル化に舵をきっています。その轍となっているのは、省一が夢見た理想です。もちろん、省伸さんがまったく同じ思想を抱いているわけではないと思いますが、ふたりを重ねて見ることで、講談社が総合出版社として目指しているところがより深く理解できるのではないでしょうか。
出版がビジネスであることは言うまでもないことです。常に読者が求めることをリサーチし、より先鋭、鮮明な形で指し示すのが、編集者の主な仕事でしょう。しかし、講談社の歴史を読み解くと、文化の作り手としての責任を果たすという意識もまた、出版人にとって重要なものだということに気付かされます。