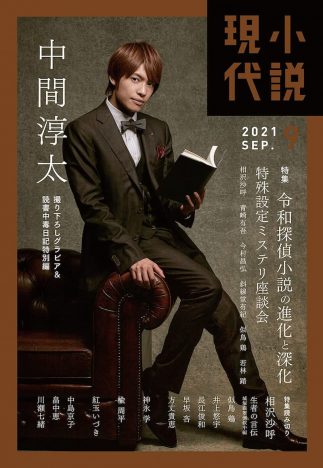講談社はいかにして日本を代表する総合出版社になった? 魚住昭が語る、文化の作り手としての矜持

日本独自の出版流通の誕生と終焉
――清治が雑誌取次の最大手だった東京堂の大野孫平と出会ったのも、その後の日本の出版業界の流通を左右する、重要なターニングポイントだったと思います。
魚住:僕が『出版と権力』を書く上で調べていたことで、いちばん目新しく感じたのは出版流通の成り立ちについてでした。これまで出版の歴史について書かれた本はたくさんありますが、講談社と東京堂の関係について詳しく書かれたものはなく、今回、講談社の秘蔵資料を読み解く中で見えてきたことがあります。当時、雑誌の元取り次ぎには東京堂、東海堂、北隆館、大東館の4社があって、大野孫平が率いる東京堂は中でも最大のシェアを占めていました。その東京堂が講談社という新興の雑誌社と組んだのは、大野が清治のことを個人的に高く評価したからで、両者が組んだことで講談社は戦前の雑誌界において圧倒的な主導権を握る存在になっていくんです。講談社は、戦前の日本の雑誌の7割前後ぐらいを占めるほどに急成長したわけですが、その背景には運転資金を捻出する機関であり、業界のまとめ役でもあった東京堂の存在がありました。
僕も本を書くにあたって、出版流通について一から勉強したのですが、柴野京子さんという方が書いた『書棚と平台: 出版流通というメディア』(弘文堂/2009年)という本はすごく勉強になりました。僕らは雑誌と書籍が同じ本屋に並んでいることに何の疑問も抱かないですが、欧米では本屋に雑誌は並ばないもので、雑誌は本来、新聞などを売るスタンドに並ぶものだそうです。雑誌が書籍とともに書店で売られているのは、日本独自の特殊なシステムがあるからで、柴野さんは「黄金の組み合わせ」だと仰っています。それが、大野孫平と野間清治の出会いによって作られていった。もともと日本の商業出版の歴史は古く、17世紀初頭にまで遡れるものですが、一方の雑誌は近代のマスメディアで、明治以降になって成立したものです。だから本来は流通のルートが違うのですが、講談社は関東大震災をきっかけに『大正大震災大火災』という雑誌のような書籍を臨時出版して、それを雑誌の販売流通網に乗せて全国的に売り出すという画期的なことをしました。雑誌と書籍を同じ流通網で全国津々浦々に届けるという独自のインフラがこの時代に作られたことによって、日本の出版業界はその後100年、成り立ってきたんです。ところが近年は雑誌が極端に売れなくなったので、それに乗っかっていた書籍もまた、これまでと同じ方法で流通させるのが難しくなった。現在の日本の出版流通システムがうまく機能しなくなった理由も、講談社と東京堂の歴史、あるいは野間清治と大野孫平の関係性を紐解くと、よりよく理解できるのではないかと思います。
――出版流通業界はいま、まさに大きな転換期にありますし、その意味でも本書が刊行された意義は大きいと思います。
魚住:この本が発売された直後に、講談社も新しい動きを発表しましたね。講談社と集英社と小学館が、大手総合商社の丸紅と組んで、出版流通改革を実現する新会社を設立しようとしています。日販やトーハンに全面的に依拠していた出版流通システムは、新しい時代を迎えようとしているのでしょう。また、Amazonとの直接取引が始まるという報道もありました。この件には関しては、まだどう評価して良いのかわからない部分がありますが、少なくとも今日の出版流通システムはすでに機能しなくなりつつあるというのは、各出版社のみならず、書店側においても共通の認識となっているのではないでしょうか。
出版と権力
――清治が亡くなった1938年(昭和13年)からは、講談社にとっても激動の時期でした。二代目として期待された野間恒も清治急死のわずか22日後に亡くなり、三代目として清治の妻だった左衛が社長に就任するも、功労者といえる社員たちや少年社員の処遇などをめぐって社内での対立が生じます。一方、同時期から日本は戦時体制となり、講談社もまた陸軍報道部の鈴木庫三少佐(のちに中佐)から圧力をかけられ、『雄弁』『冨士(キング)』『現代』などの雑誌がその編集方針の変更あるいは廃刊、統合などを求められます。「第七章 紙の戦争」では特に頁を割いて、この時期の出来事を丹念に著しています。
魚住:本書に『出版と権力』というタイトルをつけたのも、この時期のことを著すのが一番大事だと考えたからです。講談社は大衆の気分に寄り添うことで巨大な雑誌王国を築き上げてきた会社で「面白くてためになる」がそのコンセプトでした。しかし、『キング』の成功以降は「世のため人のため」という道徳路線のコンセプトが謳われるようになり、それが戦時体制で国家との距離を失っていくことで「国の為」になっていく。講談社は戦時体制の中で生き残るため、陸軍報道部にすり寄っていくのですが、同時に軍もそれを利用することで、隠微な関係ができていきます。そこから講談社は事業を多角化して軍需関連産業にも手を出し、この本で「異形のコングロマリット」と表現したような体制になっていきます。
講談社の戦争協力について、いまになって糾弾しようという意識はありませんし、僕にはそんな資格もありません。しかし出版に関わるものとして、この時期になにがあったのかを知る必要はあると考えています。将来の危機を回避するためにも、彼らが当時どんな判断のもとに何をしたのか、書き記して後世に伝えることが大事だと思いました。
――『講談社の歩んだ五十年』ではあまり言及されていなかった戦時下の出来事について、改めて深くメスを入れているのも、本書の姿勢を示していると思います。然るべきときを経ているからこそ、より客観的に当時の出来事を検証することができていて、いまを生きる我々にとっても意義のある警鐘です。
魚住:当時と現代ではもちろん状況は異なりますが、しかし出版界がこれから先、また同じような状況に遭遇しないとは限りません。過去になにがあったのかを知っているかどうかで、そのときの判断に大きな違いが出るはずです。だからこそ、具体的な事例に則して書くのが重要で、そこにノンフィクションの力があると考えています。