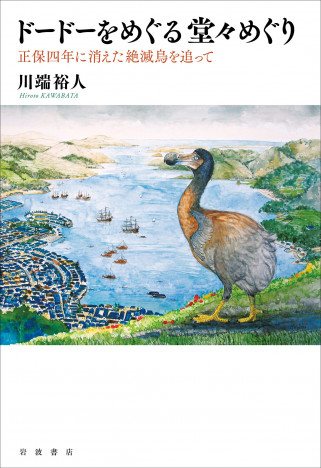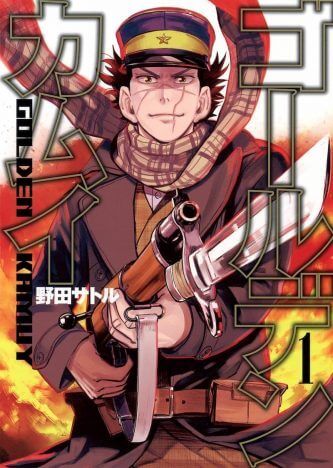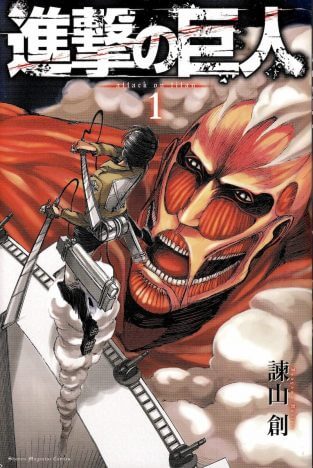貫井徳郎『邯鄲の島遥かなり』は歴史小説だーー島の一族が見た、明治から令和までの日本

しかし島の歴史は、楽しいことばかりではない。天災や戦争は、神生島にも容赦なく襲いかかる。ある話の主人公が、次の話では戦争で死んでいたりする。〝邯鄲の夢〟ではないが、人の世の栄枯盛衰は儚いのだ。とはいえ島民は、したたかでもある。一ノ屋の血を引く人も、引かない人も、自分の人生を一所懸命に生きていく。そうした人々の連なりが歴史となるのだ。だから本書は歴史小説なのである。
それにしても近年になって、近代を扱う歴史小説が増加した。門井慶喜の『地中の星』は地下鉄の父と呼ばれた早川徳次、植松三十里の『万事オーライ 別府温泉を日本一にした男』は別府観光の発展に尽力した油屋熊八、柚木麻子の『らんたん』は恵泉女学院の創立者の河井道と、その右腕の渡辺ゆり、木内昇の『剛心』は近代建築の雄である妻木頼黄と、近代を生きた実在人物を、それぞれ主人公にしている。どれも優れた物語だ。
ではなぜ、このような作品が増えているのか。簡単にいえば時代の変化である。昭和の時代では、大正や戦前の昭和は近すぎた。しかしもう令和である。おまけに昔に比べて、社会の在り方が、短いスパンで変化しているではないか。だから明治や大正だけではなく、昭和すらもの凄い勢いで歴史になっているのだ。
もちろん過去を舞台にしたからといって、すべてが歴史小説になるわけではない。肝心なのは作者が、自分の書く作品を歴史小説と認識しているかどうかだ。現代の多くの作家が、この認識を持っているからこそ、近代史は歴史小説の新たなる沃野となった。それに伴い、歴史小説の枠組みが拡大し、凄いことになっている。今回、言及した諸作を手にして、このことを実感してほしい。