伊坂幸太郎が超えてきた、エンタメ小説と純文学の境界 新作『ペッパーズ・ゴースト』を読む
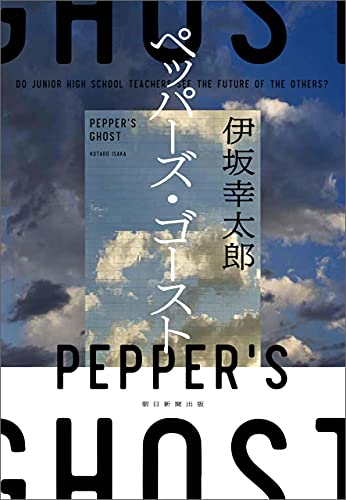
盛りこまれた諸要素とそれらを含んでいた過去の作品例をあげてみると、超能力(『魔王』2005年の他人の発言を操る力)、並行するストーリーが思いがけない形で交わる(『フィッシュストーリー』2007年)、猫(猫視点の章がある『夜の国のクーパー』2012年)、ビートルズ「ア・デイ・イン・ザ・ライフ」への言及(タイトルがビートルズの曲に由来し作中二も出てくる『ゴールデンスランバー』2007年)、野球(天才バッターが主人公の『あるキング』2009年)、学校(『逆ソクラテス』2020年)などなど。
確かに「全部乗せ」なのだが、濃厚とか脂こってりではなく、読み味はくどくない。『ペッパーズ・ゴースト』では、悲惨な事件の関係者たちが登場する。しかし、伊坂作品ではいつものことだが、重い題材を扱ってもいい意味で軽みがあるのだ。
本作では、哲学者ニーチェが『ツァラトゥストラ』で述べた「永遠回帰」について壇が考え、他の人とも意見を交わす一方、ネゴジゴハンター二人組が罪をめぐる冗談か真面目かわからない会話をする。殺し屋がドストエフスキー『罪と罰』を愛読していた『グラスホッパー』(2004年)や、その続編『マリアビートル』(2010年)における蜜柑と檸檬という殺し屋コンビの会話もそうだが、どれだけ本気かわからないやりとりを入れたり、重い要素と軽い要素を並べたりすることで物語が暗く淀まないようになっている。どこか風通しがいいのだ。それは、ただ冗談でまぎらわせるというのではなく、悲惨な出来事がまるで冗談みたいに理不尽に起こってしまう現実を踏まえた書きかたにもなっている。このへんのバランス感覚は、相変わらず絶妙だ。
しかも、本作は、全体が危機的状況に向けて緊張感で盛り上がっていくだけではない。作中作のネゴジゴハンター2人は自分たちが小説の登場人物だと自覚しているなど、メタフィクション的で過剰な部分を含んでいる。サスペンスとしてのきれいな枠組みを突き抜けている。なるほど「集大成」というにふさわしい作品なのだ。
























