伊坂幸太郎が超えてきた、エンタメ小説と純文学の境界 新作『ペッパーズ・ゴースト』を読む
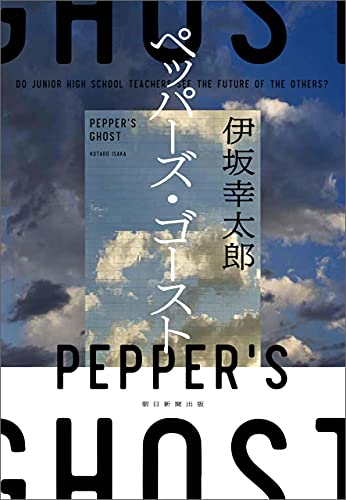
底が抜けるという表現があるが、伊坂幸太郎の小説はむしろ天井が抜けているのだと、新作『ペッパーズ・ゴースト』を読んで思った。
中学校で国語を教える壇先生は、父から奇妙な力を受け継いだ。他人から飛沫感染することで相手の未来が見えるのだ。父はそれを「先行上映」と名づけていた。壇は、虐待された猫のための復讐を請け負う「ネコジゴハンター」二人組について書いた自作小説を生徒から渡され、その内容が作中に随時挿入される。また、壇は「先行上映」能力のおかげでサークルと呼ばれるグループとかかわることになり、未来の危機を回避するため奮闘しなければならなくなる。
『ペッパーズ・ゴースト』では、ネコジゴハンターで猫にちなんだ偽名を使うロシアンブルとアメショーがいずれも野球ファンであり、後に視点人物の1人となるサークルの一員、成海豹子は、野球場でビール販売員をしていたことがある。このため、野球の話がたびたび出てくる。だが、ハンターたちが好きな「東北イーグルス」と「東京ジャイアンツ」が対戦し物語の重要な舞台となる場所は「後楽園球場」なのだ。天井があって雨天でも試合開催が可能な東京ドームに役割を引き継ぎ、1987年に閉鎖された後楽園球場が、この小説では現役であり続けている。
読むと今の日本のように感じられる『ペッパーズ・ゴースト』の世界は、パラレル・ワールドの日本と設定されているわけだ。同作のなかの人々は、球場の上を天井でふさがれず、突き抜ける空の下で試合を楽しんでいる。この小説における“抜け感”は、野球に関してだけではない。飛沫感染で相手の未来が見える超能力の設定からして現実を突き抜けているし、他にも常識はずれな要素を含んでいる。
『ペッパーズ・ゴースト』は書籍の帯で「作家生活20周年超の集大成となる、一大エンターテインメント長編!」と銘打たれているが、ふり返れば伊坂幸太郎は、新潮ミステリー倶楽部賞を受賞した2000年のデビュー作『オーデュボンの祈り』の時から“抜け感”のある小説を書いていた。同作は、未来が見えるうえに人語を喋れる案山子がなぜ殺されたかという、突拍子もない謎を語った一風変わったミステリーだったのである。
初期の伊坂の作品は、洒落っ気があって気の利いた会話、奇矯な人物の登場、ロックやジャズへの言及、軽妙な文体などから、しばしば村上春樹と比較された。だが、伊坂本人は村上作品をほとんど読んでいなかったと証言しており、ミステリー以外で愛読した作家としてあげたのはむしろ大江健三郎だった。
私は、5冊目の長編『アヒルと鴨のコインロッカー』(2003年)を刊行した頃の伊坂にインタビューしたことがある(探偵小説研究会編著『本格ミステリこれがベストだ! 2004』所収)。その際、いわゆるミステリー、エンタテインメントに分類される「冒険小説以外でも、冒険はあると思うんです」と話し、例にあげた作家名が大江健三郎だったことを覚えている。大江はノーベル文学賞を受賞した純文学作家だが、若い頃には痴漢がつかまるまでの顛末をある種の日常の冒険が挫折する過程として描いた『性的人間』(1963年)なども発表していた。また、大江は幻想性やSF的要素を含んだ作品を少なからず発表している。そういうタイプの純文学作家として、村上春樹は大江健三郎の後継的存在だったといえる。
冒険や幻想などのエンタメ要素が、エンタメの枠外にあって実験が許される純文学でも書かれていると意識することは、伊坂の執筆姿勢を自由なものにしたように思う。2008年に『ゴールデンスランバー』(2007年)で第5回本屋大賞を受賞するなど、伊坂は人気作家になった。ただ、彼は純文学ではなく面白さ重視のエンタメの道を選んだとはいえ、自分が考える面白さのためにはエンタメらしく収まらなくてもいい、突き抜けてもいいという姿勢をとっている。
結果的に後には「群像」、「新潮」といった純文学雑誌にも作品が掲載された。同じく大江の影響があり、自分が考える純文学のためにはエンタメ的になって純文学らしくなくなってもよいという姿勢の阿部和重と伊坂が意気投合し、『キャプテンサンダーボルト』(2014年)という共作を発表したのは、必然と感じられる。
そして、新作の『ペッパーズ・ゴースト』である。著者自身がインタビューで「得意パターン全部乗せ」と語っている。(【公式】伊坂幸太郎『ペッパーズ・ゴースト』) 読んでみると確かにそうで「集大成」、「一大エンターテインメント」と銘打たれた通り、かなりサービスしてくれた印象だ。























