アメリカ女性文学の研究者が見出した、少女マンガとの繋がり 大串尚代インタビュー
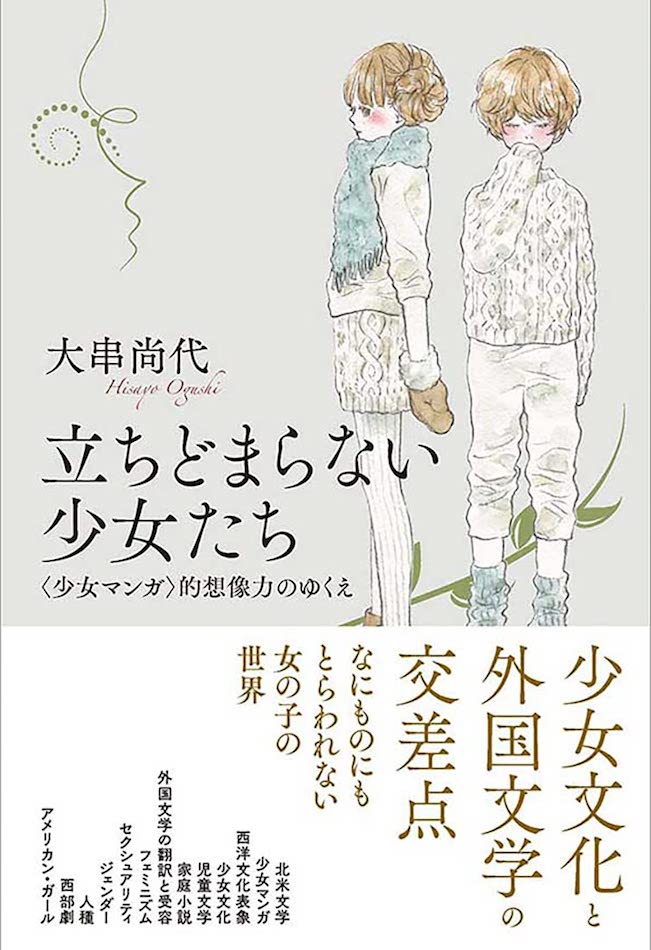
読み手にも描き手にも必要な繊細さ
――ネットやアプリでマンガが親しまれるようになってきたなかで、BL(ボーイズ・ラブ)をテーマにした作品を目にする機会が増えたように思います。BLは少女マンガなのか、という大きな問いにどう答えますか?
大串:BLをそのまま少女マンガとは言えないかもしれませんが、地続きじゃないかなと思います。少女マンガの定義は色々とあると思うのですが、私が今回の本で扱った作品は大きく「女性作家が読者の女性に向けて描かれた作品」と定義できます。BLも、様々な作家さんがいると思いますが、おおむねそうでしょう。基本的に、女の子の妄想が暴走するようなジャンルですから。
――少女マンガ誌で連載されていても、BLの要素を感じる作品はたくさんありますね。
大串:このインタビューを受けるにあたって、のちにBL作家になられたあさぎり夕さんの『こっちむいてラブ!』などを読み返していたのですが、男の子同士のケンカのシーンなんて、とても生き生きと描かれています。小中学生のころ、あさぎり夕さんや魔夜峰央さんの作品を読んでいたからこそ、大人になってから二次創作やアニパロを読んでも抵抗がなく、そういうものか、と思えたのはやはり少女マンガのおかげかと。
――場合によってはBL作品も含め、少女マンガは「ひとには色々な事情があるよね」ということを教えてくれますね。
大串:そうですね。作品によるんですけど、すごく悪い人でも背景がきちんと描かれているものが多い気がします。絶対悪みたいなものを描かない。それか、絶対悪すら許容してしまう、包み込んでしまうような包容力のあるジャンルなのではと思います
――『BANANA FISH』のディノ・ゴルツィネすら、絶対悪ではないですよね(笑)。
大串:そうそう(笑)。そういう作品が年々増えてきている気がしますね。
――最後の質問になりますが、菅聡子さんが『女が国家を裏切るとき』(岩波書店)で「文学的感傷に抵抗せよ」とお書きになっていました。大串さんは「感傷小説」や「家庭小説」がご専門ですが、「感傷」というものをどうとらえますか? 私はセンチメンタリズムはとても危ういものだと感じることがあるのですが……。
大串:それはまったくその通りですね。感傷性はプロパガンダにも利用されやすく、少女マンガに見られる「共感」ということに関しても、批判的にみる評論家もいます。アメリカ文学では、19世紀に女性作家が書いていた「感傷小説」というジャンルは感傷性があるがゆえに、ながらく価値がないとされてきたんですが、その感傷性が人々や社会に与える影響を再評価する批評が出てきて、多くの作品に注目が集まるようになりました。少女マンガも同様で、感傷や共感という力が転用されやすいものであるという指摘ももちろんその通りなんですが、同時に読者をいい意味でエンパワメントして、意識を変えていくものでもあると思います。感傷や感情自体に、いいも悪いもないですから。大切なのは、それをどう使っていくか。異性愛を当然の規範として描き、共感を集める作品もありますが、そうではない愛を描かれた竹宮恵子さんや萩尾望都さんのように、少女マンガの多様性を常に意識していくことが大切だと思います。読み手にも描き手にも、繊細さが必要だと考えています。
























