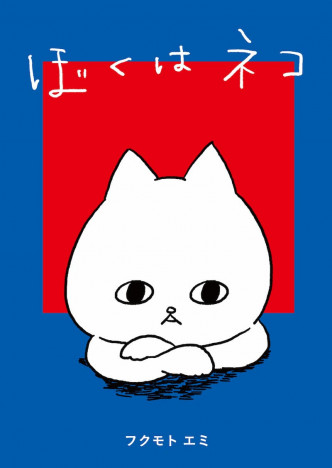ぜんぶ君のせいだ。如月愛海が明かす、小説執筆のウラ側 「人生の苦しいほうにフォーカスを当てたい」

“病みかわいい“をビジュアルコンセプトにするユニット、ぜんぶ君のせいだ。(以下、ぜん君。)のリーダー如月愛海が、8月25日に初のオーディオ・ドラマ付きノベル『縁罪』(読み:エンザイ)をリリースした。
細部にまでこだわりが感じられる作り込み。謎と伏線が絡み合い読み手を引き込む力作に、如月愛海のさらなる進化を感じずにはいられない。
これまでのアーティストとは異なるスタイルでの表現への挑戦。なぜノベル執筆という新たな一歩を踏み出したのか。如月にとってクリエイティブとは何なのか。彼女の強い眼差しの先に見据えているものに触れたいと、インタビューを行なった。(佐藤結衣)
たくさんあった物語の種から生まれた『縁罪』

――今回は初のノベルリリースということですが、ぜん君。としての活動も並行した忙しい日々の中で、いつから執筆されたのですか?
如月愛海(以下、如月):たぶん……2年前とかですかね。実は覚えていないんですよ。昔過ぎて(笑)。物語自体は書き始めて1〜2週間で完結していたんですけれどね。
――そんなに早くに!?
如月:はい、思いついたら書く感じで。「ナリ(主人公)ならこういう部分あるよな」みたいにふと思ったりするから、その都度メモにして缶カン入れておくみたいな。
――缶カンとはまた可愛らしいですね。
如月:本当はノートとかにまとめておくと便利なんですけどね。ライブで遠征するときは、そのメモをスマホで写真撮ったりして(笑)。ダンス練習終わりとか時間の合間を見つけては書き上げました。ただ、書いてみたはいいものの、本を作るにあたって文章のチェックから、本のデザイン、イラストの発注まで、すべて自分でやるスタイルだったので、そこからがまた大変で。納得のいくものができるまで時間をかけて準備をしたので、このタイミングでの発売になりました。
――もともと文章を書くことは好きだったんですか?
如月:そうですね。小さいころからドラマとか本の続きを自分で想像してメモするようになって。それから短編小説みたいなことは個人的にちょっとずつ書いていました。ジャンルもバラバラで、それこそ思いついたときに書いていた感じなので、世の中の多くの人に見せたいという願望は特になかったんですよ。メンバーが「読みたい」っていうから「どうかな?」って見せるくらいのものでした(笑)。そうしているうちに、ぜん君。の活動でもドラマCDなどの特典を作るときに脚本を書いたりして、今回本っていう形にしてみることになったんです。
――では、他にもたくさん物語はあったということでしょうか?
如月:はい。缶カンとかスマホの中にあるメモを合わせたら結構な量になりますね。その中で、今回1つの物語で本を作るって考えたときに、“死んでも叶えたい願い“をキーワードに『縁罪』の世界を広げていくことにしました。
2年の間で変わった物語のエンディング

――“罪を犯した人の願いを叶える“というテーマは、どこから着想を得たのでしょうか?
如月:「死んだ人も願い叶えたいよね」みたいなメモがあったんですよ。それがいつどんなところで思いついてメモをしたのか覚えていないんですけど。
――キャラクターたちにはモデルになるような方はいるのでしょうか?
如月:主人公のナリは、完全に自分でしたね。やっぱり自分が主人公だと、“こういうときどうやって言うかな“っていうセリフを考えやすくって。周りのメンバーは、街中で見かけた人だったり、コドモメンタルにいる人同士のサラブレッドだったり……。“この人のこういうのがいいな“と思ったところを抽出してキャラクターを作り上げています。それも思いついてはメモって缶カンへ、みたいな感じですね。
――主要キャラクター5名の個性が魅力的で、イラストもとても可愛らしいですね。
如月:ありがとうございます。そこはかなりこだわったところなのでうれしいです。イラストレーターさんには「髪の毛の色はもっとこういう感じのピンク色で」「肌の色はもう少し薄めで」「この子の服装はもうちょっとレトロな感じで」……みたいな細かな要望をお伝えして、本当に申し訳ないくらい何度も何度も修正をお願いしました。この子たちの服装についても、1人ひとりの持つ背景とリンクしている部分があるので妥協できなかったんですよね。もはや下巻のイラスト、受けてくれるかなって心配です(笑)。
――(笑)。カバー裏でノトがいなかったり、脳内の場面は白黒反転したデザインになっているのも、如月さんのアイデアですか?
如月:そうです! 私自身、本を手にとったとき、すぐにそこをチェックしたくなっちゃうので。何か仕掛けがあるかもしれないっていうワクワクがあるから、自分で本を出すならそこにこだわりたいなと。作中の白黒反転のページについては、そのほうが状況を理解しやすくなるからという理由もあるんですけど、実は脳内のシーンなのに黒くなっていないところもあって。そこも後々その理由が明かされていくみたいな……ああ、これネタバレしないように話すの大変ですね(笑)。
――たしかに。私たちはまだ上巻の内容しか知らないですが、如月さんの中ではすでに2年前に結末まで書き上がっているんですもんね(笑)。
如月:はい。あ、でもいろいろと見直している内に書き直したところもあるんですよ。実はラストも最初に考えていたものとは全然違うものになっています。やっぱり2年の間に私自身の環境の変化もありましたし、その間にたくさんの作品に触れてきたこともあって「もうちょっといいラストがあるじゃん!」ってなって。
――そうだったんですね。そのあったかもしれない別の世界線も気になるところです。上巻をリリースしてファンのみなさんからの反響はいかがでしたか?
如月:初ノベルということで、みなさんすごくやさしい眼差しで見てくださってありがたかったですね。もちろん辛辣な言葉もいただきましたが、それ以上に「面白かった」とか「描写がわかりやすい」といった、うれしい言葉もたくさん届いています。特に誤解なく伝わってほしいと思っていたところが、ちゃんと伝わっているのを見るとホッとしました。あとは、「この子が好き!」とか「この子がかわいそう……」っていう感想や、「こういう意味があると思う」って細かく考察している人もいて。そういう声を見るたびに、「本当にそれでいいの? いいのね?」みたいな神の視点で問いかけています(笑)。
――えー、怖い!(笑)
如月:あはは。物語は最後まで読んでみないとわからないものですから。みなさん、あまりにもやさしさで溢れているので、結末まで読んだときの反応が今から楽しみです!
――もともと本を読むのがお好きだったとお聞きしました。
如月:大好きです。もともと学生のころに本にハマって、1日2冊くらいのペースで読んでいた時期もあったんです。一気観しないと我慢できないタイプで(笑)。昔、山本文緒さんという方の作品を小説で読んだ時は、現実でも主人公が自分になっちゃった感覚があって。そのキャラクターの感情をずっと持っていたことがありました。そういうすごい作品って、ずっと忘れられないです。
――現実にも尾を引いてしまう作品ってありますよね。漫画やアニメはいかがですか?
如月:絵が描けたら漫画家にもなってみたかったんですよ! 兄の影響で『少年ジャンプ』系をよく読んでいましたね。『ONE PIECE』みたいな王道のものももちろん好きですけど、『サマータイムレンダ』とか『多重人格探偵サイコ』とか。浦沢直樹先生の『MONSTER』もアニメを何回も見ました。ミステリーとか刑事モノみたいな主人公がギリギリのラインにいるようなテーマの作品が好きなんですよね。生死のギリギリとか、善と悪のギリギリとか。犯罪をした人とそれを追う人の境目って本当はそんなにないんだよな、みたいなことを考えさせられる作品をよく観てきました。
――たしかに、ちょっとしたことがきっかけでゴロゴロッと人生が転落していくことってありますし、それがフィクションであってもゾワッとします。
如月:そうなんですよ。そうなっちゃう理由を、わかりたくないけどわかるというか。犯罪はダメなことですけど、そういうのを観ていると“人間って面白いな“と思って。物語を考える上でも、現実にあるかもしれないリアルな部分が感じられるほうが、ゾクゾクできるんじゃないかなと。
――小さいころドラマなどの続きを自分で考えていたとおっしゃっていましたが、その予想は当たることが多かったんですか?
如月:当たったときは「やっぱり!」って名探偵の気分になれるのでもちろん楽しかったんですが、当たらないときのほうが「この作品すごい!」って興奮しましたね。自分でも本当めんどくさい性格だなって思うんですけど、そういう視点でドラマとか映画を見るようになったら、ちょっとだけ映ったエキストラさんにも目がいくようになっちゃって。「もしかしたらこの人が犯人なんじゃ?」「今なんで読みかけていた本を閉じた? 主人公たちの会話を聞いていたんじゃない?」って、いろんな可能性を考えて見る楽しみを覚えてしまいました。だから、ネットでいろんな人が書かれている考察ブログとかも大好きです(笑)。
――そんなミステリー好きな部分が『縁罪』にもしっかりと反映されていますね。
如月:そうですね(笑)。テーマについては、ぜん君。にちょっと通じているなと思っている部分があって。ぜん君。って、人前に出さないような部分を歌ったり、表現したりするから。なんというか、生命力の強いライブをしているんです。人生って楽しい部分はもちろんありますが、そうじゃないところも必ずあるじゃないですか。だからこの本についても、せっかく書くのであれば、やっぱり人に出していない、苦しいほうにフォーカスを当てたいという気持ちはありました。