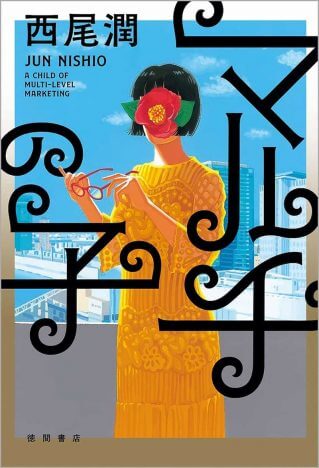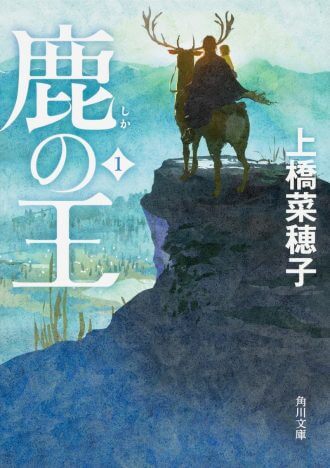不倫した夫が交通事故に遭い失踪……残された母子の選択は? 辻村深月『青空と逃げる』の問いかけ

因果応報、という言葉があるけれど、たいていの苦難は前触れなく理不尽に襲いかかってくる。「なんで自分がこんな目に?」「何も悪いことをしていないのに」と茫然としているうちに日常に入った亀裂が大きくなって、ずっと続くと信じていた“普通”に戻れなくなっていた。そんな経験をしたことのある人も、少なくないのではないだろうか。辻村深月の小説『青空と逃げる』の主人公である本条早苗と息子の力も、思いもよらぬ不運で平穏から追い立てられてしまった人たちだ。
きっかけは、劇団員として細々とキャリアを積んできた早苗の夫(力の父親)・拳が、人気女優の立つ舞台に客演として呼ばれたことだった。キャリアアップのチャンスを喜んだのもつかのま、女優が運転中に事故を起こし、助手席に座っていた拳も病院に運ばれる。ひとめで降板とわかるほどの大怪我、だけでなく、深夜の密会はダブル不倫ととり沙汰されたあげく、女優が亡くなってしまったため、世間の注目はいっせいに拳に注がれる。そして、夫の言い分を聞く気にもなれないまま、病院から遠ざかっていた早苗の知らぬ間に夫は退院し、姿をくらませた。語るのは、残された早苗たちの責任とでもいうように、連日押し寄せてくるマスコミ。女優の所属事務所エルシープロも拳の行方を知っているのではないかと疑い、迫る。近所に迷惑もかかるし、なにより力への悪影響を心配し、夏休みなのをいいことに早苗は友人の嫁ぎ先・高知の四万十へ逃げるのだけど……。
こうした経緯は、二人の逃避行を追ううち少しずつ明かされていくのだが、抱えている事情に反し描かれる情景は冒頭からとても爽やかで美しい。青空のもと、水面のきらめく四万十川で漁師の手伝いをする力の健やかさと、早苗の働く食堂でとびかう快活な声、常連たちとの交流。二人を照らす太陽が眩しければ眩しいほど、じりじりと迫る追手の不穏さが際立つ。この明るさのなかに二人は身を置き続けることはできないのだと、否応なしにつきつけられるのだ。
早苗の前に唐突に現れたエルシープロの男によって、親子はふたたび逃亡を余儀なくされる。力は、せっかくできた友達との約束を反故にすることになり、抵抗する余地も与えられないまま、母とともに四万十を脱する。わずか、十歳の少年である。おおよその事情を理解はしていても、母が悪いわけじゃないとわかっていても、どうして、という想いは消えない。明確な説明をしてくれない母への怒りもある。それでも、子どもである彼は、母についていくよりほかにすべはない。憤懣とやるせなさを抱え、早苗とともに兵庫の家島、大分の別府へと場を転じていく力はとても“いい子”だけれど、それはひとえに無力であるからだ。母を救うことも、状況を改善することも、そしてひとりで生きていくこともできない。なすすべがないから、耐えるしか選択肢がない。でもそれは、早苗も同じなのである。
もともとは拳と同じ劇団の女優だった早苗は、結婚を機に主婦となった。別府にたどりついた彼女がこんなことを思う場面がある。
〈四十近い自分の年齢を思うと、年を経ていることがかえって怖かった。若い頃なら許されるようなことも、自分にはもう許されないのではないか。〉〈職探しで面接に臨んだところで売り物にできるようなものがない。自分の人生経験の乏しさを、今更突きつけられているような気がした。〉
無為に時間を過ごしてきたわけじゃない。妻として、母として、家族を支えてきた。けれど夫がいなくなった今、経済的に追い詰められて、社会的な居場所を失っているのは確かだ。それは多くの中年女性が、人生を見つめ直したときに直面する問題なのではないかと思う。だからこそ、“逃げる”という道すら選べない人もいる。そんななか、早苗が一歩を踏み出せたのは、力がいたからだ。自分ひとりのことなら、耐え忍ぶことはできても、息子が傷つく未来をみすみす招くわけにはいかない。だから、説明する覚悟はいまだもてなくとも、それが息子をさらなる混乱に陥らせることになったとしても、最悪の“今”からとりあえず逃げることができた。それは、大いなる一歩だと思う。