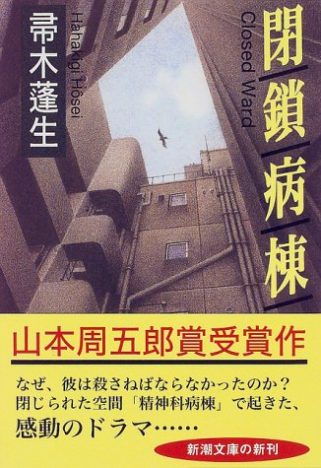萩原朔太郎、星新一、カフカ……作家にとっての「ひきこもり」とは? ステイホーム文学の多様性


本書『ひきこもり図書館 部屋から出られない人のための12の物語』は、13年間のひきこもり経験を持つ文学紹介者・頭木弘樹が選んだ、古今東西のひきこもり文学を収録。家にこもらざるを得ない今だからこそ誰もが興味深く読める一冊であり、読めばひきこもりに対する考え方の多様さに驚くこと請け合いなのだ。
たとえば、詩人の萩原朔太郎はエッセイ「病床生活からの一発見」の中で、ひきこもりを「休息」のようだと考える。健康だった時は、意義のある仕事を成し遂げたいと思っても自分には才能がないと憂鬱になることもあった。だが、病気になり床に臥してしばらくすると、普段感じていた焦りが無くなっていたことに気づく。
病気であるならば、人は仕事を休んで好いのだ。終日何もしないでぶらぶらとし、太々しく臥ていたところで、自分に対してやましくなく、かえって当然のことなのだ。無能であることも、廃人であることも、病気中ならば当然であり、少しも悲哀や恥辱にならない
こうして悠々自適の境地に達すると、一匹の蝿を眺めたり、昼食に何が出てくるかを想像したりするだけで一日飽きない。それどころか〈無味平淡なタダゴトの詩〉に感じていた正岡子規の歌や〈文字通りに退屈極まる文学〉と思っていた自然主義文学のよさに気づきさえしたというのだから、ひきこもりの効能恐るべしである。
星新一のショートショート「凍った時間」では、主人公のムジナはひきこもりを「役目」と捉える。勤め先の工場で、事故により放射能を持つ薬品を浴びてしまったムジナ。一命を取り留めたものの、脳以外の器官を全て人工の部品に入れ替えられる。見た目がほぼロボットとなり、奇異の目で見られるのを嫌って殺風景な地下室に閉じこもるムジナは思う。
できるものなら、もっと社会に役立ち、人に喜ばれるような生きがいを持ちたい。(中略)人に見られ、相手に不快な気分を味わわせないよう、ここに閉じこもっているのが、自分にできる、ただ一つの役目なのかもしれない
前書きで〈この図書館の目的は、ひきこもりを肯定することでも、否定することでもありません〉と編者が語るように、収録作はひきこもることに前向きな作品もあれば後ろ向きな作品もある。中には、ひきこもりの概念を揺さぶるような作品も存在する。
韓国の小説家ハン・ガンの短篇「私の女の実」(斎藤真理子 訳)には、一見するとひきこもる人間は出てこない。結婚を機に高層マンションに引っ越して同居を始めてから4年が経ち、〈私〉の妻の体調は突如悪化していく。病院で診察を受けても異常なし。一体何が原因なのか? 妻の独白から明らかとなるのは、〈痛ければ泣き、つねられれば叫ぶ子供のように、私はいつもひたすら、逃げ出したかったのです〉という、一つの場所に落ち着くことのできない彼女の性分である。つきまとう何かから逃れようと移動を続けてきた半生、それはひきこもりとイコールであり、体調不良は住まいに落ち着くことへの拒否反応だった。拒否反応はやがて奇妙な変化を遂げ、さらに〈私〉を困惑させることになる。
このように、さまざまなひきこもりの登場する本書。その何よりの魅力は、収録作の作者の他の作品も読んでみたくなるところにある。