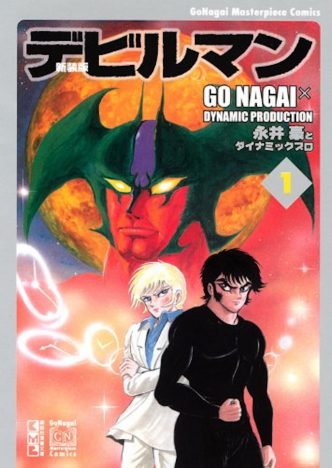『チェンソーマン』はなにが「恐ろしい」のか? 巧みな恐怖の描き方を考察

根源的恐怖に見る、間接的な恐怖の描き方
手足が斬り飛ばされたりと、スプラッター的な戦闘の多い本作だが、おそらく「怖くて(グロくて)目も向けられない」とまで感じる読者は少ないのではなかろうか。藤本タツキのペンタッチはドライで生々しさがなく、「スプラッター漫画」と呼べるほど猟奇的ではない、誰に勧めても大丈夫そうなポップさもある。
だが、コミックス8巻で「根源的恐怖」と呼ばれる「闇の悪魔」を登場させてから、この作品は明確に「恐怖」を読者に伝えようとしてくるのだ。
これまでも「永遠」「未来」「天使」といった、恐怖という言葉だけでは捉えにくい名の悪魔がいたのと反対に、それこそ「映画や物語が生まれる以前から」人類が恐れていただろう脅威を根源的恐怖、と分類するのだろう。
改めて言うと、「恐ろしいもの」を映画や漫画で表現することは難問である。体験しなければ分からないその感覚を、(物理的に)安全な場所にいる観客に伝えなければならないからだ。
だから恐怖の伝え方にはいくつかのパターンがあり、「恐ろしいものを観客にだけ見せる」「恐ろしいものとそれを怖がるキャラクターをセットで見せる」「恐ろしいものを直接見せず、怖がるキャラクターを見せる」「何も見せない」などがある。

特に「恐ろしいものを直接見せず、怖がるキャラクターを見せる」の手法では、1999年の映画『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』が有名だろう。そしてこの手法の欠点とは、「キャラクターがさんざん怖がっていた対象を直接見せてしまうと、観客が拍子抜けしやすい」という法則にある。
例えば「世界で一番ヒットした音楽」や「最も美しい絵画」を登場させたかったとしても、それはスタッフが具体的に制作しない方が無難である、という法則に似ている。つまり、観客の期待するハードルが高くなりすぎるからだ。
この法則で言えば、8巻でその姿が直接描かれる「闇の悪魔」は、先述したように目を背けたいほど、という怖さや気持ち悪さはない。だが、確かに「恐怖」は充分に伝わってくる。登場前からの、デンジたちを地獄に招く超越的な描写、呆気なく捧げられる生贄たちの命、他の悪魔が語る「私達は彼らに敵意を向けられた瞬間死にます」「自殺の許可を…」という圧倒的な絶望のセリフによって高められた恐怖は、闇の悪魔が直接描かれた後でも「根源的恐怖」の説得力を維持している。
だが、そこで「読者は闇の悪魔を直接見ているのに、死にたくなるほど怖くはない」という現実とのズレに突き当たるだろう。まさに、映画の劇中で「聴くと失神するほどの名曲」が実際に流れたとしたら、失神する観客が出るはずだ、というように。
ここから『チェンソーマン』が独特なのは、「恐怖とは何か」ということ自体を読者に伝えるセリフが各所に存在することだ。特に、作中で一貫したメッセージとして「知らない方が幸せである」というキャラクターたちの考え方がある。
「都会のネズミよりも田舎のネズミがいい」という価値観を持つキャラクターがいたり、クァンシは「無知で馬鹿なままでいること」を幸福の秘訣だと言う。さらに8巻でクァンシは「バカになれ」とデンジに伝えるが、まさしく本作は、無知で愚かなゆえに単純だった「田舎」のデンジが、「都会」で生活を豊かにしていくほど単純なバカではいられなくなっていく……という変化と成長の切なさを描いている。
「幸福」について語るこれらのメッセージが、「恐怖」に繋がっていくのは、8巻のラストだ。宇宙の悪魔が「森羅万象の知識」を相手の脳に流し込むことで発狂させた後(ここでも「知らない方が幸せ」を連想する)、目隠しをさせられた岸辺がマキマのクァンシ斬殺に立ち会うシーン。
この時点で、読者にとってもマキマの能力は謎のままであり、なぜ圧倒的な強さで周囲に警戒されているのかも分からない。そもそも目隠しをさせて「見せたくない」理由すら謎だ。
見せられないものは、先述したように、見えるものより恐ろしい。斬殺の返り血を浴びた岸辺は、クァンシの処分が終わった後でも目隠しを外そうとせず、立ち固まったまま「何も見たくない」と呟く。
この「何も」、にはダブルミーニングがある。読者がひとつ連想するのは、それまで強調されていたマキマの得体の知れなさ、その不気味さだろう。彼女と敵対する意思のある岸辺にとって、目を塞いだままでいたいほど恐怖に支配されていたのではないか……、と。
そしてもう一つ、過去にバディだったクァンシとの個人的な関係だ。これはコミックス8巻の巻末に「岸辺のことを知ろう!」という3頁の描き下ろしがあるのだが、なぜか読者の側が「知りたくなかった」と感じざるをえない過去が知れるので、ジャンプ連載の読者はコミックスで確かめてほしい。
こうして『チェンソーマン』では、「知らない方が幸せ」という人生訓のようなメッセージが、「見たくない恐怖」と密に重なってくるのだと理解できてくる。映画的な演出法にかぎらず、「恐怖とは何か」、を読者が頭で納得できるようなセリフを埋め込むことで共感性を上げてくる所に、作者の独特な巧みさがある。
そして8巻から続く第71話は、「日常回」と呼べなくもない休息のエピソードだが、共感性を高めようとする作者の演出は止まらない。闇の悪魔がトラウマとなって幼児退行してしまったパワーを描く回だが、その怖がり方というのが「一人でトイレやお風呂に入れない」「一人で眠れない」「後ろに何かが立ってる気がする」「ドアの向こうに何かいる気がする」といった、誰でも幼児期に体験したことがあるような、別の意味で「根源的」な恐怖なのだ。
人類が闇を恐れてきたという本能的な記憶は、電気に溢れた文明社会ではピンと来にくいかもしれない。だが「小さな頃はおばけが怖くて仕方なかった」という「あるある」ネタで表現されると、物覚えのいい人はダイレクトに思い返す羽目になるだろう。少なくとも、「パワーが怯えているであろう恐怖」の始末の終えなさは、(作中のデンジ同様)「マジで怖かったんだな……」と文句も言いにくくなる。
このように、『チェンソーマン』は恐ろしいものをただ描くだけでなく、間接的な方法で私たちに「恐いという感覚」を連想させようとする。その絡め手のような技術が、スッキリとした見やすい絵柄と「恐怖」のテーマを両立させているのだ。
最後に、「悲劇」の最も名高い古典である、ギリシア悲劇『オイディプス王』を紹介したい。主人公のオイディプスが事件を解決しようと謎解きを進めた結果、「真相を知る」ことで自らの父殺しと、実母を妻に娶ったという認めがたい禁忌が発覚してしまう。
オイディプスは運命を嘆き、もう何も見たくないし聞きたくもない、と自ら両目を潰して放浪することで結末となるのだが、8巻以降にあたる『チェンソーマン』の読者もまた、「次回のお話」を知りたくない、しかし読んでしまうだろう、という別の恐怖と隣り合わせの気分を味わわされている。それほどに、「続きが楽しみ」な漫画なのだ。
■泉信行
漫画研究家、ライター。1980年奈良生まれ。2005年頃から漫画表現論の研究発表を始め、現在は漫画、アニメ、VTuber他について執筆。共著に『マンガ視覚文化論』、『アニメ制作者たちの方法』など。@izumino
■書籍情報
『チェンソーマン』(ジャンプ・コミックス)既刊8巻
著者:藤本タツキ
出版社:集英社
https://www.shonenjump.com/j/rensai/chainsaw.html